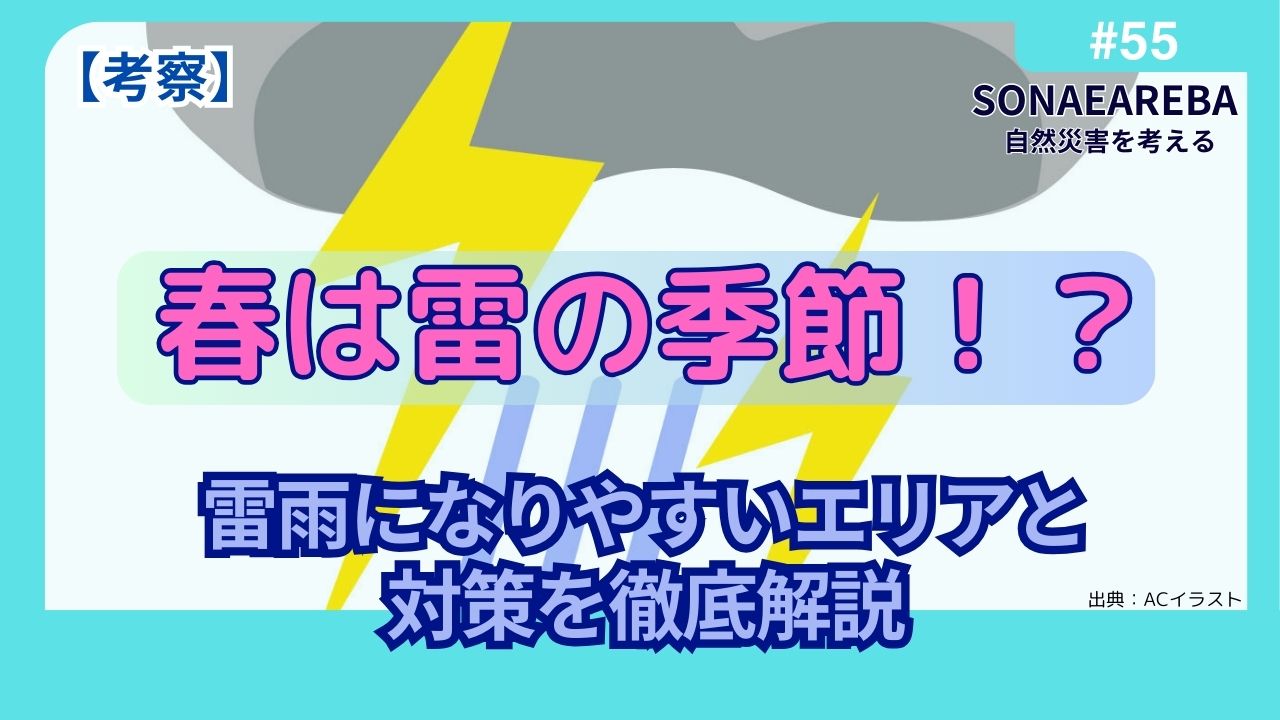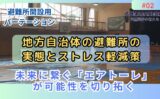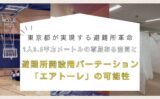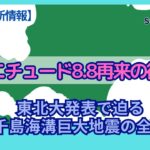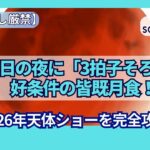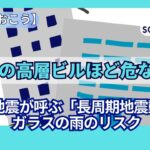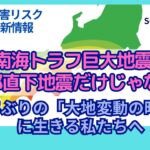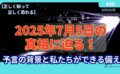この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
気温が上がり始め、桜が咲く春の季節。
穏やかなイメージがある春ですが、
実は雷の活動が活発になる時期でもあるのを
ご存知でしょうか?
今日の天気予報で「春雷に注意」という
フレーズを耳にしたことがある方も
多いのではないでしょうか。
「春雷(しゅんらい)」は
古くから季語としても親しまれてきました。
今回は、春に雷が発生するメカニズムと、
日本のどのエリアで雷雨が発生しやすいのか
について、最新データを交えながら
詳しく解説していきます。
春に雷が鳴るのはなぜ?春雷のメカニズム
まず気になるのは、
「なぜ春に雷が鳴るのか?」
という点ですよね。
雷といえば真夏のイメージが
強いかもしれませんが、
春も雷が発生しやすい季節なのです。
夏の雷と春雷の違い
夏の雷(熱雷)と春雷は、
発生するメカニズムが異なります。
夕立をもたらす夏の雷は、
強い日差しによって地面が
暖められることで発生します。
地面に温められた空気は強い上昇気流となり、
対流圏と成層圏の境目にまで達して、
背の高い積乱雲(かみなり雲)を形成します。
そこから雷が発生するのです。
一方、春雷は寒冷前線に伴って発生します。
冬の寒気をもたらすシベリア高気圧の勢力
が弱まると、偏西風に乗って移動性の高気圧
と低気圧が交互に西から東へと
訪れるようになります。
この低気圧は暖かい空気と冷たい空気の境目を
示す前線を伴うことが多いのです。
「界雷」の一種としての春雷
春雷は「界雷(かいらい)」と呼ばれる
雷の一種です。
界雷とは、暖かい空気の下に冷たい空気が
潜り込み、前線付近で発生する雷のことを
指します。
季節に関係なく、また時間帯も
決まっていません。
寒冷前線付近では、
冷たい空気に潜り込まれた暖かい空気が
急に上昇するので、積乱雲が発生します。
そして、その積乱雲から春雷が発生する
というわけです。
春雷と「ひょう」の関係
春雷の特徴として、
「ひょう」が降りやすいという点があります。
ひょうとは、直径5mm以上の氷の粒のこと
をいいます。
積乱雲はとても背が高いため、雲の頂上付近の
気温は夏でも-40℃近くになり、小さな水と
氷が存在しています。
積乱雲の中には強い上昇気流があるため、
氷の粒が長く空中にとどまることで
大きく成長し、直径5mm以上になると
「ひょう」となります。
夏であれば落下中に溶けて雨になることが
多いのですが、春先はまだ気温が低いため、
ひょうが溶け切らずに地上まで落ちてくること
があるのです。
これが農作物に被害をもたらすことが
あるため、春雷は農家にとって悩ましい現象
でもあります。
日本のどこで雷が多いのか?統計からみる雷多発地域
次に、日本のどのエリアで
雷が多いのかを見ていきましょう。
気象庁の統計データをもとに、
雷の多い地域について解説します。
年間を通じた雷日数ランキング
全国各地の気象台や測候所の目視観測に
基づく雷日数(雷を観測した日の合計)の
平年値(1991~2020年までの30年間の平均)
によると、年間の雷日数は東北から
北陸地方にかけての日本海沿岸の観測点で
多くなっています。
特に金沢は年間45.1日と最多を記録しており、
さながら「雷の都」とも言えるでしょう。
これは、夏だけでなく冬も雷の発生数が
多いためです。
2023年の調査による都道府県別の
落雷日数ランキングは以下の通りです:
- 北海道:140日
- 新潟県・鹿児島県:120日(同率2位)
- 秋田県
- 石川県
- 福井県
- 山形県
このように日本海側の地域を中心に、
九州南部でも雷日数が
多い結果となっています。
一方、太平洋側の都道府県は比較的雷日数が
少ない傾向にあります。
暖候期(春~夏)の雷日数チャンピオンは?
興味深いことに、
春から夏にかけての暖候期(4~9月)に
限ってみると、ランキングが変わってきます。
栃木県宇都宮の雷日数は
平年値で24.2日となり、
この数字は全国で最多なのです。
北部に千~2千メートル級の山岳部を
抱える栃木県では、夏季はその斜面を
南から吹く風が上昇気流となって駆け上り、
積乱雲を発達させます。
そのため、栃木県は「暖候期の雷日本一」
というわけです。
なぜ日本海側で雷が多いのか?
北海道や北陸地方、
東北地方などの寒い地域に落雷が多いのは、
「冬季雷」と呼ばれる冬型の気圧配置時に
見られる雷が発生することが主な原因です。
特に新潟から福井にかけての日本海側は
落雷が多いエリアとして知られています。
その理由は、
日本海を流れる「対馬海流」の暖かい海面に
シベリアからの冷たい空気が流れ込むと、
水蒸気が盛んに供給されて冬の積乱雲が
発生するためです。
この積乱雲が発達しながら季節風の影響で
日本海側に流れてくるため、日本海側の道府県
に冬の落雷が多くなるのです。
実際に、新潟県沿岸の冬の海面水温は
10~14℃と高く、新潟の冬の気温の平年値で
ある3.7℃よりもかなり高いことが、
この現象を裏付けています。
春雷から身を守るための対策
春雷は美しい春の風物詩である一方、
時に危険をもたらすこともあります。
ここでは、春雷から身を守るための
基本的な対策をご紹介します。
雷に遭遇したときの基本対応
- 屋外にいる場合:
できるだけ早く建物や車の中に
避難しましょう。 - 高い場所や開けた場所を避ける:
ゴルフ場や野球場、サッカー場などの
開けた場所や、山の頂上などの高い場所
は落雷の危険が高まります。 - 木の下は危険:
木に落雷した場合、
側撃雷(側方への放電)の危険が
あります。 - 金属製の物から離れる:
傘や釣り竿など、長く金属製の物は
避けましょう。 - しゃがむ姿勢をとる:
避難する場所がない場合は、
両足をそろえて低い姿勢で
しゃがみましょう。
参考リンク:
NHK WEBサイト
「雷(カミナリ)」対策 落雷の注意点は?
かみなりしゃがみ
家の中での対策
- 電化製品のプラグを抜く:
テレビやパソコンなどの電化製品は、
落雷による過電流から守るために
プラグを抜いておくと安心です。 - 窓やドアを閉め部屋の真ん中へ:
雷に伴う強風や雨、飛来物によるガラスが
割れることから身を守りましょう。 - シャワーや入浴を避ける:
水は電気を通しやすいため、
雷が鳴っている間はシャワーや
入浴を避けることをお勧めします。
ひょう対策
春雷ではひょうが降る可能性もあります。
ひょうは農作物に
大きな被害をもたらすこともあるので、
家庭菜園などをしている方は注意が必要です。
- 天気予報をこまめにチェック:
ひょうを伴う雷雨の予報が出ている場合
は、植物をカバーするなどの対策を。 - 車を保護:
可能であれば車をガレージや屋根のある
場所に移動させましょう。 - 外出を控える:
大きなひょうは人体にも危険を及ぼす
可能性があります。
雷情報の入手方法と活用法
最後に、雷情報を入手する方法と、
その情報の活用法についてご紹介します。
雷情報を入手できるサイト・アプリ
- 気象庁ウェブサイト:
気象庁の公式サイトでは、
雷注意報などの防災情報を確認できます。
気象庁WEBサイトはここから - tenki.jp(日本気象協会):
雷レーダーで実況と予報を確認できます。
日本気象協会WEBサイトはここから - フランクリン・ジャパン「雷ぶらり」:
雷統計データや落雷密度などの情報を
提供しています。
フランクリン・ジャパン公式サイトは
ここから
雷情報の見方と活用法
雷レーダーなどの情報を見る際は、
以下のポイントに注目すると良いでしょう:
- 雷活動度:
雷の活動がどの程度活発かを示す指標です。 - 移動方向:
雷雲がどの方向に移動しているかを確認し、
自分のいる場所に近づいてくるかどうかを
判断します。 - 雷の種類:
夏の熱雷と異なり、
春雷は前線に伴うことが多いため、
前線の動きもチェックしましょう。
ウェザーニュース
雷レーダーはこちらから
まとめ:春の雷雨に備えて
今回は「春は雷の季節!?
雷雨になりやすいエリアは」
というテーマで、春雷のメカニズムと
日本の雷多発地域について解説してきました。
春雷は寒冷前線に伴って発生する
「界雷」の一種であり、
夏の熱雷とは異なるメカニズムで生じます。
年間を通じた雷日数は、
金沢をはじめとする日本海側で多く、
特に北海道や北陸、東北地方などの
寒い地域で多いことがわかりました。
一方、暖候期(4~9月)に限ると、
栃木県が「雷日本一」となります。
雷情報は、気象庁や各種気象サイト、
アプリから入手できます。
これらの情報を活用して、
春の雷雨に備えましょう。
自然の驚異である雷は、時に私たちに
危険をもたらすこともありますが、
適切な知識と対策があれば、
その被害を最小限に抑えることができます。
春の訪れを告げる「春雷」を、
安全に、そして風情ある自然現象として
楽しむことができれば幸いです。
皆さんも、天気予報や雷情報を
こまめにチェックして、
安全で快適な春をお過ごしください!
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。