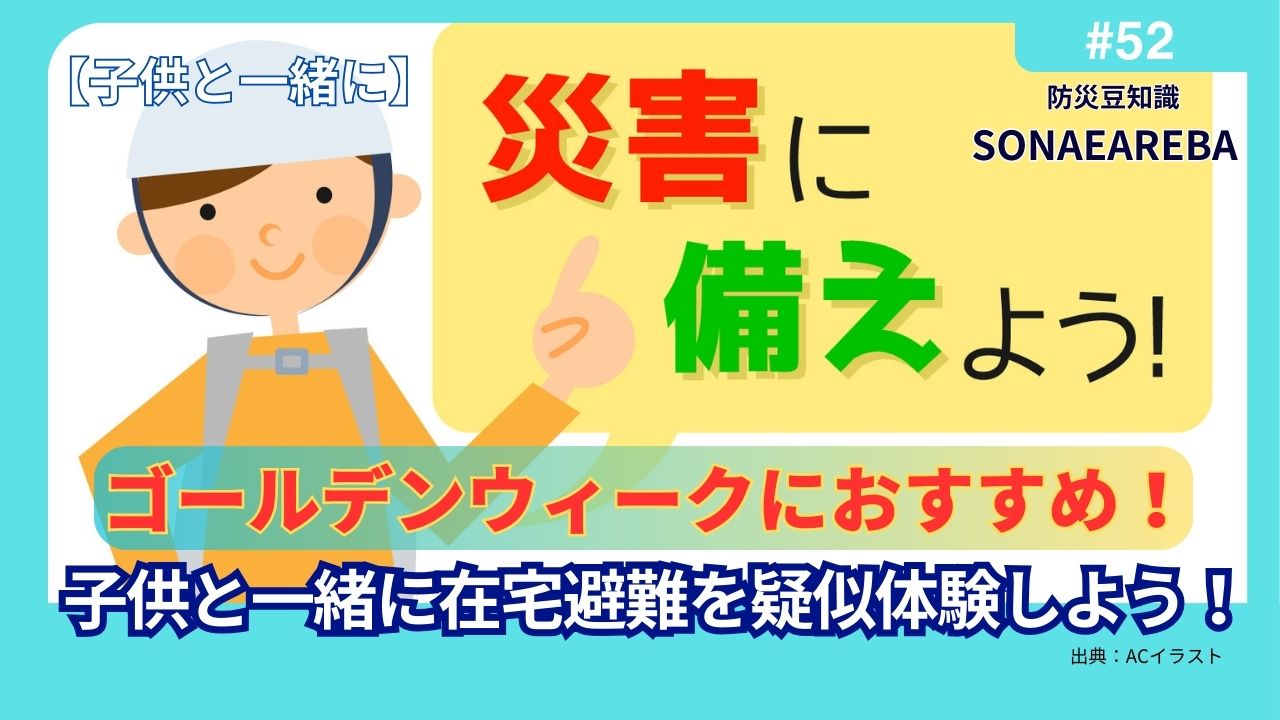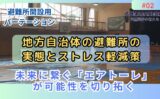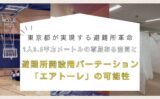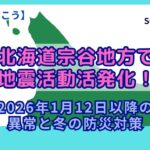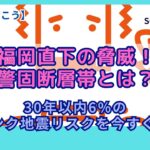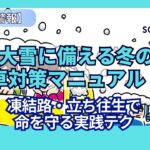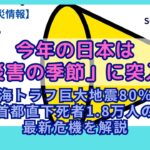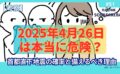本記事はAmazonアソシエイトとして、
商品を紹介して収益を得る可能性があります。
こんにちは!SONAEAREBAです。
ゴールデンウィークの家族イベントを
お探しではありませんか?
今年のゴールデンウィークは、
楽しみながら防災力をアップできる
「おうちで避難所訓練」に
チャレンジしてみませんか。
近年頻発する地震や災害に備え、
家族で防災意識を高めるこの取り組みは、
子どもたちの生きる力を育むとともに、
家族の絆を深める貴重な機会となります。
本記事では、
実際に行える在宅避難の疑似体験について、
準備から実施方法まで詳しくご紹介します。
在宅避難とは?その重要性を知ろう

私たちが暮らす日本は地震大国と呼ばれ、
毎年のように各地で地震が発生しています。
災害時、多くの方が避難所に行くことを
考えますが、実は自宅が安全な場合は
「在宅避難」という選択肢があることを
ご存知でしょうか?
「在宅避難」とは、
自宅が安全で倒壊や浸水・火災などの
リスクがない場合に、自宅でそのまま生活
を続ける避難方法のことです。
慣れない環境での集団生活となる
避難所よりも、住み慣れた自宅で
避難する方がストレスが少なく、
感染症対策にもなるため、
近年注目されています。
また、都心部では避難所が足りず、
避難所難民になるというデータもあります。
自宅が危険な状況でない場合は
「在宅避難」が推奨されているのです。
ご自宅での耐災力を高めておくことで、
本当に助けが必要な人に行政の力を
集中させることができます。
在宅避難のために知っておきたいこと
災害時に在宅避難をするためには、
事前の準備が欠かせません。
電気・ガス・水道といったライフラインが
止まった状態を想定し、最低でも7日間は
自力で生活できる準備が必要です。
特に注意すべきなのは、
地震発生後72時間(3日間)です。
この時間は
「自力で生き残らなければならない時間」
とも言われています。
災害時の人命救助において、
発災後72時間は「デッドライン」と呼ばれ、
生存率が急激に低下すると言われています。
よって、人命救助が最優先されるからです。
国や自治体の支援体制が十分に整うまでは、
自分たちの力で乗り切る必要があるのです。
ゴールデンウィークの連休中に
家族で在宅避難を疑似体験することで、
実際に災害が起きた際の不安やパニックを
減らし、冷静に行動するための知識や経験
を得ることができます。
子どもたちにとっても、
楽しみながら生きる力を学ぶ
貴重な機会となるでしょう。
子どもと一緒に楽しく学ぶ!在宅避難疑似体験の準備
私が子どもたちと在宅避難の疑似体験を
行うときは、まず事前の準備から
子どもたちを巻き込むようにしています。
子どもが主体的に参加することで、
防災意識が自然と身につくからです。
必要なものをチェックリストで確認

在宅避難を成功させるためには、
以下のような準備が必要です:
- 飲料水の確保:
1人1日2~3リットル×家族の人数×7日分 - 非常食の準備:
レトルト食品、缶詰、乾パンなど - 照明器具:
LEDランタン、懐中電灯、ヘッドライト - 調理器具:
カセットコンロ、ボンベ(8本以上が目安) - トイレ対策:
携帯用トイレ、簡易トイレ - 衛生用品:
除菌シート、ボディシート、歯磨きシート - 情報収集手段:
ラジオ、モバイルバッテリー、ポータブル電源 - 防寒・暑さ対策:
防寒具、寝袋、アイマスク、耳栓など
これらを子どもと一緒に
チェックリストを作って確認していくと、
楽しみながら準備できます。
特に、家にあるものを探す
「宝探し」のように進めると、
子どもたちは喜んで協力してくれるでしょう。
ローリングストックで無理なく準備
また、日常生活に取り入れやすい
「ローリングストック法」も
子どもと一緒に始めるのがおすすめです。
ローリングストックとは、
日頃から少し多めに食材や日用品を購入し、
古いものから順番に使って、
定期的に新しいものを補充する方法です。
これにより、いざという時に
「賞味期限切れで使えない」という事態を
防ぎ、普段から食べ慣れたものを非常時にも
食べられるメリットがあります。
子どもと一緒に、
今晩の献立をローリングストックの食材で作る
「練習」をするのも良いでしょう。
実際に使ってみることで、
災害時に何が必要か、実感を持って
理解できます。
子どもと体験する1泊2日の在宅避難訓練プログラム
実際に行う在宅避難訓練は、
単なる「不便な生活体験」ではなく、
家族で楽しむイベントとして
企画することが大切です。
特にゴールデンウィークは、
通常の日常から少し離れて新しいことに
チャレンジするのに最適な期間です。
ここでは、子どもたちと一緒に行う
1泊2日の在宅避難訓練の
具体的なプログラム例をご紹介します。
1日目のプログラム例
午前:防災についての事前学習と準備
- ハザードマップの確認
- 一時集合場所や
避難所の場所の確認 - 家族との連絡方法の確認
- 自宅の安全点検
(家具の固定状況など)
昼食:非常食で食事体験
- カセットコンロを使った簡単調理
- 災害時に食べるレトルト食品や
缶詰の試食会 - 水の使用量を記録して
節水意識を高める
午後:避難経路の確認ウォーク
- 実際に避難所までリュックを
背負って歩いてみる - 公衆電話の場所や使い方を確認
- 地域の危険箇所や安全な場所を
マップに記入
夕方~夜:在宅避難生活体験
- 「電気・ガス・水道が使えない」
と想定した生活開始 - LEDランタンや懐中電灯だけでの生活体験
- 簡易トイレの設置と使用体験
- 非常食での夕食づくり
(明るいうちに準備するのがおすすめ)
就寝:避難所での就寝を想定
- 硬いフローリングでの就寝体験
- 電気をつけたままでの就寝
(避難所では消灯しないことが多い) - 寝袋やマット、アイマスク、耳栓などの
防災グッズの効果検証
2日目のプログラム例
朝:非常時の朝の過ごし方
- カセットコンロでお湯を沸かしての
朝食づくり - 水を使わない洗顔・歯磨き体験
(ウェットティッシュ、歯磨きシート)
午前:振り返りと反省会
- 家族でのディスカッション
(何が不足していたか、
何が役立ったかなど) - 今後の改善点やさらなる準備の検討
- 子どもたちの気づきや感想を共有
この1泊2日の体験を通じて、
子どもたちは自分の命を守る大切さや、
日ごろからの備えの重要性を
実感することができます。
また、
家族が協力して困難を乗り越える経験は、
子どもの自己肯定感や問題解決能力の向上
にも繋がります。
子どもが楽しめる!在宅避難クエストの工夫
子どもたちに防災を楽しく学んで
もらうためには、ゲーム感覚で取り組める
工夫が必要です。
私が実践している
「在宅避難クエスト」をご紹介します。
こちらの本を参考にしました。


セーフティーゾーン探しゲーム
セーフティーゾーンとは、
地震で大きな揺れがあったとき、
物が落ちてきたり倒れてきたりしない
安全な場所のことです。
部屋の中で安全な場所を子どもたちに
探してもらい、家族で相談しながら
「ここは安全?危険?」とクイズ形式で
進めると楽しく学べます。
防災バッグ詰め競争
防災バッグに必要なものをリストアップし、
制限時間内に家の中から集めてくる
競争をします。
集めてきたものが本当に必要かどうかを
家族で判断し、点数をつけることで、
子どもたちは楽しみながら優先順位を
学ぶことができます。
ブラックアウトチャレンジ
夜の一定時間(1~2時間程度)、
電気を消して過ごす体験をします。
LEDランタンや懐中電灯だけで、
読書や食事、トイレなどの日常生活が
できるかチャレンジします。
子どもたちは「サバイバル体験」として
楽しめるでしょう。
水を使わない生活体験
朝の歯磨きや洗顔を水を使わずに行う
チャレンジです。
ウェットティッシュや歯磨きシートなどを
使って、どれだけきれいにできるか
競争します。
これにより、水の大切さと節水の意識が
自然と身につきます。
これらのクエストは、
オープンハウスグループが開催した
「子どもと学ぶ在宅避難!
おうちのサバイバル体験」
イベントでも実施され、参加した親子からは
満足度100%という高評価を得ています。
楽しみながら学ぶことで、
子どもたちの防災への関心が高まるのです。
在宅避難時に特に注目したい「耐災力」とは
最近の防災対策では
単なる「防災」ではなく、
「耐災力」(たいさいりょく)
という考え方が重視されています。
これは
「大きな災害が起こった際に命を守る力」
のことです。
耐災力を高めるための3つのキーワード
耐災力を高めるために
重要な3つのキーワードを
覚えておきましょう:
- セーフティーゾーン:
地震の揺れで物が落ちてこない、
家具が倒れてこない安全な場所 - 在宅避難:
自宅が安全な場合、慣れた環境で
避難生活を送る方法 - ローリングストック:
日常的に使いながら備蓄する方法
これらを子どもたちにも分かりやすく説明し、
家族全体で意識することが大切です。
子どもと一緒に確認したい家の中の安全対策
家の中の安全対策は、
子どもと一緒に確認すると良いでしょう:
- 背の高い家具にはつっかえ棒を
設置して転倒を防ぐ - 食器棚や本棚には飛び出し防止対策をする
- 机が横滑りしないように足に滑り止め
を貼る - 窓ガラスには飛散防止フィルムを貼る
これらの対策を子どもと一緒に行うことで、
なぜそうするのかを理解させ、
防災意識を高めることができます。
実際の家族での体験談と学び
私自身も昨年のゴールデンウィークに家族で
在宅避難の疑似体験を行いました。
当初、子どもたちは
「楽しいキャンプみたい!」
と軽い気持ちでしたが、
実際に電気やガス、水道を使わない生活を
体験することで、様々な気づきがありました。
我が家の体験から学んだこと
予想外だった非常食の量
実際に非常食だけで食事をしてみると、
想像以上に量が少なく感じました。
特に子どもたちは「おなかがすいた」
と言うことが多く、備蓄量の見直しが
必要だと気づきました。
水の大切さを実感
トイレや手洗い、食器洗いなど、
日常生活で当たり前のように使ってい
る水の量に気づかされました。
特に子どもたちは
「お風呂に入れないのは辛い」
と感じていました。
情報収集の重要性
スマートフォンの充電が切れると
情報が得られなくなることを実感。
ポータブル電源やソーラーチャージャーの
必要性を強く感じました。
家族のコミュニケーションが増えた
テレビ、YouTube、switchなどの
電子機器が使えない環境では、
家族で会話をしたり、
カードゲームや読書をして
過ごす時間が増えました。
これは思わぬメリットでした。
この体験を通じて、
子どもたちは防災への意識が高まった
だけでなく、普段の生活のありがたさや
家族の絆の大切さも実感できたようです。
他の家庭でも実践されている在宅避難訓練の事例
全国各地で、家庭や地域ぐるみでの
在宅避難訓練が実施されています。
参考になる事例をいくつかご紹介します。
東村山市の「ブログ回覧板を活用した安否確認訓練」
東村山市の自治会では、
ブログの回覧板機能を利用した安否確認訓練
を実施しています。
災害時に電話での確認が困難な場合でも、
ブログのコメント機能を使って安否を
確認する方法です。
この方法は、
高齢者も含め約7~8割の住民をカバーでき、
外出しなくても安全に情報共有ができる
利点があります。
ブログを見られない方向けには、
災害伝言掲示板への書き込みや電話確認も
併用しているそうです。
渋谷区の「おうちで避難所訓練」
渋谷区では、ゴールデンウィークを利用した
「おうちで避難所訓練」が開催されました。
各家庭で都合の良い日に1泊2日の在宅避難を
想定して過ごし、その体験をオンラインで
共有する取り組みです。
「地震で電気・ガス・水道」が止まり、
使えないという設定で防災グッズを
使いながら過ごすことで、
家庭ごとの課題や改善点が見えてくる
とのことです。
オープンハウスグループの「子どもと学ぶ在宅避難」イベント
2025年3月に開催された
「子どもと学ぶ在宅避難!
おうちのサバイバル体験」
では、親子45名が参加し、楽しく学びながら
耐災力をアップさせるプログラムが
実施されました。
このイベントでは、
在宅避難クエストや非常用トイレの設置体験、
常温保存食のランチ試食など、体験型の
アクティビティが好評だったようです。
参加者アンケートでは満足度100%という
結果が出ており
「体験型・経験できるイベントだったのが
良かった」
「子どもを連れて楽しく学べるイベントが
少ないので、ぜひまた参加したい」
といった声が寄せられています。
在宅避難を成功させるための便利グッズと活用法
在宅避難を快適に過ごすためには、
いくつかの便利なグッズが役立ちます。
実際に我が家で活用している
便利グッズとその使い方をご紹介します。
1. LEDランタンライト
停電時でも室内全体を明るくするには、
電池式のLEDランタンが大活躍します。
複数箇所に置くことで、
家全体を明るく保つことができます。
また、
ヘッドライトがあれば両手が使えるので、
料理や読書などの細かい作業に便利です。
2. 水が不要な衛生グッズ
水が使えない状況でも清潔を保つために、
以下のようなグッズを用意しておくと
安心です:
- 除菌シート
- 大判のボディシート
- 口腔ケア用ウェットティッシュ
(歯磨きシート・液体歯磨き) - ドライシャンプー
これらを使えば、
お風呂に入れなくても最低限の清潔さを
保つことができます。
3. カセットコンロとボンベ
東日本大震災の経験から、
ライフラインの中で
最も復旧に時間がかかったのはガス
だったそうです(約5週間)。
カセットコンロとボンベがあれば、
温かい食事を取ることができ、
特に寒い季節には心身の健康を保つ上で
重要です。
4人家族の場合、カセットコンロ2台以上、
ボンベ8本以上を目安に備えておくと
良いでしょう。
4. ポータブル電源
スマートフォンの充電や、小型家電の使用に
欠かせないのがポータブル電源です。
情報収集や家族との連絡手段を確保するため
に、あらかじめ充電しておくことが大切です。
最近は災害時だけでなく、
アウトドアでも活用できる商品が多いので、
家族でキャンプに行く際にも使えて
一石二鳥です。
5. 簡易トイレ
トイレは災害時に最も困る問題の一つです。
水が使えない場合でも使用できる簡易トイレ
を家族の人数分×7日分程度用意しておくと
安心です。(目安は平均1日1人当たり5回)
子どもが使いやすいタイプを
選ぶことも重要です。
子どもと一緒に試しておきたいこと
これらのグッズは、
実際に使ってみないと使い方が
分からなかったり、想定外の問題が発生する
ことがあります。
ゴールデンウィークの在宅避難訓練で
一度試しておくことで、いざという時に
スムーズに使うことができるようになります。
特に子どもには、
遊び感覚でこれらのグッズの使い方を
教えておくと良いでしょう。
例えば、「暗闇探検隊」として
ヘッドライトやランタンを使った暗闇での
行動訓練や、「サバイバルクッキング」として
カセットコンロでの調理体験などが
効果的です。
こちらの本を参考にしました。
在宅避難訓練の体験を次につなげるための振り返り方
在宅避難訓練を行った後は、
家族での振り返りが非常に重要です。
この振り返りを通じて、
体験で得た気づきを実際の防災対策に
活かすことができます。
家族会議で共有する5つのポイント
訓練後の家族会議では、
以下の5つのポイントについて
話し合うことをおすすめします:
- 良かった点:
どの準備や対策が役立ったか - 困った点:
予想外の問題点や不足していたもの - 改善点:
次回までに準備しておくべきこと - 子どもの気づき:
子どもたち自身が感じた課題や学び - 家族の役割分担:
実際の災害時に誰が何をするか
特に子どもたちの意見は、
大人では気づかない視点が含まれていること
があります。子どもの発言をしっかり聞き、
次の防災対策に取り入れることで、
防災への関心や主体性を育むことができます。
オンラインでの情報共有も効果的
SNSやブログでの発信、
地域のLINEグループでの共有など、
様々な方法で体験を共有することで、
防災の輪を広げることができるでしょう。
防災計画の見直しと改善
振り返りを通じて見つかった課題は、
すぐに家庭の防災計画に反映させることが
大切です。
例えば:
- 足りなかった備蓄品の追加購入
- 家具の固定や安全対策の強化
- 避難経路や連絡方法の再確認
- 新たな防災グッズの検討
このサイクルを繰り返すことで、
家族の防災力は着実に高まっていきます。
アイリスオーヤマの防災特集
まとめ:ゴールデンウィークだからこそできる家族の防災力アップ
今回ご紹介した
「子どもと一緒に在宅避難を疑似体験」は、
ゴールデンウィークの連休中だからこそ
実践しやすい家族イベントです。
1~2日の体験でも、
実際に行うことで得られる気づきは
非常に大きいものになるでしょう。
防災は「非日常」から「日常」へ
防災というと特別なことのように感じますが、
本当は日常生活の延長線上にあるものです。
ローリングストックのように普段の生活に
自然と取り入れられる方法や、
子どもと一緒に楽しく学べる体験を通じて、
防災を「特別なこと」から「当たり前のこと」
へと変えていきましょう。
子どもの力を信じる
子どもたちは、
大人が思っている以上に多くのことを吸収し、
理解する力を持っています。
在宅避難の疑似体験を通じて、
子どもたちは「自分の命は自分で守る」という
意識を芽生えさせ、災害時にも冷静に行動
できる力を身につけていくでしょう。
一歩踏み出す勇気が家族を守る
「備えあれば憂いなし」ということわざが
あるように、事前の準備が災害時の被害を
最小限に抑える鍵となります。
本格的な訓練は難しくても、
ゴールデンウィークの1日を使った簡易版の
体験から始めてみましょう。
その一歩が、いざというときの家族の命を
守ることにつながります。
今年のゴールデンウィークは、
家族で楽しみながら防災力をアップさせる
特別な時間にしてみませんか?
自宅での避難訓練を通じて、
子どもたちと一緒に「生きる力」を育む
貴重な機会にしましょう。
SOIAEAREBAでは、
これからも皆さんの「備え」を
サポートする情報を発信していきます。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。