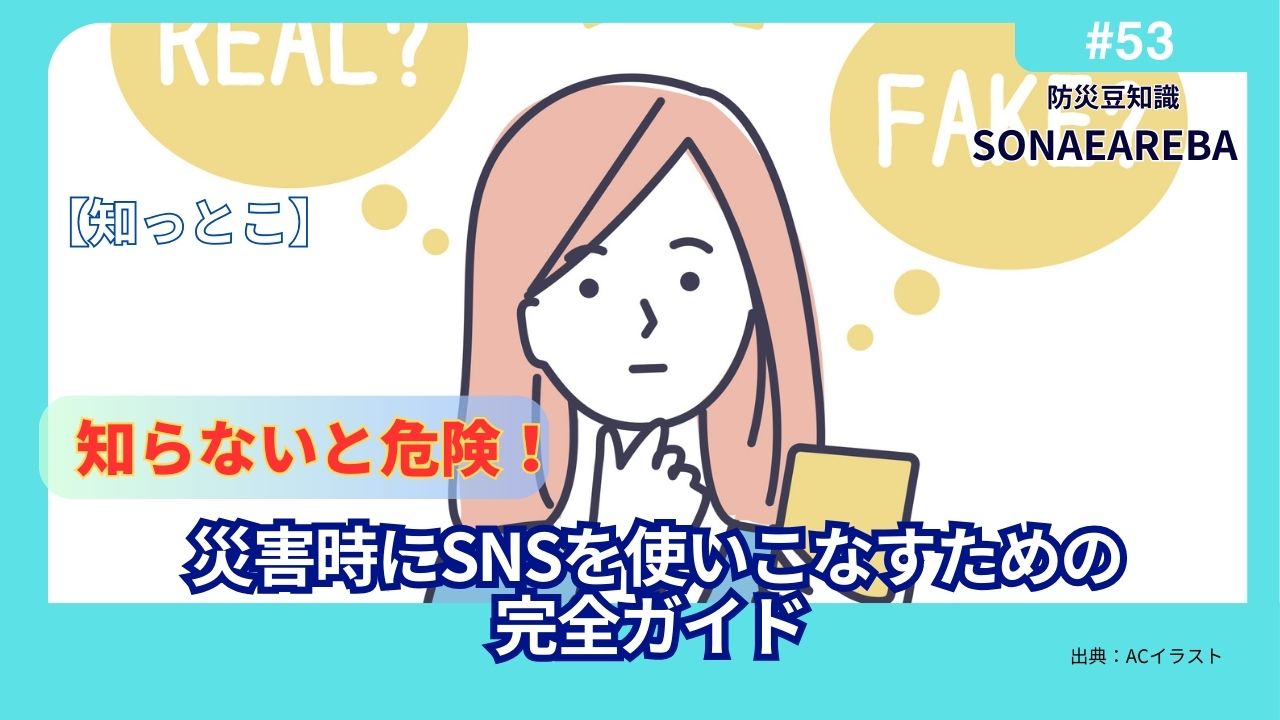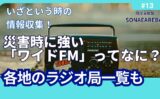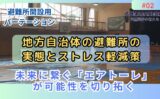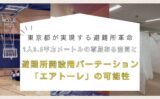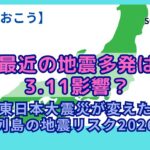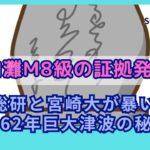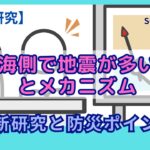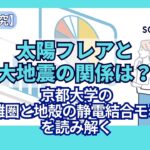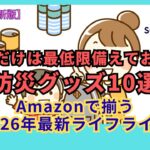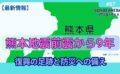この記事は広告を使用しています
SNSを活用した災害時の情報共有と課題:効果的な活用法と注意点
こんにちは!SONAEAREBAです。
災害時におけるSNSの役割は
年々大きくなっています。
情報の迅速な共有手段として
注目される一方で、
デマや偽情報の拡散といった課題も
浮き彫りになっています。
本記事では、
災害時のSNS活用における現状とメリット、
そして直面する課題と対策について
詳しく解説します。
災害時におけるSNSの価値と進化
災害が発生すると、
私たちはまず正確な情報を求めます。
従来は電話やテレビ、
ラジオが主な情報源でしたが、
現在ではSNSが重要な情報プラットフォーム
として機能しています。
東日本大震災以降、
SNSの災害時における活用は急速に広がり、
情報収集や共有のための強力なツール
となりました。
特に注目すべきは、
SNSが持つ迅速性と拡散力です。
災害発生直後、
公的機関からの情報発信が整う前に、
SNSでは現場からのリアルタイム情報が
共有されることがあります。
これにより、被災状況や必要な支援などの
情報がいち早く広まる可能性があります。
2016年の熊本地震の際には、
SNSの利用率が急増し、救助や支援に
つながったケースもありました。
また、
自治体の防災担当者を対象とした調査では、
8割以上が災害時のSNS情報に
「有用性を感じる」と回答しています。
公的機関よりも早く情報が得られることや、
被災者の声を直接聞くことができるという点が
評価されているのです。
SNSが変える災害時のコミュニケーション
災害時におけるSNSの活用は、
単なる情報収集にとどまりません。
2019年の台風19号の際、
長野県はTwitterを救助要請の情報収集ツール
として活用し、写真や位置情報とともに
「#台風19号長野県被害」というハッシュタグ
を付加したツイートを呼びかけました。
これにより約50件の投稿情報を
実際の救助につなげることができたのです。
2020年7月の九州南部豪雨時にも、
大分県災害対策本部の情報収集班にSNS担当を
置き、救助要請や家族の安否確認のツイートに
電話連絡を求める返信をしたことで、
情報提供や安否確認につながりました。
このような取り組みは、SNSが災害対応の現場
に直接貢献できることを示しています。
さらに、技術の進化も見逃せません。
2020年8月には、
総務省主導の3年間の社会実験を経て、
埼玉県がAIのSNS分析システム
「高度自然言語処理プラットフォーム」
を導入しました。
このようなシステムにより、
膨大なSNS投稿から重要な情報を
効率的に抽出することが可能になっています。
参考リンク:
朝日新聞 2021年4月3日
災害時の情報収集にSNS活用の動き
災害時のSNS活用における具体的なメリット
SNSが災害時に持つ価値は多岐にわたります。
主なメリットを詳しく見ていきましょう。
情報収集の迅速性と広範性
災害発生時、
電話やFAXなどの従来の連絡手段では
同時多発する災害に対して情報伝達の遅れが
生じる恐れがあります。
一方、SNSを利用すれば迅速に情報を
伝達・共有することが期待できます。
自治体の調査では、
災害発生直後は関係省庁や消防・警察からの
情報だけでなく、SNSからも積極的に情報を
収集していることが明らかになっています。
公的機関からの連絡を待つだけでなく、
SNSを通じて現場の状況をリアルタイムで
把握することで、より効果的な災害対応が
可能になるのです。
「官公庁は調査に時間がかかり、
即発信できないから」
「被災者の今必要な声が、適時に聞こえる」
といった声からも、SNSの迅速性が
高く評価されていることがわかります。
現場からの情報発信と支援要請
大きな災害が発生すると、
自治体や消防が被害の全体像を
把握するまでに時間がかかります。
そのような状況下で、
現場の被災者から直接情報が発信される
ことの価値は計り知れません。
「誰がどこで助けを求めているかわかった
事例がある」
という声もあるように、救助が必要な場所や
状況をリアルタイムで把握できることは、
限られたリソースを効率的に配分する上で
非常に重要です。
特に位置情報を活用した投稿は、
救助活動において大きな価値を持ちます。
被災した際に自ら情報発信する場合は、
どこで起きていることなのか、
場所の情報を掲載することで
有効な情報になります。
家族間の安否確認と情報共有
災害時には、家族の安否確認が
最も気がかりです。
SNSは離れた場所にいる家族との
コミュニケーション手段として
大いに活用できます。
事前に家族間でSNSを共有しておくことで、
災害時にどんな状況にあるのかを互いに
把握することが可能になります。
また、自分の住んでいる地域だけでなく、
家族が住む地域の自治体公式アカウントを
登録しておくことで、
遠隔地の情報も収集できます。
これは「自助」の観点からも重要で、
自分自身や家族の安全を確保するための
情報収集手段として、
SNSの価値は今後さらに高まるでしょう。
災害時のSNS活用における課題
SNSの有用性が認められる一方で、
その活用には多くの課題も存在します。
自治体の調査では、
8割以上が災害発生後の情報収集において
課題を感じていると回答しています。
ここでは主な課題について
詳しく見ていきます。
偽情報・デマの拡散問題
災害時のSNS活用における最大の課題は、
デマや偽情報の拡散です。
2024年の能登半島地震では、
X(旧Twitter)上で「人工地震」
という言葉を含む投稿が約10万件、
「窃盗団」(が現地に出没)に
関する投稿が約200件、
「支援要請」(偽の寄付を募るもの)に
関する投稿が約350件も確認されました。
こうした偽情報は、
迅速な救命・救助活動や円滑な復旧・復興活動
を妨げるだけでなく、被災者に不安を与え、
貴重なリソースを無駄に消費させる
危険性があります。
「デマに惑わされてしまうことがある」
「フェイクニュースを確認に時間が
かかり速報性がなくなる」
といった声からも、
偽情報の問題が深刻であることがわかります。
参考リンク:
内閣府 防災情報のページ
災害時におけるインターネット上の偽・
誤情報について
情報の信頼性検証の難しさ
SNSでは誰でも情報発信ができるため、
情報の信頼性を検証することが難しいという
課題があります。
「発生直後の正確な状況がわからないため、
災害対応に活用しにくい」
「実際に現場に行くと情報が全く違った」
といった声があるように、
情報の正確性を担保することは
容易ではありません。
しかし、
「完全に正しいとは限らないが、
他ではつかめない情報もある」
という意見もあり、
情報の取捨選択が重要になっています。
情報過多による混乱
災害時にはSNS上に膨大な情報が流れ、
必要な情報を見つけることが困難になること
もあります。
「2016年~2020年の災害事例にみる
被災地内における災害時のSNSの利用実態」
の研究によると、
被災者の約30%がSNSから
「受信した情報に困った経験がある」
と回答しており、特に問題となったのは
事実ではない情報(デマを含む)、
不安を引き起こす情報、
そして情報量が多すぎて必要な情報の
判断が難しくなるケースでした。
また、災害関連のハッシュタグが
統一されていないことも、
情報過多の状況下で混乱を招く
要因となっています。
救助要請対応の課題
SNSを通じた救助要請を効果的に
処理するための体制づくりも課題です。
消防庁の検討会では、
SNSユーザーからの救助要請情報を
SNS事業者が集約・フィルタリングし、
消防庁を経由して都道府県庁や消防本部に
伝達するという流れが検討されています。
しかし、
このような体制を整備するためには、
情報の集約方法や伝達経路の確立、
各機関の役割分担など、
多くの課題を解決する必要があります。
効果的なSNS活用のための対策
これらの課題を踏まえ、
災害時のSNS活用をより効果的にするための
対策について考えていきましょう。
平時からの準備と公的アカウントの登録
災害時にSNSを効果的に活用するためには、
平時からの準備が重要です。
まず、
自分の住んでいる自治体の公式SNSアカウント
をフォローしておくことが基本となります。
家族が離れた地域に住んでいる場合は、
その自治体のアカウントもフォローして
おくと良いでしょう。
SNSを利用していない家族の代わりに情報収集
ができるようにしておくことが、
いざという時の備えになります。
また、災害関連のハッシュタグを
平時から統一的に整備しておくことで、
災害時の情報共有がスムーズになります。
情報リテラシーの向上
偽情報やデマに惑わされないためには、
情報リテラシーの向上が不可欠です。
悪質な情報を受け取らないためには、
国や自治体などの公的機関からの
情報かどうか、信頼できる発信元であるか
を確認することが重要です。
また、投稿内容の日時を確認し、
最新情報であるかどうかを落ち着いて
判断する習慣をつけましょう。
SNSの投稿を見て、拡散するべき情報か
どうかを慎重に見極めることも必要です。
個人的なツイート(意見や感想、
あいまいな個人的な伝聞内容など)や、
信頼性や妥当性が担保できない状況の
ツイートは自粛するという意識も大切です。
テクノロジーの活用
AIを活用した情報解析システムの導入も
有効な対策です。
X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSに
投稿された情報から、自然災害や火災、
事故などの緊急性の高い情報を抽出し、
「どこで何が起きているか」を
リアルタイムに確認できるシステムが
開発されています。
埼玉県が導入した
「高度自然言語処理プラットフォーム」
のように、AIによるSNS分析は
今後さらに発展していくでしょう。
プラットフォーム事業者の取り組み
SNSプラットフォーム事業者も、
災害時の偽情報対策に取り組んでいます。
たとえば、X(旧Twitter)では、
明らかな偽情報などの違反投稿を
削除するとともに、
災害時におけるSNSのデマ・誤情報について
注意喚起を行っています。
Metaは通報に対する投稿の削除対応を実施し、
Facebook上の「災害支援ハブ」による
情報共有を行っています。
Googleは、YouTubeにて
一定期間集中的にモニタリングする体制を
整備し、信頼できる情報を見つけやすくする
施策を実施しています。
一般ユーザーができる災害時のSNS活用法
最後に、
一般ユーザーが災害時にSNSを効果的に
活用するためのポイントをまとめます。
情報収集のポイント
- 公的機関のアカウントを活用する:
自治体や気象庁、消防などの
公的機関の公式アカウントから
情報を収集しましょう。 - 情報の信頼性を確認する:
投稿者が信頼できる情報源かどうか、
投稿日時は最新かどうか、
他の信頼できる情報源でも同様の情報が
出ているかを確認しましょう。 - 複数の情報源を参照する:
SNSだけでなく、テレビやラジオなど
複数の情報源を組み合わせて情報を
収集することで、より正確な状況把握が
可能になります。 - ハッシュタグを活用する:
災害に関連するハッシュタグを
検索することで、関連情報を
効率的に収集できます。
情報発信のポイント
- 正確な情報を発信する:
未確認の情報やデマを拡散しないよう、
正確な情報のみを発信しましょう。 - 位置情報を活用する:
被災状況や救助要請を投稿する際は、
位置情報を付けることで、
救助や支援が届きやすくなります。 - 必要な情報を簡潔に伝える:
混乱を避けるため、必要な情報を
簡潔に伝えることが重要です。
また、統一されたハッシュタグを
使用することで、
情報が整理されやすくなります。 - プライバシーに配慮する:
個人情報の取り扱いには十分注意し、
不必要な個人情報を公開しないように
しましょう。
今後の展望:より効果的なSNS活用に向けて
SNSの災害時活用は
今後もさらに進化していくと考えられます。
AIによる情報分析の精度向上や、
公的機関とSNSプラットフォームの連携強化、
一般ユーザーの情報リテラシー向上などが
進むことで、より効果的な活用が
可能になるでしょう。
2011年の東日本大震災以降、
SNSは災害時の情報共有手段として
急速に普及しました。
しかし、調査結果によれば、
災害時の主な情報収集手段は依然として
テレビ(70-80%)やラジオ(40-60%)が
中心であり、LINEやX(旧Twitter)などの
SNSツールはこれらに次ぐ約20-40%の割合
となっています。
また、SNSで情報発信をする被災者は
約20%にとどまり、主にLINEを通じて
行われているという結果もあります。
これらの数字は、災害時のSNS活用には
まだ伸びしろがあることを示しています。
今後は、公的機関によるSNS活用の
さらなる普及や、一般ユーザーの
SNSリテラシー向上、AIなどのテクノロジーを
活用した情報分析の高度化などが進むことで、
SNSが災害時のより強力な情報共有ツール
となることが期待されます。
まとめ:災害時のSNS活用の未来
SNSは災害時の情報共有において
非常に有用なツールです。
迅速な情報伝達、
現場からのリアルタイム情報発信、
家族間の安否確認など、
多くのメリットがあります。
一方で、偽情報・デマの拡散、
情報の信頼性検証の難しさ、
情報過多による混乱などの課題も存在します。
これらの課題を克服し、
SNSの利点を最大限に活かすためには、
平時からの準備、情報リテラシーの向上、
テクノロジーの活用などが重要です。
また、SNSプラットフォーム事業者の
取り組みも欠かせません。
「災害は忘れた頃にやってくる」
と言われます。
だからこそ、日頃から防災意識を高く持ち、
SNSを含めた情報収集・共有の手段を
確保しておくことが大切です。
情報が溢れる時代、
いざという時に正しい情報を
速やかに得ることができるように、
普段からSNSで防災情報を受け取ることや
発信することに慣れておくことも
重要な防災対策の一つと言えるでしょう。
SNSを災害時の強力な味方にするか、
混乱の原因にするかは、
私たち一人ひとりの使い方にかかっています。
正しい知識と意識を持って、
災害時にもSNSを効果的に活用できるよう、
日頃から準備しておきましょう。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。