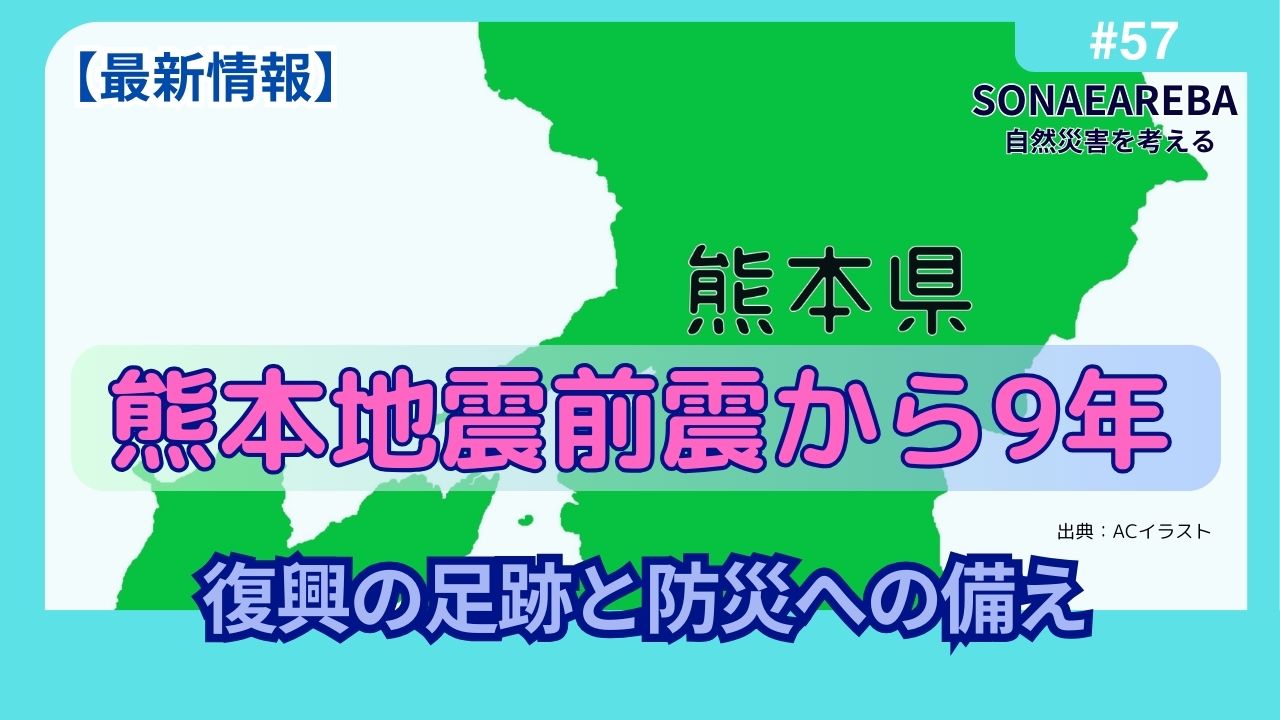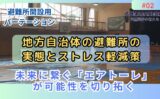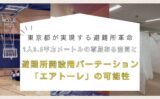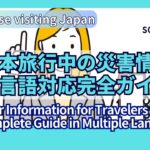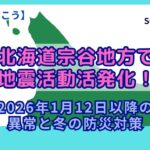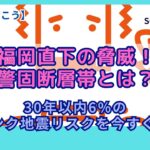この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
熊本地震発生から9年が経過した今、
被災地の復興状況と
今後の防災への取り組みに
ついて詳しくまとめました。
TSMCの進出による人口回復や
進む防災インフラ整備など、
復興の現状と「次」に備える動きを
徹底解説します。
熊本地震から9年を迎えて
2016年4月14日の夜に発生した前震、
そして48時間後の
4月16日未明に発生した本震。
観測史上初めて同じ地域で
最大震度7を2度記録した未曾有の災害から、
はや9年が経ちました。
あの日、多くの人が経験したことのない
恐怖と不安に包まれました。
今回は「熊本地震前震から9年」という
テーマで、復興の現状と防災への取り組みに
ついてお伝えしていきます。
熊本地震とはどのような災害だったのか
前震と本震が連続して発生した稀有な地震
熊本地震の特徴は、
前震と本震が連続して発生したことです。
2016年4月14日午後9時26分頃に
発生した前震(マグニチュード6.5)に続き、
約28時間後の4月16日午前1時25分頃に
本震(マグニチュード7.3)が
発生しました。
前震と本震のマグニチュードの差は
0.8に過ぎませんが、エネルギーでいうと
本震は前震の約16倍もの規模だったのです。
本震の規模は1995年の
阪神淡路大震災と同程度であり、
甚大な被害をもたらしました。
観測史上初の震度7連続記録
前震と本震はいずれも最大震度7を
記録しました。
同じ地域で震度7が連続して観測されたのは、
観測史上初めてのことでした。
震度7という揺れは、立っていることが
できず、這うことさえ困難になるほどの
激しい揺れです。
身体が飛ばされる危険さえある状況でした。
広範囲にわたる被害と避難者数
熊本地震では、
熊本県を中心に約20万7000棟の家屋が
被災し、熊本県と大分県で災害関連死を含む
278人の命が失われました。
最大で2万255世帯、
4万7800人が仮設住宅などに
避難する事態となりました。
9年間の復興の歩み
仮設住宅の終了と災害救助法適用終了
熊本県によると、「みなし仮設」を含む
仮設住宅は2023年3月に閉鎖されました。
また、今年(2025年)3月末には
県内全自治体で災害救助法の適用が
終了しました。
ただし、区画整理事業の影響で、
現在でも2世帯4人が仮住まいを続けており、
県の支援を受けています。
土地区画整理事業の進展
熊本県の復興事業は、
全家屋の98%に当たる1万584棟が
被害を受けた益城町の土地区画整理事業など
を除き、多くは完了しています。
同事業では、対象宅地482か所のうち
半数近くの造成が終わっており、
県は2027年度中の事業完了を目指しています。
人口の回復状況
復興が進む被災地では、
地震の影響で流出した人口が
戻ってきています。
地震後に約1500人減少した益城町は
今年3月末現在、
3万4175人と地震前の水準に回復しました。
地震で9人が亡くなった西原村も一時は
約300人減少しましたが、同月末現在で
地震前とほぼ同じ7043人となっています。
TSMCの進出による復興の加速
人口回復の背景には、
通勤圏にある菊陽町に進出した
台湾積体電路製造(TSMC)の効果も
大きいと言われています。
益城町では2023、2024年度、
それぞれ3社の半導体関連企業を
誘致しました。
国内外からの問い合わせも相次ぎ、
半導体関連工場や物流施設の誘致を目指して
新たに約9.4ヘクタールの産業用地の整備を
進めています。
益城町産業振興課は
「TSMCは復興の追い風になっている。
効果を町内に波及させたい」
と意気込んでいます。
防災インフラの整備状況
創造的復興のシンボルプロジェクト
県が創造的復興のシンボルに掲げる
益城町の県道熊本高森線の4車線化計画は、
3.8キロのうち1.6キロが開通済みです。
2025年度末までに残る2.2キロを
開通させる方針とのことです。
都市計画道路「益城東西線」の整備
災害に強いまちづくりの一環で益城町が
整備する都市計画道路「益城東西線」は、
2320メートルの一部244メートルが
2025年3月中旬に初めて開通しました。
県道熊本高森線の北側を並走する形で
建設しており、2031年度末の全線開通を
目指しています。
土地区画整理事業の進捗
町中心部の土地区画整理事業では
県が2025年3月、区画を新たに決める
「仮換地」の指定を終えました。
宅地のほか道路や公園といった公共用地を
合わせた計28.3ヘクタールを2027年度末まで
に整備する計画です。
災害関連死の実態
新たな災害関連死の認定
この1年間で新たに2人が災害関連死に
認定され、地震の犠牲者は計278人と
なりました。
熊本市が昨年7月に40歳代の男性、
今年3月に70歳代の女性をいずれも関連死
と認定しています。
両者とも遺族との連絡がつかない時期が
あったため認定が遅れたとのことです。
災害関連死への理解の重要性
災害関連死とは、
地震による直接的な被害ではなく、
避難生活での体調悪化やストレスなど
間接的な原因で亡くなることを指します。
熊本地震では、
関連死の数が直接死を上回るという
特徴がありました。
これは、避難生活の長期化や高齢者のケアの
重要性を浮き彫りにしました。
熊本地震から学んだ教訓
住民の声から見えた課題
熊本地震を経験した住民の声からは、
いくつかの重要な教訓が得られています。
熊本大学の学生へのインタビューによると、
以下のような点が挙げられました:
- 携帯電話の充電問題:
「初めに困ったことは携帯の充電です。
連絡手段や情報源は携帯しかありませんでした」 - 連絡の優先順位:
「限られた充電の中では全員に連絡を
返すことは難しい状態にありました」 - 生活環境の激変:
「家周辺の建物が崩れていたり、
通れない道があったり、以前とは違った
環境になっていることに驚きと恐怖を
感じました」 - 一人での避難生活の困難:
「地元が遠く、帰省できず1人で家に
居ることが出来なかった私は大学の体育館
に約1カ月間避難して過ごしていました」
体験者の教訓から学ぶ防災の心構え
体験者からは、
次のような防災の心構えが提案されています:
- 情報源の確保:
「情報をどこから得るのか
事前に考えておくことや、
誰にどのような連絡をすべきなのかを
考えておくべき」 - 最低限の備え:
「何かあった際に必要最小限のものを
リュックに入れておくだけでも違います」 - 日用品の準備:
「コンタクトなど普段の生活で必要なもの
は必ず入れています」 - ポータブル充電器の重要性:
「ポータブルの充電器は
必ず入れるようにしています」 - 行動計画の検討:
「今自分が災害に遭ったらどのような行動
をするのか考えてみることも、
防災に繋がる1歩」
前震と本震のメカニズム
断層帯の活動
熊本地震では、
4月14日の前震は
日奈久断層帯の北部で発生し、
4月16日の本震は
布田川断層帯で発生したことが
明らかになっています。
東京大学地震研究所の研究によると、
前震が発生した後、時間がたつにつれて
地震の発生域がじわじわと拡大していく
様子が観測されました。
「前震の後、地震活動は北東方向、
つまり日奈久断層の走向方向に拡大する
とともに、断層の浅い方向と深い方向にも
拡大していきました」
前震域の拡大が本震を示唆
この前震域の拡大が本震の発生を予測する
ヒントになる可能性があります。
研究者によれば、
「地震の予知はできなくても、
発生する確率が普段に比べて相対的に
高いという評価ができれば、それだけでも
被害の軽減につながることが期待される」
とのことです。
「次」に備える取り組み
大規模災害を想定した訓練
熊本県は今後の大規模災害に備えた
訓練を重ねています。
2024年11月には
南海トラフ巨大地震発生時の
広域応援訓練を実施しました。
政府は宮崎や大分で甚大な被害が出た場合、
熊本市西区の熊本地方合同庁舎に
九州地方の災害現地対策本部を置く計画が
あり、訓練では情報収集や物資輸送など
広域防災拠点としての役割を確認しました。
半島・島しょ部の孤立を想定した訓練
2024年12月には天草・水俣地域の
孤立を想定した実動訓練も行われました。
自治体職員や自衛隊など30団体約700人が
参加する大規模な訓練で、
海上自衛隊のホーバークラフト型揚陸艇も
加わり、陸路が断絶した場合の物資輸送など
を試しました。
2025年度も内容を変えた訓練を
実施する予定とのことです。
次の大地震への警鐘
九州大学が中心となって進めてきた
活断層の調査結果によると、
熊本地震のような大地震が熊本県内で
再び発生する可能性が指摘されています。
布田川断層帯の布田川区間は熊本地震により
「ひずみ」を完全に解消しましたが、
日奈久断層帯で動いた高野-白旗区間は
「ひずみ」がたまった状態のままであり、
次の大地震はいつ起きてもおかしくないとの
見解が示されています。
九州大学の清水洋教授は
「布田川区間で予想される次の大地震は
2千年ほど先ですが、日奈久断層帯では
いつ起きてもおかしくありません」
と指摘しています。
熊本地震の教訓を活かした防災準備
個人でできる防災対策
熊本地震の体験者の声を参考に、
個人でできる防災対策をまとめました:
- 非常用持ち出し袋の準備:
最低3日分の水・食料、懐中電灯、
携帯ラジオ、予備の電池、救急セット、
常備薬、現金などを
準備しておきましょう。 - ポータブル充電器の常備:
災害時の情報源・連絡手段となる
スマートフォンの電源確保は
最優先事項です。 - 避難場所と連絡方法の確認:
家族間で災害時の集合場所や連絡方法を
事前に決めておきましょう。 - 家具の固定:
家具の転倒防止対策を行い、
寝室や子供部屋には大型家具を
置かないようにしましょう。 - 日用品のストック:
トイレットペーパー、生理用品、
コンタクトレンズ用品など、
普段使用している生活必需品を多めに
ストックしておくことも重要です。
正確な情報収集の重要性
熊本地震では、
SNSなどでデマ情報が拡散する事態も
発生しました。
「熊本動物園からライオンが逃げ出した」
という偽情報が写真付きで拡散されるなど、
混乱に拍車をかける状況が見られました。
一方で、熊本地震ではデマ情報は
発生直後に広まったものの、
収束も早かったという特徴があります。
ネットユーザー間でデマを否定する動きが
自発的に起きたことが要因と
考えられています。
災害時には、
公的機関や信頼できるメディアの情報を
優先的に確認し、不確かな情報に
惑わされないよう注意が必要です。
熊本地震が私たちに残したもの
コミュニティの力
熊本地震の体験者の声からは、
災害時のコミュニティの力の重要性も
浮かび上がります。
「体育館ではたくさんの人の助け合いが
ありました。飲食物の配給や夜間警備、
小さな子と遊ぶことなどで学生が手伝いを
行っている様子を見たり、
自分も実際に行ったりすることで
自分にしか余裕がなかった気持ちにも
変化がありました」
という証言は、共助の精神の大切さを
示しています。
防災意識の変化
熊本地震以降、熊本県内では
防災意識が高まり、各家庭での備蓄や
避難場所の確認、地域での防災訓練への参加
など、具体的な防災行動につながっています。
Yahoo!ニュースの読者投票では、
「十分な備えができている」と
「ある程度の備えができている」を
合わせて38.5%である一方、
「あまり備えていない」
「まったく備えていない」を
合わせると61.4%にも上り、
さらなる意識啓発の
必要性が浮き彫りになっています。
今後の防災に向けて
科学的知見を活かした対策
熊本地震の経験と科学的知見を活かし、
今後も継続的な防災・減災対策が
求められます。
特に、日奈久断層帯の「ひずみ」状態を
考慮すると、次の大地震に備えた対策の
一層の強化が必要です。
地域コミュニティの防災力強化
災害時に最も頼りになるのは、
近隣の地域コミュニティです。
日頃からの交流や防災訓練を通じて、
コミュニティの防災力を高めていくことが
重要です。
防災教育の充実
若い世代への防災教育も重要な課題です。
学校教育の中に防災学習を積極的に取り入れ、
災害の経験や教訓を次世代に伝えていくことが
必要です。
まとめ:熊本地震から9年、そして未来へ
熊本地震から9年、
被災地の復興は着実に進み、
新たな街づくりや産業の誘致など、
創造的復興の取り組みが進められています。
TSMCの進出も追い風となり、
被災地の人口は地震前の水準に回復しつつ
あります。
一方で、日奈久断層帯の「ひずみ」状態や
南海トラフ巨大地震の可能性など、
新たな災害リスクも指摘されています。
熊本地震の教訓を活かし、
個人、地域、行政それぞれのレベルで
防災・減災に取り組んでいくことが重要です。
「災害は忘れた頃にやってくる」
と言われますが、
忘れないことが防災の第一歩です。
熊本地震の記憶を風化させることなく、
次の災害に備えるため、
日頃からの準備と心構えを
大切にしていきたいと思います。
私たちSONAEAREBAは、
これからも防災・減災に関する
情報発信を続け、皆様の「備え」を
サポートしていきます。
※本記事は2025年4月14日時点での
情報に基づいて作成しています。
最新の情報については各公的機関の
発表をご確認ください。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。