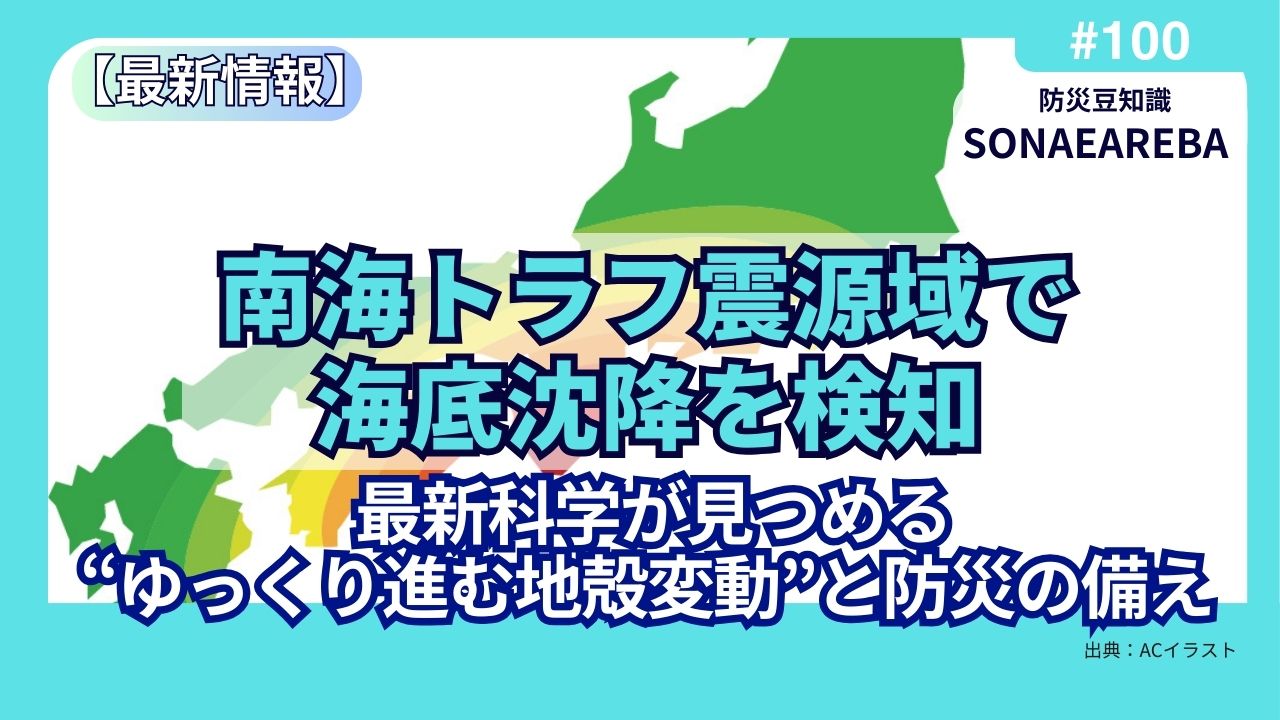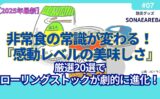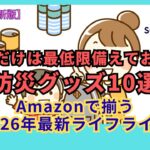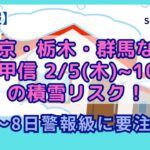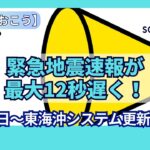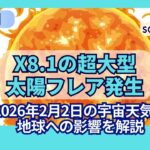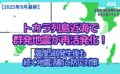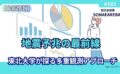この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
最新ニュースを防災視点で噛み砕くと、
紀伊半島沖の南海トラフ震源域で
「年間約1.5〜2.5センチ」
の微小な海底沈降が確認され、
長期的な地殻変動の把握に役立つ
成果が示されました。
これは直ちに巨大地震の前兆を
意味するものではない一方、
観測網の高度化で“ゆっくり進む変化”を
より正確に掴める段階に入ったという
前向きなニュースです。
何が起きたのか
JAMSTECなどが、
南海トラフ巨大地震の震源域に当たる
紀伊半島沖の2地点で海底のわずかな
沈降を検出し、年1.5〜2.5センチの速度
と評価しました。
観測には地震・津波監視システムDONET
の水圧計が使われ、津波の即時把握だけ
でなく、プレートの沈み込みに伴う
陸側の沈降も測る活用が進んでいます。
成果は米国の科学誌に18日付で発表され、
長期観測による予測精度向上への
期待が述べられています。
参考リンク:
JAMSTEC | 海洋研究開発機構 |
ジャムステック
これは前兆なのか
今回の沈降は、
プレートの沈み込みで生じる
“長期的・背景的な変動”として
捉えられており、巨大地震の直前兆とは
断定されていません。
気象庁の周辺地域でも、
長期的沈降傾向は以前から確認され、
トレンド自体に大きな変化はない
とされます。
重要なのは、こうした小さな動きを
継続的に測り、将来のリスク評価に
役立てる観測体制の強化が
進んでいる点です。
なぜ重要か(防災の意味)
微小沈降の検出は、
地殻の蓄積や緩みの分布を高解像度で
把握するうえで基礎データになります。
長期のトレンドが見えると、
想定震源域ごとの揺れ・津波の事前評価
や訓練シナリオの改善に資します。
観測網(DONETや整備が進むN-netなど)
が拡充されるほど、即時警報と長期評価
の両輪が強化されます。
今できる実務的な備え
- 家の耐震チェックと固定:
家具の転倒防止と水回り・窓の補強は
コスパが高い一次対策です。 - 在宅備蓄の見直し:
水・食料は最低3日、可能なら7日分を
目安にローリングストックを
設定します。 - 津波避難の確認:
沿岸部は最寄りの高台・避難ビルと
最短ルートを紙でも控え、
夜間・豪雨時想定で複線化します。 - 情報源の整備:
緊急速報・津波警報の受信設定と、
地域防災メールや自治体公式SNSの
フォローを済ませます。
観測技術の進化
DONETの水圧計は津波の即時検知で
知られますが、年数センチ規模の誤差と
どう向き合うかが課題でした。
今回の成果は、長期データ処理や補正の
改良で“微小な沈降”の抽出に成功した点
が注目で、将来のモニタリング高度化に
弾みがつきます。
加えて、国の観測網整備の進展は
面的な監視力を底上げします。
まとめ(行動につなげる)
微小沈降の検出は
「直ちに危険」ではなく、
「見えない変化を見える化する力が
上がった」という朗報です。
最新の科学と観測網の強化を追い風に、
耐震・備蓄・避難・情報の4点を
今日のToDoに落とし込み、季節替わりの
タイミングで更新しましょう。