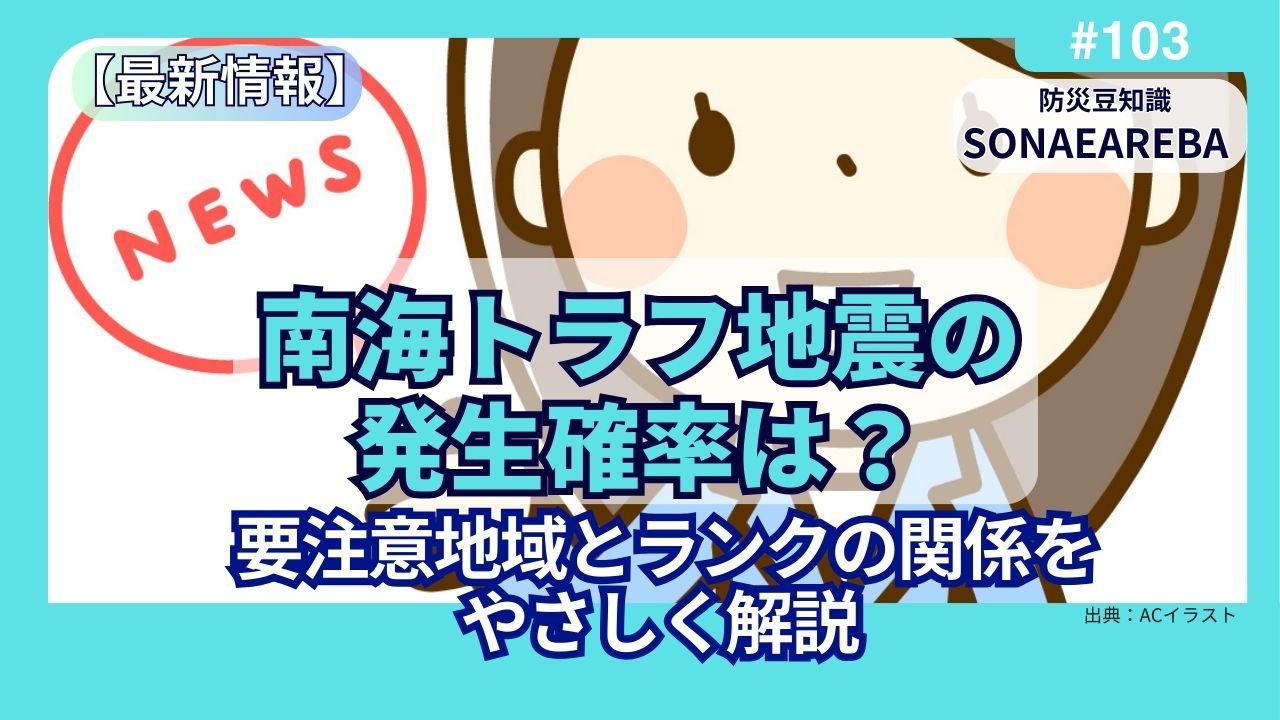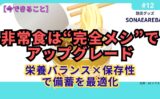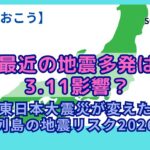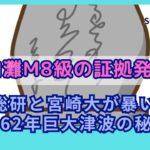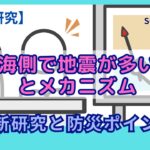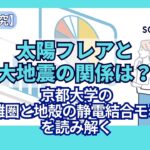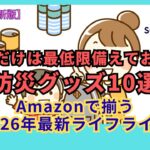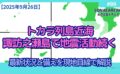この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
政府の地震調査委員会は、
南海トラフ巨大地震の発生確率について、
新たな研究などを踏まえ
「60%から90%程度以上」と
「20%から50%」
の2つの確率を新たに算出しました。
最新の公的情報をもとに
「南海トラフと並ぶ要注意地域」
「ランクと発生確率の関係」を
整理してわかりやすく記事にします。
結論
南海トラフ巨大地震の30年発生確率は
「60〜90%程度以上」に見直され、
依然として極めて高い水準です。
一方で、活断層のSランク(3%以上)
地域や「震度6弱以上の確率」が
高い都市圏も要注意で、確率の見方と
ランクの意味を正しく理解することが
防災行動の第一歩だと考えています。
この記事の概要
この記事では、
南海トラフの最新評価を起点に、
「ランク(S/Aなど)」と「30年確率」
の関係、そして全国の揺れリスクを示す
地震動予測地図の読み方を、
皆様の視点でわかりやすく解説します。
参考リンク:
NHK WEBホームページ
南海トラフ巨大地震
30年以内発生確率 2つの確率を新たに算出
南海トラフの最新評価
9月の見直しで、政府の地震調査委員会は
南海トラフ巨大地震の30年確率を
「60〜90%程度以上」と公表しました
(計算手法とデータの不確実性を考慮し
幅を明示)。
年初の「80%程度」からの表現変更で、
モデルを2本提示(室津港データの見直し
を含む)したのがポイントです。
「要注意地域」はどこか
要注意は南海トラフ沿いの
太平洋側だけではありません。
全国の「30年で震度6弱以上の確率」
を見ると、都市部や沿岸域で高い地点が
散在し、居住地ごとの差が可視化されます
(J-SHISや報道解説が便利)。
確率が低い地域でも強い揺れは
起こりうるため、
地図は“目安”として活用し、構造対策や
備蓄に落とし込むのが実際的です。
参考リンク:
防災科学技術研究所 ホームページ
今後30年間に震度6弱以上の揺れに
見舞われる確率
ランクと確率の関係
活断層の長期評価では、
今後30年の発生確率に応じて
ランクが付与されます。
Sランクは3%以上、
Aランクは0.1〜3%未満、
Zランクは0.1%未満、
Xランクは評価困難です
(公的評価に準拠)。
例えばSランクの主要断層帯が
各地に存在し、地域計画や耐震投資の
優先度判断に使えます。
「確率」と「被害想定」を分けて考える
確率が高い=必ず近く起きる、
ではありませんし、
確率が相対的に低い地域でも
大きな被害は起こり得ます。
同じ30年確率でも、
人口密度・地盤・建物ストックによって
リスクの意味が変わるため、
「発生確率」と「揺れやすさ(地震動)」
「被害規模」を別レイヤーで
評価するのが現実的です。
参考リンク:
地震調査研究推進本部事務局
確率的地震動予測地図の見方
南海トラフと並ぶ注目エリア
- 首都圏直下型の揺れリスクは
地震動予測地図で常に注視対象です
(広域に震度6弱以上の確率ゾーン)。 - 太平洋側の各県は、
海溝型と内陸活断層の双方に目配りが
必要で、自治体想定と一致しない点
もあり得ます(確率の幅に留意)。 - 北海道〜東北太平洋岸でも、
確率地図上の“色の濃い”帯が局所的に
現れるため、ピンポイントに住所単位
で閲覧することを推奨します。
参考リンク:
防災科学技術研究所
J-SHIS 地震ハザードステーション
地震動予測地図の“読み方”のコツ
- 30年・震度6弱以上・地点ごとの確率
という前提を押さえ、ゼロは安全を
意味しないと理解します。 - 近隣自治体との境界で色が変わること
があるため、番地レベルで確認し、
通勤・通学先も含めた行動圏で
評価します。 - 地図は「危険度」の俯瞰であり、個別
建物の耐震性は別途診断が必要です。
実務としての行動に落とす
- 住居と勤務先の30年確率をJ-SHISで
確認し、家具固定・ガラス飛散防止・
非常用照明を優先実装します。 - 木造は耐震等級と接合部の補強計画、
マンションは共用部の耐震改修履歴
や非常電源の確認が有効です。 - 南海トラフ想定域は津波避難経路と
徒歩避難時間の二重確認
(車に依存しない)を基本とします。
参考リンク:
地震調査研究推進本部事務局
全国地震動予測地図2020年版
防災科学技術研究所
J-SHIS 地震ハザードステーション
SONAEAREBAが伝えたいこと
南海トラフの「60〜90%程度以上」は、
危機感を煽るためではなく
行動の優先順位を決めるための指標です。
確率・ランク・地震動の三点を
地図で可視化し、今日できる一手から
始めることが、最も合理的な備えだと
確信しています。