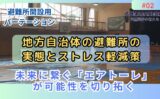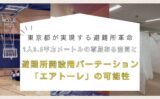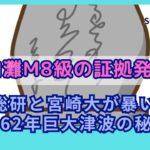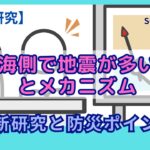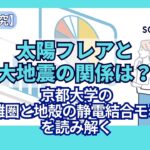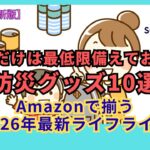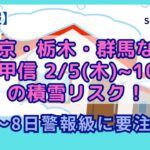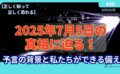本記事はAmazonアソシエイトとして、
商品を紹介して収益を得る可能性があります。
こんにちは!SONAEAREBAです。
今回は2025年3月31日に国が公表した
「南海トラフ巨大地震の新たな被害想定」
について、最新情報をもとにやさしく解説
していきます。
約10年ぶりに更新された被害想定には、
私たちが知っておくべき重要な情報が
含まれています。
地震大国日本に住む私たちにとって、
この情報は「我が事」として
捉えるべきものです。
南海トラフ巨大地震とは?発生確率80%の巨大災害
南海トラフとは、
静岡県の駿河湾から九州東方沖まで続く
深い海底の溝のことです。

ここでは日本列島側のプレートの下に、
フィリピン海プレートが沈み込んでおり、
この境界でマグニチュード8~9クラスの
巨大地震が100~150年周期で発生しています。
注目すべきは、
2025年1月に政府の地震調査委員会が
南海トラフ地震の30年以内の発生確率を
「70%~80%」から「80%程度」へ
引き上げたことです。
発生確率の推移を見ると、
2013年は60~70%、2014年は70%程度、
2018年は70~80%と、年々上昇しています。
これは時間の経過に伴い発生確率が
高まっていることを意味し、
今すぐ南海トラフ地震が起きても
不思議ではない状況になってきています。
【速報】2025年3月31日公表の新たな被害想定
国の有識者会議は3月31日、
南海トラフ巨大地震について
約10年ぶりとなる新たな被害想定を
公表しました。
マグニチュード9クラスの地震が
発生した場合、最悪のシナリオでは
以下のような被害が予測されています:
- 直接死者数:最大29万8000人
- 全壊・焼失建物:235万棟
- 経済的損失:292兆円(国家予算の2.5倍)
- 災害関連死:2万6000人~5万2000人
この被害想定は、
東海沖から九州沖を震源域とする
「南海トラフ巨大地震」について、
最悪の場合を想定したものです。
全国の死者のうち約7割は
津波による被害とされています。
前回(2012年)の想定との比較:何が変わった?
2012年に公表された
前回の被害想定と比較すると、
以下のような変化が見られます:
- 直接死者数:
32万3000人 → 29万8000人
(約2万5000人減少) - 全壊・焼失建物:
238万6000人 → 235万棟
(約3万6000棟減少) - 経済的損失:
220兆円 → 292兆円
(72兆円増加)
死者数と建物被害が減少した主な理由は、
この13年間で建物の耐震化が
一定程度進んだためです。
一方、経済的損失が増加したのは、
物価の上昇を反映したためとされています。
特筆すべきは、
今回初めて「災害関連死」の人数が
盛り込まれたことです。
災害関連死とは、
地震や津波の直接的な被害ではなく、
避難生活のストレスや医療機関の機能停止など
による間接的な死亡を指します。
地域別に見る被害想定:あなたの住む地域は?
新たな被害想定では、地域別の被害についても
詳しく示されています。
静岡県から宮崎県の沿岸部
静岡県から宮崎県にかけての
太平洋沿岸部では、一部地域で震度7、
周辺の広い地域で震度6強から6弱の強い揺れ
が想定されています。
さらに、関東地方から九州地方にかけての
太平洋沿岸の広い地域には10mを超える
大津波の襲来が予測されています。
愛知県
愛知県では最大で1万9000人が
犠牲になるとされています。
国の作業部会の主査を務めた
名古屋大学の福和伸夫名誉教授は会見で
「南海トラフ地震の被害を減らさない限り、
国の将来が非常に危ぶまれる」
と強い危機感を示しています。
長崎県・山口県
長崎県では最大500人の死者が出ると
推計されています。
また、山口県でも最大約500人の死者が
想定され、そのうち約400人(8割)は
津波によるものとされています。
山口県内では震度6弱から5弱の揺れが予測され
ており、瀬戸内海沿岸には最大4~5メートルの
津波が押し寄せる可能性があります。
高精度データによる新たな課題の発見
今回の被害想定では、
地形や地盤のデータが高精度化されたことで、
被害を受ける地域がより広範囲に及ぶことが
判明しました。
福島県から沖縄県に及ぶ深さ30センチ以上
の浸水域が拡大し、津波の浸水面積は
全国で3割程度増加しています。
例えば長崎県内では、
2メートル以上の浸水面積が
最大250ヘクタールに拡大し、
死者数も前回の最大80人から最大500人に、
負傷者は200人に増加すると
推計されています。
経済的損失292兆円の衝撃
今回の被害想定で特に注目すべきは、
経済的損失が292兆円に達すると
予測されていることです。
これは前回の予測(2013年)よりも
72兆円増加し、国家予算の2.5倍に相当する
巨額です。
この経済的損失は、
建物や道路などの直接的な被害だけでなく、
サプライチェーンの寸断による
生産活動の停止、観光業への打撃など、
間接的な損失も含まれています。
こうした経済的影響は日本全体に及び、
復興には長い年月と莫大な資金が
必要になるでしょう。
政府の対策と目標達成状況
政府は2023年度末までに死者を80%、
全壊・焼失建物を50%減少させるという
目標を掲げていましたが、
実際の減少幅はどちらも1割にも満たず、
目標達成には程遠い状況です。
坂井防災担当大臣は、
今回の被害想定を受けて夏ごろをめどに
政府の対策推進基本計画を見直すと発表しました。
専門家会議は
「従来の政府中心の対策だけでは限界がある」
と指摘し、国民一人ひとりが住宅の耐震化や
迅速な避難行動を取るよう呼びかけています。
個人でできる備え:今からやるべきこと
南海トラフ巨大地震に備えて、
私たち個人ができることは多くあります。
1. 住宅の耐震化
古い建物に住んでいる場合は、
耐震診断や耐震補強を検討しましょう。
多くの自治体では
耐震診断・改修の補助金制度を設けています。
2. 家具の固定
地震の揺れで家具が倒れると、
けがをしたり避難路が塞がれたりする
恐れがあります。
家具は壁に固定し、重いものは下に、
軽いものは上に配置するなどの
工夫をしましょう。
3. 非常用持ち出し袋の準備
水、食料、医薬品、懐中電灯、ラジオ、
携帯電話の充電器など、
最低3日分の備蓄を用意しておきましょう。
4. 避難場所・避難経路の確認
家族で避難場所や避難経路を事前に確認し、
実際に歩いてみることが大切です。
特に津波の危険がある地域では、
高台への避難経路を複数確保しておきましょう。
5. 家族との連絡方法の確認
災害時は電話が繋がりにくくなります。
災害用伝言ダイヤル(171)や
災害用伝言板サービスの使い方を
確認しておきましょう。
参考リンク:
NTT災害用伝言ダイヤル(171)
災害用伝言版サービス
NTTドコモ・au・ソフトバンク
楽天モバイル
まとめ:南海トラフ巨大地震に備えて
今回の被害想定は、南海トラフ巨大地震が
いかに甚大な被害をもたらす可能性があるかを
改めて示しています。
30年以内の発生確率が
80%に引き上げられたことも含め、
今すぐ対策を始める必要があります。
名古屋大学の福和伸夫名誉教授が
「南海トラフ地震の被害を減らさない限り、
この国の将来が非常に危ぶまれる。
そろそろ本気になって、対策を進めてほしい」
と訴えているように、
政府や自治体の対策に頼るだけでなく、
私たち一人ひとりが
「自分の命は自分で守る」という意識を持ち、
具体的な備えを進めていくことが重要です。
地震大国日本に住む私たちにとって、
防災・減災の取り組みは日常生活の一部として
組み込まれるべきものです。
最新の被害想定を正しく理解し、
家族や地域で備えを進めていきましょう。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
皆さんの防災意識が少しでも高まり、
具体的な行動につながれば幸いです。
次回もSONAEAREBAでお会いしましょう!