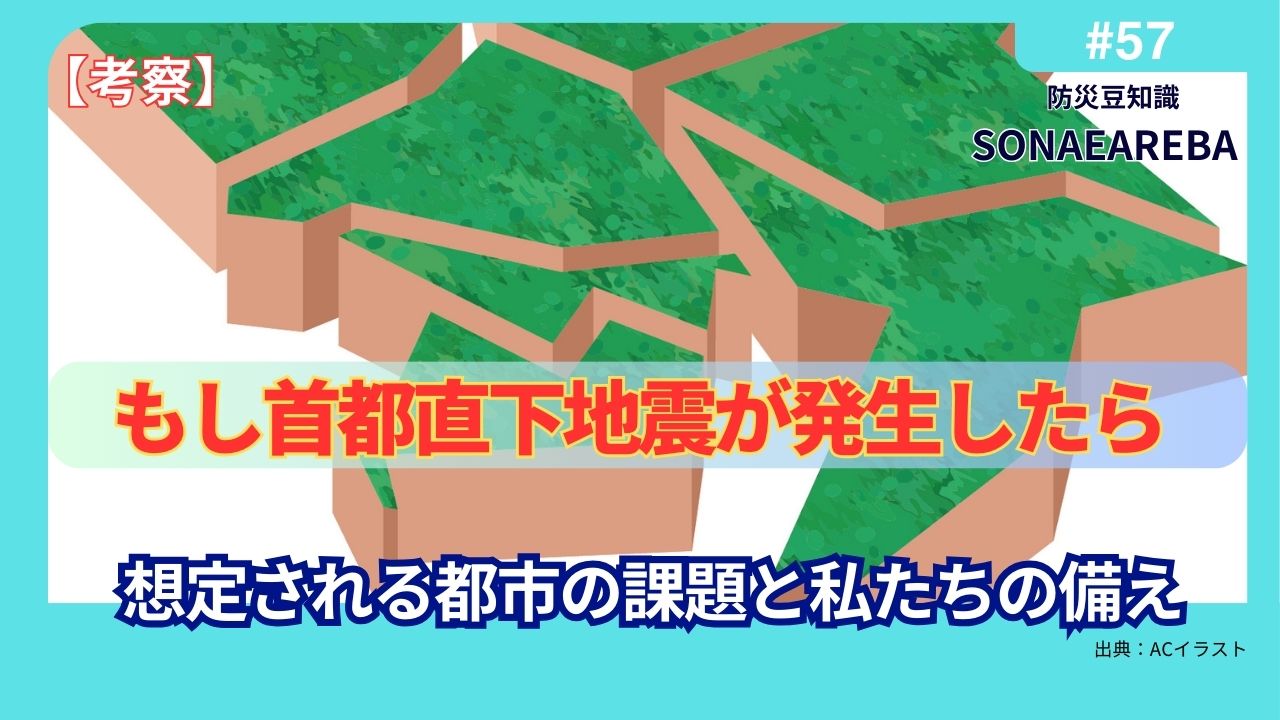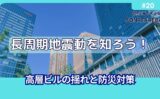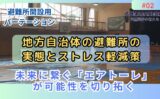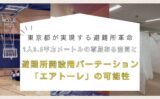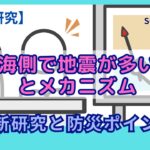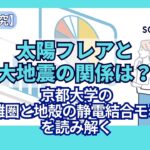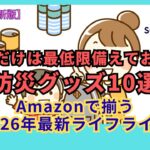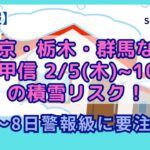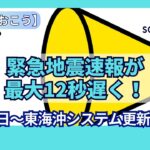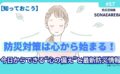この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
首都直下地震が発生した場合、
最悪のシナリオでは死者約2万3,000人、
経済被害約95兆円という
甚大な被害が想定されています。
しかし、適切な対策を講じることで
被害を大幅に軽減できる可能性もあります。
本記事では、
首都直下地震の被害想定や都市が直面する
課題、そして私たちができる備えについて
詳しく解説します。
首都直下地震とは?その特徴と発生確率
私たちが住む日本は世界有数の地震大国です。
特に首都圏に住む方々にとって
「首都直下地震」という言葉は
他人事ではないはずです。
しかし、
具体的にどのような被害が想定されている
のか、詳しく知っている方は意外と少ない
のではないでしょうか?
首都直下地震の定義
首都直下地震とは、
東京都を含む関東地方を震源として起こる
地震のことです。
現在、特に懸念されているのは
マグニチュード7クラスの巨大地震です。
国の中枢機関が集中する首都圏で
発生するため、日本全体に甚大な影響を
及ぼすと予想されています。
発生確率と根拠
気になるのは「本当に起きるのか?」
という点ですよね。
専門家によると、
首都直下地震は今後30年以内に70%の確率
で発生すると想定されています。
この数字の根拠には、
過去に南関東などで発生したとされる
地震の記録があります。
最新の被害想定から見る首都直下地震の脅威
人的被害の想定
国の中央防災会議の想定によると、
最悪の場合、
首都直下地震による死者数はおよそ2万3,000人
に達するとされています(2013年公表)。
特に注目すべきは、
この死者のうち約7割(1万6,000人)が
火災によるものと想定されている点です。
一方で、
東京都が2022年に発表した
最新の被害想定では、首都圏の建物の耐震化が
進んだことなどを反映し、
都心南部直下地震(M7.3)の場合の死者数は
およそ6,150人と予測されています。
これは10年前の想定より3割以上
少なくなった数字です。
参考リンク:
NHK WEB「首都直下地震」被害想定は?
備えや対策は?まとめて紹介
建物被害の規模
建物被害については、
中央防災会議の想定では最大で約61万棟が
全壊・焼失するとされています。
東京都の最新想定では、
都心南部直下地震の場合、
建物被害は約19万4,400棟
(揺れによる全壊約8万2,200棟、
火災による焼失約11万2,200棟)
と予測されています。
これらの被害は
江東区や江戸川区など11区の一部で
震度7の揺れが観測され、
23区のおよそ6割で震度6強以上になる
という想定に基づいています。
注目すべきは、被害の分布です。
建物・人的被害の約6割が都内(特に区部)
に集中する一方、残りの約4割は
埼玉県、千葉県、神奈川県などの周辺県で
発生すると予想されています。
このように、首都直下地震は東京だけでなく
首都圏全体に広域的な被害をもたらすのです。
経済被害の規模
首都直下地震による経済被害は、国の想定で
およそ95兆円にのぼるとされています。
これは日本のGDPの約2割に相当する金額で
す。首都圏に経済機能が集中している日本で
は、この地域の被災が全国、さらには世界経済
にまで波及効果をもたらす可能性があります。
首都圏特有の課題 – インフラとライフライン
電気・ガス・水道の被害想定
首都直下地震では、
インフラやライフラインへの甚大な被害
も予想されています。
国の想定によれば、
電力については発災直後に約5割の地域で
停電し、1週間以上不安定な状況が続くと
されています。
上下水道に関しては、都区部で約5割が断水、
約1割で下水道が使用できなくなるとの
想定です。
これらの機能が停止すると、
衛生状態の悪化や生活の質の著しい低下
を招き、「震災関連死」のリスクを
高める要因となります。
私が特に心配なのは、
ライフラインの復旧までの時間です。
阪神・淡路大震災や東日本大震災の経験から
も、都市部のインフラ復旧には想像以上の
時間がかかることがわかっています。
特に密集市街地での復旧作業は
困難を極めるでしょう。
交通網の麻痺と復旧見通し
交通インフラについては、
地下鉄は1週間、私鉄・在来線は1か月程度、
開通までに時間を要する可能性があります。
道路についても深刻な交通麻痺が予想され、
救援活動や物資輸送にも大きな支障を
きたすでしょう。
特に首都高速道路は高架構造が多く、
被災した場合の復旧には
相当な時間がかかります。
また、橋梁や高架道路の損傷は、
迂回路がない場合に地域の孤立化を
招く恐れもあります。
都市型災害としての特殊な問題
帰宅困難者問題
東京都の最新の被害想定では、
首都直下地震が発生した場合、
最大でおよそ453万人の帰宅困難者が
発生すると予測されています。
この数は10年前の想定よりおよそ64万人
減少していますが、依然として非常に多くの
人々が影響を受けることに変わりありません。
帰宅困難者の問題は単に
「家に帰れない」というだけではなく、
大量の人々が一斉に帰宅しようとすることに
よる「群集雪崩」の危険性も
指摘されています。
群集雪崩とは、
大量の人々が密集した状態で移動する際に、
一部の人が転倒するとドミノ効果で
多くの人が倒れ、圧死などの
重大な事故につながる現象です。
記憶に新しいところでは、
2022年梨泰院事故です。韓国ソウル梨泰院
で、ハロウィンの混雑の中で群衆雪崩が
発生し、悲劇的な事故となりました。
参考リンク:
NHK 首都圏ナビ
首都直下地震 東京都が被害想定見直し
「災害シナリオ」詳しく
高層ビル・タワーマンションの問題
近年、首都圏ではタワーマンションなどの
高層建築物が増加していますが、
これらの建物は地震時に特有の問題を
抱えています。
エレベーターが停止した場合、
中・高層階の住民は地上との行き来が
困難になり、物資を受け取れなくなる
おそれがあります。
また、高層ビルでは「長周期地震動」
による影響も懸念されます。
長周期地震動は、
高層建築物を共振させて大きく揺らし、
内部の設備や家具の損壊、
人的被害を引き起こす恐れがあります。
大規模火災のリスク
首都直下地震で最も恐ろしいのは、
大規模な市街地火災の発生です。
先に述べたように、
想定される死者のうち7割は火災によるもの
とされています。
都市部には木造住宅が密集する地域が
まだ多く残っており、同時多発的な火災が
発生した場合、消防力の限界を超えて延焼が
拡大する恐れがあります。
特に「火災旋風」と呼ばれる現象は
甚大な被害をもたらす可能性があります。
火災旋風とは、大規模火災によって生じる
強い上昇気流が竜巻のような渦を形成し、
周囲の火災を急速に拡大させる現象です。
関東大震災では、この火災旋風によって
多くの犠牲者が出ました。
長期的な社会・経済への影響
避難生活の長期化と震災関連死
東京都の最新の被害想定では、
避難者数は最大でおよそ299万人にのぼると
予測されています。
これらの方々の避難生活は長期化する
可能性が高く、その過程で発生する
「震災関連死」も大きな問題となります。
震災関連死とは、
地震による直接的な被害ではなく、
避難生活の長期化などによる心身の疲労や
持病の悪化などで死亡するケースを指します。
東京都の「災害シナリオ」によれば、
地震直後には停電で人工呼吸器などが
停止することによる死亡、
数日後からは車中泊による
エコノミークラス症候群による死亡、
そして1か月以上経過後には慣れない環境での
心身の不調、悪化などが想定されています。
住宅問題と「住宅難民」
首都直下地震後の大きな課題の一つが
住宅問題です。
大量の建物が被災した場合、
代替住宅の確保が極めて困難になります。
都市部では空き地が少なく、
仮設住宅を大量に建設するスペースの確保も
容易ではありません。
また、賃貸住宅も一斉に需要が
高まることで確保が難しくなり、
「住宅難民」と呼ばれる状態に陥る人々が
多数発生する恐れがあります。
経済活動への長期的影響
首都直下地震は日本経済に
壊滅的な打撃を与える可能性があります。
経済の中枢機能が集中する首都圏の機能が
麻痺することで、全国的な経済活動の停滞、
さらには世界経済への悪影響も懸念されます。
専門家による座談会では、
地震後の経済状況について
「水の値段が5倍になって、闇市ができる」
といった厳しい予測も出されています。
また、日本の財政にも大きな負担がかかり、
復興費用の捻出のために増税や国債発行が
必要になる可能性もあります。
デジタル社会における新たなリスク
SNSによるデマ拡散
災害時には常にデマや根拠のない噂が流れます
が、首都直下地震のような大規模災害では
特に深刻な事態につながるおそれがあります。
現代社会ではSNSの発達により「拡散」の
スピードが加速しており、誤った情報が
短時間で広まることが懸念されます。
災害デマが拡散する背景には
「不安」「怒り」「善意」といった
心理があるとされています。
正確な情報を得ることが困難な状況下で、
人々は断片的な情報を過大に解釈したり、
自分の不安を和らげるために信じたい情報を
無批判に受け入れたりする傾向があります。
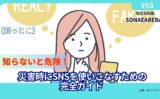
感染症拡大のリスク
東京都の最新の被害想定では、
新型コロナウイルスなどの感染症対策
によって救助活動が遅れたり、
逆に救助活動によって
感染症対応が不十分になったりする
おそれが指摘されています。
大規模災害時の避難所では、
多くの人が密集して生活することになり、
感染症が拡大するリスクが高まります。
特に水道や下水道などの
衛生インフラが機能しない状況では、
感染リスクはさらに高まるでしょう。
私たちにできる備え – 被害を軽減するために
建物の耐震化と家具の固定
首都直下地震による被害を軽減するためには、
建物の耐震化が最も効果的です。
東京都の最新の被害想定でも、
過去10年間で建物の耐震化が進み、
死者数の想定が3割以上減少したことが
示されています。
個人でできる対策としては、
住宅の耐震診断・耐震補強を行うことが
重要です。
また、家具の固定や配置の見直しも、
室内での被害を減らすために効果的です。
特に寝室や子どもの部屋には大型の家具を
置かないなどの工夫が必要でしょう。
初期消火対策の重要性
先述のとおり、首都直下地震による死者の
7割は火災によるものと想定されています。
そのため、初期消火対策は極めて重要です。
感震ブレーカーの設置は、
地震時の電気火災を防ぐ効果的な方法です。
また、消火器の設置や使い方の確認、
消火用バケツの準備なども重要です。
特に密集市街地では、
隣家への延焼を防ぐためにも初期消火の
成功率を高めることが重要です。
備蓄と非常持ち出し袋の準備
ライフラインの復旧には時間がかかるため、
少なくとも1週間分の水や食料、
生活必需品の備蓄が推奨されています。
また、避難が必要になった場合のために、
非常持ち出し袋を準備しておくことも
重要です。
備蓄品は定期的に消費し、
新しいものに入れ替える
「ローリングストック法」が効果的です。
また、高齢者や乳幼児、
アレルギーがある方など、
特別なニーズがある場合は、
それに応じた備蓄品を準備することも
忘れてはなりません。
地域コミュニティでの防災活動
大規模災害時には、
公的な救助・支援だけでは限界があります。
そのため、地域コミュニティでの防災活動が
重要な役割を果たします。
地区防災計画の策定・実施や、
定期的な防災訓練への参加は、
地域の防災力を高めるために効果的です。
特に、発災直後の救助活動は、
近隣住民による共助が最も効果的です。
阪神・淡路大震災では、倒壊した建物から
救出された人の約8割が、近隣住民によって
救助されたという事実があります。
首都直下地震対策の最新動向
国と東京都の対策
首都直下地震への備えとして、
国は「首都直下地震対策特別措置法」を
制定し、首都直下地震緊急対策区域を
指定しています。
この区域では、
震度6弱以上の地域や津波高3m以上で海岸堤防
が低い地域などが対象となっています。
また、「首都直下地震緊急対策推進基本計画」
も策定され、公助、共助、自助によって
社会全体として被害軽減に向けた備えを
行う方針が示されています。
参考リンク:
内閣府 防災情報のページ
東京都も2022年に被害想定を見直し、
具体的な対策を盛り込んだ
地域防災計画の改定を進めています。
参考リンク:
東京都防災ホームページ「防災ブック」
首都機能のバックアップ体制
首都直下地震では、
政府機能や経済中枢機能など、
首都中枢機能への影響が甚大となる
可能性があります。
そのため、首都機能のバックアップ体制
の構築も重要な課題です。
政府は、
首都直下地震発生時の代替拠点の整備や、
重要データのバックアップ体制の強化などを
進めています。
また、民間企業でも
事業継続計画(BCP)の策定・見直しが
進められています。
まとめ – 備えあれば憂いなし
首都直下地震は、
発生すれば甚大な被害をもたらす可能性が
ありますが、適切な対策を講じることで
被害を大幅に軽減できることも事実です。
東京都の最新の被害想定でも、
過去10年間の耐震化の進展などにより、
想定死者数が3割以上減少したことが
示されています。
私たち一人ひとりができる備え、
地域コミュニティでの取り組み、
そして行政による対策を組み合わせることで、
首都直下地震の被害を最小限に抑えることが
可能です。
「備えあれば憂いなし」
という言葉の通り、いざという時のために
今から準備を始めましょう。
最後に、小池東京都知事の言葉を
引用して締めくくりたいと思います。
いざ災害が起こった時に、
自分や大切な人の命を守るという
のは、まずは都民の皆様一人ひとりが
日頃から備えておくということが
必要です。
いつも申し上げておりますが、
「備えよ、常に」であります。
まずは、今できることから
始めていただきたいと思います。
参考リンク:出典
都庁総合ホームページ
小池知事「知事の部屋」/記者会見
(令和5年9月1日)
今回の記事が、
皆さんの防災意識を高め、
具体的な備えのきっかけになれば幸いです。
次回もお役立ち情報をお届けしますので、
ぜひチェックしてください!
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。