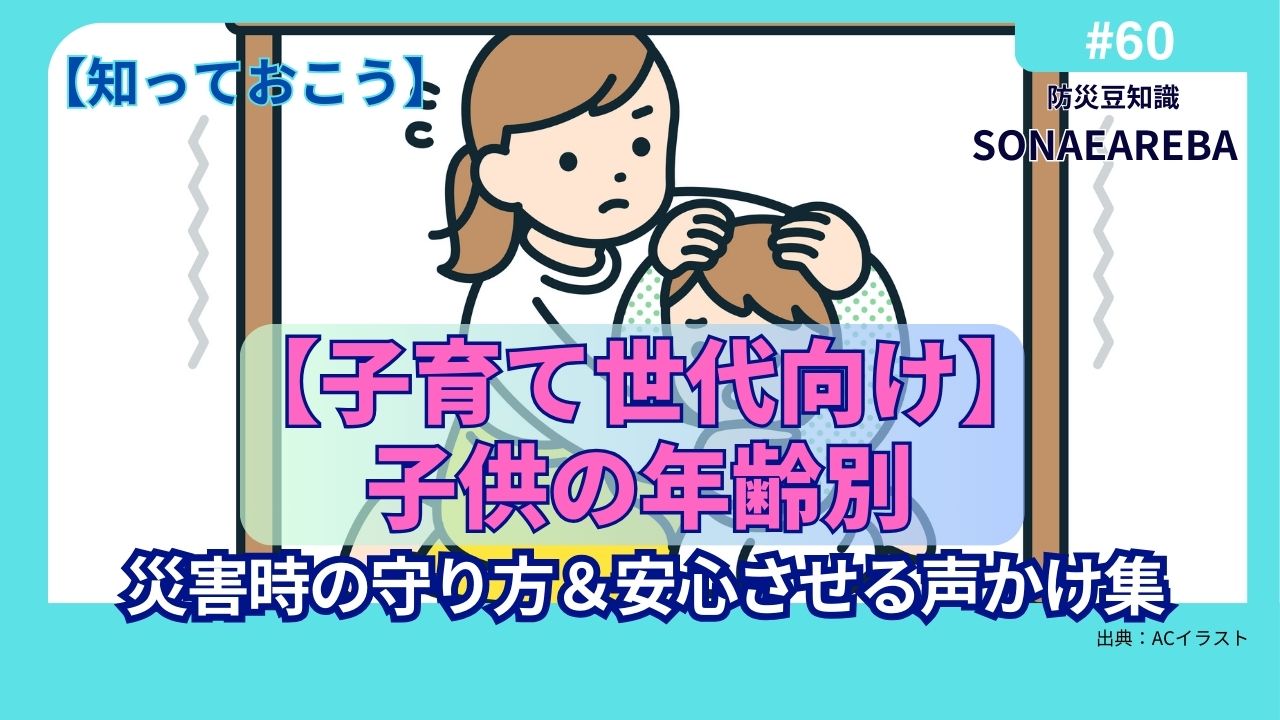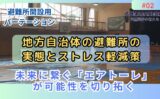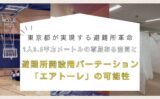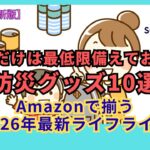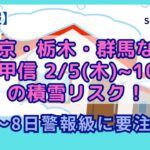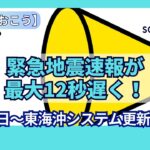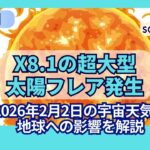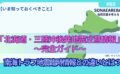この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
災害はいつ、
どこで起きるか予測できません。
特に子育て世代にとって、
災害時に子どもをどう守り、
どう声をかければいいのか、
事前に知っておくことは非常に重要です。
私自身、幼い子どもを持つ親として、
「もし災害が起きたら…」
という不安は常にあります。
この記事では、
子どもの年齢別に適切な防災対策と、
災害発生時の声かけ方法をまとめました。
いざというときに落ち着いて行動するための
参考にしていただければ幸いです。
災害時の子どものこころと行動の特徴
災害が発生すると、
子どもたちは年齢に関わらず
様々なストレス反応を示します。
まずは共通して見られる反応を
理解しておきましょう。
子どもに共通して見られるストレス反応
災害時、子どもたちには
以下のような反応が現れることがあります:
- 再度同じような災害が起きるのではないか
という強い不安 - 大切な人や自分自身が傷ついたり、
離ればなれになることへの恐れ - 被災した地域や風景を見ることによる
ショック - 家族から離れることへの強い抵抗
- 睡眠障害や夜泣きの増加
- 泣き続ける、
または感情表現が乏しくなる
これらの反応は自然なものであり、
多くの子どもに共通して見られます。
しかし、年齢によって示す反応や
必要なケアは異なります。
そのため、子どもの年齢に合わせた対応が
必要になります。
年齢別の子どもの反応と対応方法
乳児(0〜2歳)の特徴と対応
乳児の災害時の反応
乳児は言葉で不安や恐怖を表現できないため、
次のような行動で示すことが多いです:
- 普段よりも親にくっついて離れない
- 睡眠パターンや食事量の変化
- いつもより泣く頻度が増える、
またはイライラしやすくなる - おむつが外れていた子どもが
再びおもらしをするなどの赤ちゃん返り
乳児への効果的な対応と声かけ
この時期の子どもには、
言葉よりも身体的な安心感を与えることが
最も効果的です:
- 抱きしめる:
「ママ/パパがそばにいるよ」と声を
かけながら優しく抱きしめましょう - 身体的接触を増やす:
手を握ったり、背中をさすったりして
安心感を与えます - いつも通りのルーティンを心がける:
できる限り、食事や睡眠の時間を
一定に保ちます - あやす:
乳児が泣いている場合は、
優しくあやして気を紛らわせます
乳児に必要なのは何よりも保護者の存在です。
災害時には保護者自身も不安を感じますが、
できるだけ落ち着いた態度で接することで、
乳児も安心します。
幼児(3〜5歳)の特徴と対応
幼児の災害時の反応
幼児は自分の感情を言葉で表現し始める時期
ですが、まだ十分ではありません:
- 大人への依存度が高まる
- 指しゃぶりやおねしょなど、
より幼い行動への退行 - 「怖い」「悲しい」などの感情表現
- 夜泣きや悪夢の増加
- 特定の状況(音、光など)への
恐怖や過敏反応
幼児への効果的な対応と声かけ
この年齢の子どもには、
安心感を与えながらも、状況を
簡単な言葉で説明することが大切です:
- 「近くにいるよ」と伝える:
「お母さん/お父さんはあなたのそばにいる
からね」「あなたから離れないからね」
と明確に伝えましょう - シンプルな言葉で説明する:
「今は少し変わった状況だけど、たくさん
の大人が安全のために頑張っているよ」
などと伝えます - 見通しを示す:
「今日はここで寝るよ」
「明日は〇〇に行くよ」など、
予定を簡単に説明します - 気持ちを肯定する:
「怖いね」「不安だよね」と
子どもの気持ちを否定せず受け止めます
子どもが「怖い」と言った時に
「怖くないよ」と否定するのではなく、
「怖いよね、でもママ/パパがそばにいるから
ね」と気持ちを受け止めつつ
安心感を与えることが大切です。
小学生(6〜12歳)の特徴と対応
小学生の災害時の反応
小学生は状況を理解する能力が発達し
始めますが、同時に不安も増します:
- 災害について具体的な質問をする
- 親の反応に敏感になる
- 災害を自分のせいだと考えることがある
- 無力感や悲しみを感じる
- 集中力の低下や学習意欲の減退
- 友達との関係の変化
小学生への効果的な対応と声かけ
この年齢の子どもには、より詳しい説明と、
役割を与えることが効果的です:
- 正直に状況を説明する:
災害の状況について、理解できる範囲で
正直に説明します
「地震で家が少し壊れたけど、
もう大きな揺れは来ないと思うよ」 - 「あなたは大切」と伝える:
「あなたの存在が私たちの支えになってい
るよ」と子どもの価値を伝えます - 小さな役割を与える:
「一緒に防災バッグを確認してくれる?」
など、手伝いをお願いします - 質問に答える:
子どもの質問には、できる限り正直に
答えましょう - メディア視聴を制限する:
災害のニュースや動画の視聴時間を
制限し、過度の不安を防ぎます
小学生は「役に立ちたい」という気持ちが
強いため、家族の一員として小さな役割を
与えることで、無力感を軽減できます。
「一緒にいてくれてありがとう」という
言葉かけも効果的です。
中学生以上の特徴と対応
中学生以上の災害時の反応
中学生以上になると、
大人に近い反応を示すようになりますが、
同時に特有の反応もあります:
- 自分でコントロールできないことへの不満
- 将来への不安
- 友人関係の変化に対するストレス
- 災害について深く考え込む
- 無関心を装うことがある
中学生以上への効果的な対応と声かけ
この年齢の子どもには、より対等な立場での
対話と情報共有が重要です:
- 意見を尊重する:
「あなたはどう思う?」と意見を求め、
真剣に耳を傾けます - 情報を共有する:
正確な情報を適切に共有し、
一緒に考える姿勢を見せます - 感情表現を促す:
「今の気持ちを話してみる?」と
声をかけ、感情表現を促します - プライバシーを尊重する:
一人になりたいときは、
適度な距離を保ちます - 前向きな未来像を示す:
「今は大変だけど、みんなで協力して
乗り越えていこう」と希望を伝えます
中学生は何でもできるように見えても、
災害時は小学生と同様の心の動きをすること
があります。大人として扱いつつも、
必要なサポートを提供することが重要です。
事前準備と防災対策
災害時に適切に対応するためには、
事前の準備が欠かせません。
特に子育て世帯では、
子どもの年齢に合わせた準備が必要です。
家族での話し合い
最も基本的な防災対策は、
家族での話し合いです。
以下の項目について、
子どもの年齢に合わせて
話し合っておきましょう:
| 話し合う内容 | 子どもに伝えておくこと |
|---|---|
| 1. 災害の種類・場所別の対処方法 | 地震:テーブルや机の下にもぐり、座布団などで頭を守る 火災:ハンカチで口・鼻を押さえてすぐ逃げる 水害:高いところに避難する |
| 2. 避難場所の確認 | 最寄りの避難場所とそこまでのルートを確認 |
| 3. 災害時の役割分担 | 子ども専用の防災バッグを持ち出す役割など |
| 4. 家の中の危険な場所の確認 | 家具の転倒の危険がある場所など |
| 5. ハザードマップの確認 | 住んでいる地域の危険箇所を確認 |
| 6. 災害時の連絡方法 | 家族が離ればなれになった時の連絡ルール |
| 7. 連絡手段の使い方 | 災害伝言ダイヤルや公衆電話の使い方など |
| 8. 防災バッグの確認 | 防災バッグの場所と中身の確認 |
子どもが年中〜年長以降になれば、
ある程度の理解が可能です。
日常的に「地震や火事が起きたらどうする?」
と問いかけながら、
家族全員で話し合いましょう。
年齢別防災グッズの準備
子どもの年齢によって必要な防災グッズも
変わってきます。
年齢に合わせた防災グッズを
準備しておきましょう:
乳児(0〜2歳)向け防災グッズ
- 粉ミルク(できれば冷水で溶けるタイプ)
- 哺乳瓶
- おむつ(3日分程度)
- おしりふき
- 着替え
- バスタオル(防寒や簡易ベッドとして)
- お気に入りのおもちゃ(心の安定に)
- 離乳食(月齢に合わせたもの)
- 抱っこひも
幼児(3〜5歳)向け防災グッズ
- 着替え
- お気に入りのぬいぐるみや毛布
- 簡単な食べ物(アレルギー対応のもの)
- おやつ
- 子ども用の小さなリュック
(自分の大切なものを入れる) - お絵かき道具(時間つぶしに)
- 歯ブラシ・歯磨き粉
小学生(6〜12歳)向け防災グッズ
- 子ども用のヘルメットや防災頭巾
- 軍手
- 筆記用具
- 子ども用の携帯食料と水
- 家族の連絡先を書いたカード
- 小さな懐中電灯
- 簡易トイレ
防災グッズを用意するだけでなく、
子どもにその場所と使い方を
教えておくことが大切です。
特に小学生以上の子どもには、
非常時に自分で使えるよう、
普段から説明しておきましょう。
避難訓練のポイント
子育て世帯での避難訓練は、
子どもが実際の災害時に落ち着いて
行動できるようにするための重要な準備です。
避難訓練の目的
- 子どもにとって:
保育士や保護者の指示をしっかり聞いて、
安全に避難できるようにする - 保護者にとって:
冷静な判断と適切な指示を出せるように
する、避難時の問題点を把握する
子どもに分かりやすく教えるポイント
- イメージトレーニング:
災害時の音や状況を想像させる
(電線がビュンビュンと鳴る音、
壁がゴーゴーと音を立てるなど) - 繰り返し訓練する:
最初は怖がっても、繰り返すことで
慣れていきます - 視覚教材の活用:
年齢に合わせた視覚教材(絵や動画)
を使って分かりやすく説明する - 役割を与える:
子どもに小さな役割を与え、
主体的に参加させる - ほめる:
訓練後は必ず「よくできたね」とほめて、
前向きな記憶にする
避難訓練は子どもにとって怖い体験になる
可能性もありますが、
「こうすれば安全に逃げられる」という
経験を積むことで、実際の災害時の安全基礎
体力になります。
災害種類別の対応方法
災害の種類によって、
取るべき行動や子どもへの声かけも
異なります。主な災害別の対応方法を
見ていきましょう。
地震の場合
地震発生時の基本行動
- 屋内:
「机の下に隠れて!」と声をかけ、
テーブルや机の下に避難させる - 屋外:
「頭を守って!広い場所に行くよ!」と
声をかけ、かばんや上着で頭を守りながら
広い場所へ移動する
子どもへの声かけ例
- 乳幼児:
「大丈夫だよ、ママ/パパが
ずっと一緒だよ」と抱きしめながら - 幼児:
「今揺れているけど、すぐに止まるから
ね。ママ/パパと一緒にいよう」 - 小学生:
「机の下に隠れて、揺れが止まるまで動か
ないでね。落ち着いていよう」 - 中学生:
「まずは身を守って。揺れが収まったら、
次にすることを一緒に考えよう」
地震の際は、子どもの恐怖心を
和らげるために、落ち着いた声で指示を
出すことが重要です。
また、余震の可能性も伝えておくと、
再び揺れが来ても慌てずに済みます。
火災の場合
火災発生時の基本行動
- 「ハンカチで口と鼻を押さえて!」と
指示し、煙を吸い込まないようにする - 「かがんで歩こう」と姿勢を
低くするよう指示する - 「急いで外に出るよ」と声をかけ、
できるだけ速やかに避難する
子どもへの声かけ例
- 乳幼児:
抱きかかえながら「大丈夫、すぐに安全な
ところに行くからね」 - 幼児:
「ママ/パパの手をしっかり握って。
一緒に外に出ようね」 - 小学生:
「ハンカチで口を押さえて、お母さん/
お父さんについてきて。走らないでね」 - 中学生:
「落ち着いて。ハンカチで口を押さえて、
姿勢を低くして一緒に避難しよう」
火災の場合は、
煙による被害を防ぐことが最優先です。
子どもには煙を吸わないことの重要性を、
日頃から教えておくとよいでしょう。
水害の場合
水害発生時の基本行動
- 事前に警報や避難情報を確認し、
早めの避難を心がける - 「高いところに上がろう」と声をかけ、
2階や高台へ避難する - 浸水している場所を歩く場合は
「手をつないで、ゆっくり歩こう」と
注意を促す
子どもへの声かけ例
- 乳幼児:
抱きかかえながら
「大丈夫、安全なところに行くからね」 - 幼児:
「雨がたくさん降ってきたから、高いとこ
ろに行こうね。ママ/パパと一緒だよ」 - 小学生:
「川の水があふれそうだから、
○○(避難場所)に行くよ。
準備を手伝ってくれる?」 - 中学生:
「避難情報が出たから、一緒に避難場所に
行こう。持っていくものを確認しよう」
水害の場合は、天候の急変に備え、
早めの避難が鍵となります。
子どもには、ハザードマップで危険な場所
を事前に教えておくことも重要です。
参考リンク:
ハザードマップポータルサイト
身のまわりの災害リスクを調べる
災害後の子どものケア
災害が落ち着いた後も、
子どもの心のケアは継続して必要です。
以下のポイントに注意しましょう。
子どもの心の変化に気づく
災害後、子どもには以下のような
変化が現れることがあります:
- 食欲不振や過食
- 睡眠障害(悪夢、不眠など)
- 集中力の低下
- 以前は怖がらなかったことへの恐怖
- 身体的な症状(頭痛、腹痛など)
- 攻撃的な行動や引きこもり
これらの変化が長期間続く場合や、
日常生活に支障をきたす場合は、
専門家への相談を検討しましょう。
日常生活を取り戻すためのサポート
- 規則正しい生活リズムを作る:
食事や睡眠の時間を一定にして、
日常感を取り戻します - 遊びや活動の機会を提供する:
子どもが楽しめる活動を通して、
ストレスを発散させます - 学習の機会を確保する:
学校が再開するまでの間も、学習の習慣を
維持できるよう支援します - 子どもの話に耳を傾ける:
子どもが体験や感情を話したがる場合は、
じっくり聞きます - 無理に話させない:
話したがらない場合は無理に聞き出そうと
せず、準備ができるまで待ちます
子どものケアに専念するためには、
保護者自身の心身の健康も重要です。
「子どものためにも、まずは自分を大切に」
という意識を持ちましょう。
支援サービスの活用
災害後には、子どものためのさまざまな
支援サービスが提供されることがあります:
- 子どものためのスペース:
NPOなどが開設する、
勉強や遊びができる場所 - 心のケア相談:
専門家による相談サービス - グループ活動:
同じ体験をした子ども同士で行う
グループ活動
これらのサービスは、
子どもの心の回復を助け、
保護者の負担を軽減する効果があります。
積極的に活用しましょう。
まとめ:災害時の子どものケアチェックリスト
この記事でご紹介した内容を、
年齢別にチェックリスト形式でまとめました。
いざというときに確認できるよう、印刷して
保管しておくことをおすすめします。
乳児(0〜2歳)向けチェックリスト
- □ 抱きしめて安心感を与える
- □ 「ママ/パパがそばにいるよ」と
声をかける - □ いつも通りの食事・睡眠リズムを
心がける - □ 最低3日分の粉ミルク・おむつを
用意する - □ 抱っこひもで
両手を空けられるようにする
幼児(3〜5歳)向けチェックリスト
- □ 「離れないからね」と明確に伝える
- □ シンプルな言葉で状況を説明する
- □ 見通しを持たせる言葉かけをする
- □ 気持ちを否定せず受け止める
- □ お気に入りのぬいぐるみなどを
持っておく
小学生(6〜12歳)向けチェックリスト
- □ 年齢に合わせた正直な説明をする
- □ 小さな役割を与える
- □ 質問には丁寧に答える
- □ メディア視聴を適切に制限する
- □ 家族の連絡先カードを持たせる
中学生以上向けチェックリスト
- □ 対等な立場で対話する
- □ 正確な情報を共有する
- □ 感情表現を促す
- □ プライバシーを尊重する
- □ 前向きな未来像を示す
災害はいつ起こるかわかりません。
しかし、事前の準備と心構えがあれば、
子どもたちを守り、心の傷を最小限に
抑えることができます。
この記事が、子育て世代の皆さんの
防災対策の一助となれば幸いです。
最後に大切なことは、
災害時こそ「あなたはひとりじゃない」という
メッセージを子どもに伝え続けることです。
親の存在と愛情が、子どもにとって
最大の安心感になります。
参考資料・相談窓口
- 災害時の子どものケアに関する相談:
令和6年能登半島地震に関する
こども家庭庁からのお知らせ - 心理的応急処置(PFA)の詳細:
セーブ・ザ・チルドレン
「子どものための心理的応急処置」 - 災害時の子どもの生活ガイド
(認定NPO法人カタリバ)
皆さんの家庭に、
日々の安心と笑顔がありますように。
そして、この記事が「もしも」のときの
支えになれば幸いです。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。