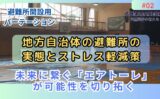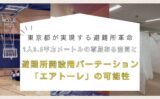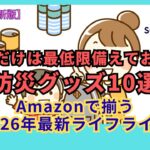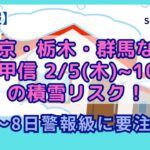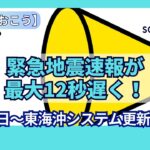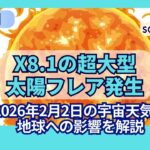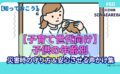本記事はアフィリエイトとして、
商品を紹介して収益を得る可能性があります。
こんにちは!SONAEAREBAです。
災害大国日本で生きる私たちにとって、
スマートフォンは単なる通信ツールを超えた
「命をつなぐライフライン」です。
しかし、いざという時に
「圏外」「バッテリー切れ」で
使えなくなってしまっては意味がありません。
本記事では、2025年最新の情報をもとに、
通信障害が発生した状況でも使えるアプリや
設定、災害時に役立つスマホの活用法を
徹底解説します。
これから紹介するテクニックを
今すぐ実践して、あなたとご家族の
「いざという時」に備えましょう。
災害時に直面する通信の課題と対策の重要性
近年、地震や豪雨による大規模災害が
増加傾向にあります。
2024年の能登半島地震では、
多くの方が通信障害に見舞われ、
情報収集や安否確認が困難になりました。
災害発生時には通信インフラが
大きなダメージを受け、基地局の停止や
回線の混雑により、通信が著しく制限される
ケースが頻発しています。
災害時に発生する通信の問題
災害時に私たちが直面する通信の問題は
主に以下の3つです。
- 通信インフラの物理的損壊:
地震や水害による基地局の倒壊・浸水 - 回線の輻輳(ふくそう):
多数の人が一斉に通信を行うことによる
回線のパンク - 停電による電源喪失:
長時間の停電によるスマホや
Wi-Fiルーターの電源切れ
東日本大震災では
最大で約9割の通信が遮断され、
能登半島地震でも広範囲で通信障害
が発生しました。
これらの問題に対応するためには、
通信に頼らないオフラインでの
情報収集手段と、長時間使用可能な
電源確保が重要になります。
なぜ今、オフライン対応が重要なのか
「すぐに復旧するだろう」
という楽観的な考えは危険です。
災害の規模によっては、
通信の復旧に数日から数週間かかる
ケースもあります。
さらに、通信が復旧したとしても、
多くの人が一斉に使用することで
回線が混雑し、実質的に使用できない
状況になることも。
現代社会では、情報が命を左右することも
少なくありません。
避難指示や危険区域の把握、
支援物資の配布情報など、
生存に直結する情報を得るためにも、
オフラインでも機能するスマホの活用法を
知っておくことは、もはや必須のスキル
と言えるでしょう。
オフラインでも使える地図アプリ3選【2025年最新】
災害時、
避難所や安全な経路を確認するために
最も重要なのが地図アプリです。
しかし、通常の地図アプリは
通信環境がないと使用できません。
ここでは、オフラインでも使える
地図アプリを紹介します。
Google マップのオフラインマップ機能
Googleマップは多くの方が
日常的に使用している地図アプリですが、
オフラインでも使える機能があることを
ご存知でしょうか?
ダウンロード方法:
- スマホでGoogleマップアプリを開く
- オフラインマップを
ダウンロードしたい地域を検索 - 画面下部の住所または
場所の名前をタップし、
その他アイコン「⋮」→
「オフラインマップをダウンロード」
をタップ
メリット:
- 災害時に避難場所が確認できる
- GPS機能はインターネットがなくても
利用できるため、現在地が確認可能 - バッテリーの節約になる
注意点:
- ダウンロードデータには有効期限があり、
15日前になると自動更新 - 公共交通機関・自転車・徒歩などの
経路表示はオフラインでは使用不可 - マップデータのダウンロードに
データ容量が必要
Yahoo! MAPの防災モード
Yahoo! MAPには「防災モード」があり、
災害時や通信障害などの緊急時でも、
オフラインでハザードマップや自宅周辺など
の地図が確認できます。
2023年3月からは、
事前にダウンロードした地図が自動的に
更新される機能も追加されました。
特徴:
- 「土砂災害」「洪水」「津波」
「地震(地盤のかたさ)」の
4種類のハザードマップがオフライン対応 - Wi-Fi接続時に自動で地図が
更新されるため、常に最新情報を確保可能 - 自宅、職場を中心に南北ぞれぞれ約10km、
東西それぞれ約6kmの範囲をカバー
参考リンク:
オフラインで地図が使える
Yahoo!マップの「防災モード」
MAPS.ME
MAPS.MEは
世界中の地図をオフラインで利用できる
地図アプリです。
旅行者向けに開発されましたが、
災害時の利用にも適しています。
特徴:
- 世界中の地図をオフラインで
ダウンロード可能 - ドライブやサイクリングなど交通手段
に合わせたナビゲーション機能 - 通常のマップには載っていない隠れた
スポットも表示される
※高知県防災アプリ(地域特化型)
高知県の公式防災アプリは、
地域に特化した詳細な防災情報を提供します。
他の自治体も同様のアプリを提供している
ケースが増えています。
特徴:
- 警戒度により「地震」などのボタンの色
が変化し、異常をすぐ察知しやすい - 重要な情報を時系列で追える
タイムライン機能 - オフライン地図は事前に
手動でダウンロードが必要
参考リンク:
高知県ホームページ
「高知県防災アプリ」
オフライン地図アプリの選び方と事前準備のポイント
オフライン地図アプリを選ぶ際の
ポイントは以下の3点です。
- 自分の行動範囲をカバー:
自宅周辺だけでなく、
職場や子どもの学校、よく行く場所など、
日常の行動範囲をカバーするエリアを
ダウンロードしておきましょう。 - 定期的な更新:
道路状況や施設情報は常に変化します。
月に1回程度、最新情報に更新することを
お勧めします。 - 複数のアプリの併用:
一つのアプリだけでなく、
GoogleマップとYahoo! MAPなど、
複数のアプリを併用することで、
互いの弱点を補完できます。
災害時の安否確認アプリ・サービス【最新ガイド】
災害が発生した際、
まず気になるのは家族や友人の安否です。
ここでは、通信環境が制限された状況でも
使える安否確認の方法を紹介します。
LINE安否確認機能
LINEは2011年の東日本大震災で
大切な人と連絡が取れなかった経験をもとに
誕生したコミュニケーションアプリです。
現在では災害時に特化した
安否確認機能も提供しています。
使い方:
- 震度6以上などの地震や
その他大規模な災害が起こったとき、
LINEのホーム画面に「安否を報告」
ボタンが赤枠で表示される - 「安否を報告」をタップして
自分の状況を選択し報告 - 友だちリストの「安否確認」から
家族や友人の安否状況を確認可能
ポイント:
- LINEは電話回線がつながらなくても、
インターネットにつながっていれば
利用可能 - 友だちの安否状況がアイコンの下に
表示される - リアクション機能を活用することで
バッテリー消費を抑えられる
参考リンク:
LINE公式サイト
「緊急時に役立つLINEの使い方」
災害用伝言板サービス
各携帯電話会社が提供している
「災害用伝言板」は、災害時に音声発信が
集中して繋がりにくくなった場合に、
メッセージを預かりして伝えるサービスです。
ソフトバンクの災害用伝言板の例:
- 震度6弱以上の地震など
大規模災害発生時に開設 - 「無事です」「自宅にいます」など
状況を選択して登録可能 - 全角100文字までのコメント入力も可能
- 他社携帯電話やパソコンからも確認可能
事前設定のポイント:
- 自動Eメール送信設定を行っておくと、
安否情報登録時に指定した
メールアドレスに通知される - 10件までのあて先を設定可能
- 災害時でなくても設定は可能なので、
今すぐ設定しておきましょう
参考リンク:
各社 災害用伝言板サービス
ソフトバンク au NTTドコモ
楽天モバイル Y!mobile
災害用伝言板(web171)
NTT東日本 NTT西日本
ココダヨ(位置情報共有・防災アプリ)
2025年の安否確認アプリランキングで
1位に選ばれた「ココダヨ」は、
地震速報・災害情報の通知と
位置情報共有機能を兼ね備えたアプリです。
機能:
- 家族や友人と位置情報を
リアルタイムで共有 - 地震・津波・豪雨などの災害情報を
プッシュ通知で受信 - 事前に設定しておけば、
災害時に自動で安否を共有
参考リンク:
【ココダヨ】公式サイト
安否確認と見守り、位置情報共有・防災速報
Facebook災害時情報センター
Facebookの「災害時情報センター」は、
利用者間で安否確認ができるだけでなく、
災害発生後に必要な食料や避難場所、
移動手段などを探したり提供したりすること
ができる「コミュニティヘルプ」機能も
備えています。
起動条件:
- 第三者機関が事故・災害の発生を
Facebookに報告 - 利用者の投稿が多数確認された場合に起動
- 自然災害や事故災害の発生時には
「コミュニティヘルプ」も起動
参考リンク:
Facebook
セーフティチェック(災害時安否確認機能)
がオンになるしくみ
安否確認サービスを最大限活用するためのポイント
- 複数サービスの事前登録:
災害の種類や規模によって
使えるサービスが異なるため、
複数のサービスに登録しておく - 家族間での利用方法の共有:
家族全員がどのサービスをどう使うか、
事前に話し合っておく - 定期的な動作確認:
特に災害用伝言板は、
毎月1日や15日など「体験利用日」
があるので、実際に使ってみる - バッテリー消費を考慮:
安否確認後は、できるだけアプリを
終了してバッテリーを節約する
災害時のSNS活用法と信頼性の高い情報収集テクニック
災害時、SNSは情報収集・発信の
強力なツールになります。
しかし、デマ情報、フェイクニュースも
拡散されやすい特性があるため、
正しい活用法を知っておくことが重要です。
各SNSプラットフォームの特徴と活用法
X(旧Twitter)の活用法
メリット:
- リアルタイム性が高く、
最新情報が素早く拡散される - ハッシュタグ(例:#江戸川区)を
使うことで地域の被害情報を集約できる - 公式アカウント(自治体、気象庁など)
から信頼性の高い情報を取得可能
注意点:
- デマ情報・フェイク画像が拡散されやすい
- 救助要請ツイートが救助完了後も
残り続け、混乱を招くこともある
活用テクニック:
- 自治体や気象庁など公式アカウントを
あらかじめフォローしておく - 地域ごとのハッシュタグを知っておく
(例:自治体名+「災害」など) - 複数の情報源で確認できない情報は
安易に信じない・拡散しない
LINEの活用法
メリット:
- 「LINEスマート通知」機能で
防災情報を受け取れる - 位置情報共有機能で現在位置を
正確に伝えられる - リアクション機能でバッテリー消費を
抑えながら確認可能
活用テクニック:
- 事前に「LINEスマート通知」の
防災速報を設定 - 複数人でグループを作成し、
一度に情報共有 - バッテリー節約のため、
必要最小限のやり取りを心がける
Facebookの活用法
メリット:
- 「災害時情報センター」で
安否確認と支援のマッチングが可能 - 長文での詳細な情報共有が可能
- グループ機能で地域コミュニティの
情報集約ができる
活用テクニック:
- 自治体や地域コミュニティのグループに
事前に参加しておく - プロフィールに居住地情報を設定して
おくと、災害時の情報が届きやすい - 「災害時情報センター」の使い方を
事前に確認しておく
SNS情報の真偽を見極めるポイント
防災科学技術研究所の臼田裕一郎センター長
によると、SNS情報の真偽を見極める
ポイントは以下の通りです:
- 発信された情報をうのみにせず、
落ち着いてみる姿勢 - 公式情報と比較しながら見る
- 複数の情報源で確認する
特に発災直後は、
誤情報やデマが拡散されやすいため、
公式情報を基準に判断することが重要です。
参考リンク:
NHK水戸放送局 茨城WEB特集
X(旧ツイッター)LINEなどSNSを
災害時どう活用?
自治体のSNS活用の最新事例
南相馬市では、
東日本大震災を教訓にSNSの情報収集を
強化するため、LINEを使ったシステムを
活用しています。
システムの特徴:
- 住民から情報が寄せられると
AIが自動で返信 - 対話によってより具体的な情報を引き出す
- 2023年9月の記録的大雨では120件の
被害情報が寄せられ、避難指示などに活用
このような双方向のやりとりを行うシステム
は、一方的な情報発信よりも正確な情報収集
が可能になります。
オフライン通信を可能にする最新アプリ【メッシュネットワーク活用】
通信インフラが完全に機能停止した状況でも、
近くのスマホ同士で通信できる
「メッシュネットワーク」技術を活用した
アプリが注目されています。
Bridgefy – オフラインメッセージアプリ
Bridgefyは1,100万回以上ダウンロードされた、
インターネットなしでメッセージを
送れるNo.1アプリです。
特徴:
- Bluetoothを使用して、
近くの人(最長100メートル)に
メッセージを送信可能 - 連絡先を追加する必要がなく、
近くのBridgefyユーザーと
すぐにチャット可能 - パブリックチャットで知り合った相手と
プライベートメッセージも送信可能
使い方:
- Bluetoothをオンにする
- 初回のみ、インターネット接続が
有効な状態でBridgefyを開く
(アプリ有効化に必要) - 有効化後はパブリックチャットで
近くの人にメッセージを送信可能 - 相手のアバターをタップして
プライベートメッセージを送信
Bridgefyは、学校、コンサート、
自然災害後など、従来のネットワークが
使えない状況で人々をつなげるために
広く利用されています。
Briar – セキュリティ重視のメッセージングアプリ
Briarは活動家、ジャーナリスト向けに
設計された、安全性と堅牢性を重視した
メッセージングアプリです。
特徴:
- 中央サーバーを使用せず、
端末間で直接メッセージを同期 - インターネット中断時はBluetoothや
Wi-Fiを経由して同期 - インターネット回復時は
Torネットワークを経由して匿名性を確保
機能:
- プライベートメッセージング
- グループでの会話
- フォーラム機能
- ブログ投稿機能
特に高いプライバシーが求められる状況や、
長期的な通信インフラ障害に備えたい方に
おすすめです。
メッシュネットワークアプリの限界と活用のポイント
メッシュネットワークアプリには以下の
限界があることを理解しておきましょう:
- 通信範囲の制限:
基本的にBluetooth範囲(約100m)内の
ユーザー同士のみ通信可能 - 利用者数の制約:
周囲に多くのユーザーがいなければ
機能しない - バッテリー消費:
Bluetoothを常時オンにするため
バッテリー消費が早い
活用のポイント:
- 日常的に家族や同僚にもインストールを
勧め、利用者数を増やしておく - 定期的に起動して最新版に
アップデートしておく - 災害時は通信の中継点となるため、
人が集まる避難所などで特に有効
災害時に備えるモバイルバッテリー選び【2025年最新ガイド】
災害時、スマホを長時間使い続けるためには、
大容量のモバイルバッテリーが必須です。
ここでは、災害に備えたモバイルバッテリーの
選び方と最新おすすめ製品を紹介します。
災害時に適したモバイルバッテリーの選び方
1. 電池容量は大きいものを選ぶ
災害時は
「次にいつモバイルバッテリー
の充電ができるかわからない」
状況に陥りがちです。
そのため、基本的には容量の
大きいものがベストとなります。
目安としては、20,000mAh程度の容量が
おすすめです。
容量の目安:
- 20,000mAhの容量があれば、
容量が2,500mAhのスマートフォンを
約4.8回充電可能 - 実際には充電効率の関係で、
充電できる回数は容量の60%程度
になる点に注意
2. 複数の端末を充電できる機能
3. 耐久性と防水・防塵性能
4. ソーラーチャージャーの検討
一般的な折りたたみソーラー充電器は
蓄電しておくことができないものが多いです
が、2025年現在では蓄電可能なタイプも
増えています。
ソーラーチャージャーなら、晴れている時に
蓄電し、好きなタイミングで充電が可能です。
災害用モバイルバッテリーおすすめ製品3選
1. Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)
27650mAhの超大容量でiPhone15Proを
約5回、MacBook Airを約1回以上充電可能な
超大容量かつパワフルなモバイルバッテリー。
2. Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh)
一般的なポータブル電源に比べて約6倍の
長寿命な「リン酸鉄リチウムイオン電池」
を搭載。1229Whの超大容量と
合計最大出力1500Wで、電気毛布や
電子レンジ、ドライヤーまで幅広い家電を
使用可能。別売りのソーラーパネル
「Anker 625 Solar Panel (100W)」を
用いた屋外充電も可能。
3. DE-C50L-20000BK
USB Power Deliveryに対応した容量
20,000mAhのモバイルバッテリー。
USB-Aポートと USB Type-Cポート×2の
合計3ポートを搭載し、単ポートで65W、
合計75Wの出力が可能。
スマホのバッテリーを長持ちさせるテクニック
災害時にスマホのバッテリーを
効率的に使うためのテクニックを紹介します:
- スマホの省電力設定を活用:
画面の明るさを下げる、
バックグラウンドアプリを制限するなど - 機内モードの活用:
通信が復旧するまでは定期的に
機内モードに切り替える - 不要なアプリを終了:
GPS、Bluetooth、Wi-Fiなど
電力を消費する機能をオフに - モバイルバッテリーの適切な保管:
50%程度充電した状態で、
極端な高温・低温を避けて保管
災害に備える日頃からの準備と設定【チェックリスト】
災害時にスマートフォンを最大限活用する
ためには、日頃からの準備が欠かせません。
ここでは、災害前に行っておくべき設定や
準備をチェックリスト形式で紹介します。
スマホの基本設定
- 省電力モードの設定方法を確認
- iPhoneの場合:
設定 > バッテリー > 低電力モード - Androidの場合:
設定 > バッテリー > バッテリーセーバー
- iPhoneの場合:
- 緊急連絡先の登録
- iPhoneの場合:
ヘルスケアアプリ > メディカルID - Androidの場合:
設定 > セキュリティと緊急 > 緊急情報
- iPhoneの場合:
- 自動アップデートの停止設定
- 災害時に貴重なバッテリーを消費しない
よう、自動アップデートを停止
- 災害時に貴重なバッテリーを消費しない
- 位置情報の精度設定
- 高精度モードより
バッテリー節約モードを選択
- 高精度モードより
アプリのインストールと設定
- オフラインマップのダウンロード
- Google マップ
- Yahoo! MAP(防災モード)
- その他専門アプリ
- 安否確認アプリの設定
- 災害用伝言板(各キャリア)
- LINE安否確認
- Facebook災害時情報センター
- オフライン通信アプリの設定
- Bridgefy
- Briar
- 家族や知人にも同じアプリを
インストールするよう依頼
- 電子版の重要書類の保存
- クラウドと端末の両方に保存
- 保険証、運転免許証、パスポートなど
をスキャン/撮影
家族との情報共有計画
- 家族での連絡手段の優先順位を決める
- 通常の通話/メッセージ
- SNS(LINE、Facebook、X)
- 災害用伝言板
- オフライン通信アプリ
- 集合場所の設定
- 第一、第二の集合場所を決めておく
- オフラインマップに保存
- 使用するSNSや合言葉の決定
- 家族間で同じSNSを使用する
- 安否確認時の合言葉を決めておく
(なりすまし対策)
電源確保の準備
- モバイルバッテリーの定期的な充電確認
- 月に一度は充電状態を確認
- 長期保管時は50%程度の充電状態を維持
- ソーラーチャージャーのテスト利用
- 実際に使用して充電効率を確認
- 設置方法や角度などを確認
- 手回し充電器などの代替電源の確保
- 小型の手回し充電器
- 乾電池式の充電器
まとめ:災害時のスマホ活用法を今すぐ実践しよう
本記事では、2025年最新の情報をもとに、
災害時にスマートフォンを最大限活用するため
の方法を紹介してきました。
ポイントをまとめると以下の通りです。
今すぐ実践すべき5つのポイント
- オフラインマップのダウンロード
- Google マップやYahoo! MAPの
防災モードなど、複数のアプリで
自宅・職場周辺の地図をダウンロード
- Google マップやYahoo! MAPの
- 安否確認サービスの設定と練習
- 災害用伝言板、LINE安否確認機能、
などの使い方を確認 - 家族と一緒に実際に試してみる
- 災害用伝言板、LINE安否確認機能、
- オフライン通信アプリのインストール
- BridgefyやBriarなどをインストール
し、家族や近隣の人にも勧める - 実際に通信テストをしてみる
- BridgefyやBriarなどをインストール
- 大容量モバイルバッテリーの準備
- 20,000mAh以上の容量を目安に準備
- 定期的に充電状態を確認する
- 家族との情報共有計画の策定
- 連絡手段の優先順位、集合場所、
使用するSNSを決める - 実際に訓練してみる
- 連絡手段の優先順位、集合場所、
最後に
災害はいつ起こるかわかりません。
「備えあれば憂いなし」という言葉通り、
日頃からの準備が災害時の行動を
大きく左右します。
本記事で紹介した方法をぜひ試してみて、
あなたとご家族の安全を守るための
「デジタル防災」を整えてください。
また、デジタル機器だけに頼らない従来型の
防災グッズ(ラジオ、地図、懐中電灯など)
も併せて準備しておくことをお忘れなく。
テクノロジーと従来の知恵、
両方を活用することが真の防災力を
高める秘訣です。
皆さんの防災への取り組みが、
少しでも実りあるものになることを
心から願っています。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。