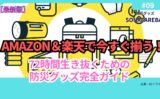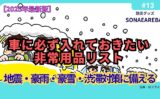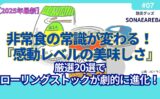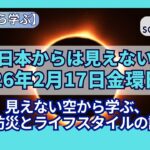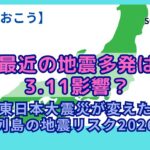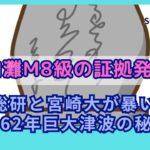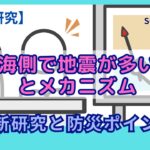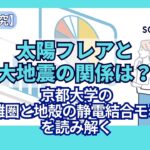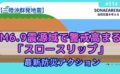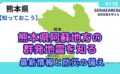本記事は広告が含まれます
こんにちは!SONAEAREBAです。
今回は
「災害時に『情報格差』が生む問題」
というテーマで、自身の体験や知見、
さらには最新の防災DX動向を交えつつ、
この記事をお届けします。
「情報格差」とは何か―災害現場で感じた現実
災害が発生したその瞬間、
ネットやテレビ、ラジオ、SNS…
多様な手段で大量の情報が流れ始めます。
しかし、どんなに便利な時代になっても
「情報」にたどり着けない人や、
逆に情報が多すぎて“間違った情報”を
信じてしまった人が身近にいるのです。
特に若い世代は情報収集をSNSに頼る方
が多くなり、フェイクニュースに触れる
可能性が年配者よりも高くなっています。
SNS・AIが拡げる「情報化」の光と影
2020年代、
災害時の情報源としてSNSや
生成AIの存在感が急拡大しています。
特にZ世代の約半数が「X(旧Twitter)」
をメインの情報源とする一方、
高齢者世代はその7分の1程度と、
世代をまたいだデジタルデバイドが鮮明。
しかも2025年の調査では、
若者の6割近くが
「フェイクニュース被害」
に遭ったというデータもあり、
情報の偏りや誤情報拡散という
新たな課題が切実化しています。
SNSや生成AIを活用した
防災情報が便利になる反面、
信頼度はわずか37.7%。
多くの人が
「リテラシー教育の強化」や
「複数ソースで裏を取る重要性」を
実感しているのが現状です。
「情報弱者」をどう守るか―現場からの提言
情報格差の主な“弱者”は、
やはり高齢者・障がい者・外国人など、
災害情報へのアクセスや言語理解に
困難を抱える方々です。
最近は自治体が「やさしい日本語」や
多言語対応のアプリ、AIスピーカーなど
の導入を進めていますが、
依然として避難指示や経路把握の
難しさが課題となっています。
地域ごとに「防災DX」や
デジタル連携プラットフォームを使った
情報共有の取り組みが生まれており、
デジタル庁も民間連携による新しい
防災システムの整備を急いでいます。
参考リンク:
デジタル庁ニュース
デジタル庁が取り組む「防災DX」
~デジタルの力で、一人ひとりに
的確な災害支援を~
災害時の“正しい情報”とは何か―私の行動ルール
大規模災害が発生した時、
まず「公式の防災アプリ」や
「自治体・政府のSNS」を確認すること。
災害情報には古い情報やデマも多いので、
「複数メディアを横断して状況を比較・
確認」「公式防災機関や信頼できる
ボランティア、専門家からの発信を優先」
という基本ルールを決めています。
また、家族や周囲とも
「情報共有の習慣化」を徹底しています。
最先端の「防災DX」と未来への備え
2025年現在、
デジタル庁が推進する防災DX施策では、
避難所の運営・避難者管理の効率化や
マイナンバーカード連携、防災情報の
官民連携プラットフォーム構築など、
“一人ひとりが取り残されない情報化”
を目指した動きが進んでいます。
特に能登半島地震を機に、
位置情報や健康状態のデジタル把握、
外国人や高齢者にも分かりやすい多言語・
ピクトグラムによる情報伝達など、
“情報格差ゼロ”社会へ
本格的にシフトしつつあります。
結論:“情報で生き残る”時代、備えの新常識
災害時の「情報格差」という課題の
本質は、単なるデジタル機器の
有無だけでなく、
“正しい情報を選び抜き、
確実に伝え合う力”を一人ひとりが
育てていくことにあります。
AIやSNSの進化とともに
リスクも高度化していますが、
「リテラシーの向上」と
「多様な伝達手段の確保」を両輪に、
いつ誰が情報弱者になるか分からない
現実を自覚し続ける、それが本当の
“災害への備え”なのだと感じています。
今後もSONAEAREBAでは、
防災×デジタルをキーワードにした
最新情報や実践ノウハウを
発信していきます!
バックの中に、あるという「安心」を。
通信障害時に役立つワイドFMラジオ付き
「空間にマスクする感覚」
地方自治体避難所開設用パーテーション