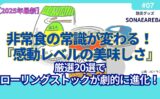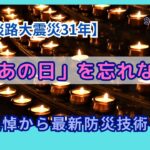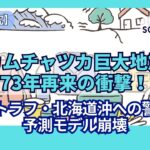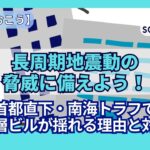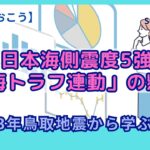この記事は広告を使用しています
こんにちは、SONAEAREBAです。
能登半島地震は
「地下の古いマグマ(硬い高速度体)
がひずみを蓄え、群発地震を経て
最終的に破壊したこと」
が大規模化の引き金だった可能性が
高いと東北大学チームが発表しました。
参考リンク:
東北大学 ホームページ
プレスリリース・研究成果
能登地震、地下の「古マグマ」の破壊が
引き金に 3年間継続した群発地震が
大地震につながった要因を解明
はじめに
2024年1月1日の能登半島地震
(M7.6・最大震度7)について、
東北大学の最新研究が
「古いマグマ(約1500万年前に
固結した硬い岩体)の破壊」
がカギだったと示し、
地震像が一段クリアになりました。
何が“引き金”だったのか
研究チームは半島北部の高密度観測データ
を解析し、震源近傍の地下5〜15kmに
地震波速度が高い硬い岩体(固結マグマ)
が広がることを特定しました。
この岩体は群発地震帯の西側に位置し、
当初は流体の移動を遮る“壁”として
働きましたが、応力が蓄積して
最終的に岩体内部で断層破壊が進み、
大地震に接続したと解釈されています。
群発地震との関係
能登では2020年12月頃から
群発地震が長期化していました。
群発地震は流体の関与で断層が
すべりやすくなる現象として知られます
が、今回は「群発→硬い岩体の
ひずみ蓄積→破壊→本震規模化」
という段階的シナリオが提案されました。
群発地震が大地震に結びつくかの
評価には、こうした地下構造(高速度体)
の把握が鍵だと指摘されています。
どれくらい大きかったのか
固結マグマの破壊を伴うことで、
東西約150kmにわたる断層破壊へと
拡大したとされます。
その結果、M7.6の大地震となり、
半島北西部では最大4m級の隆起や広範な
土砂災害が観測・推定されています。
津波は1.0〜4.4mの範囲と見積もられ、
海岸線の前進も報告されています。
研究の裏付け
成果は米科学誌Science Advancesに
掲載され、固結マグマ(高速度体)の
空間配置と破壊進展の対応関係が
国際査読で示されました。
読売・毎日・共同など国内主要メディアも
相次いで報道し、学術・社会の両面で
注目が集まっています。
参考リンク:
Science Advances WEBサイト
Rupture of solidified ancient magma that
impeded preceding swarm migrations
led to the 2024 Noto earthquake
防災への示唆
今回の知見は、「群発地震」と
「地下の硬い高速度体(古いマグマ)」
の組み合わせがリスク増大のサインに
なり得ることを示します。
トカラ列島や山口県北部など各地での
群発地震評価にも、地下構造の詳細把握が
重要だと研究者は述べています。
私の考え
群発地震の長期化を“時間の猶予”と
見るのではなく、地下に潜む硬い岩体が
どれだけ応力を抱え込んでいるかに意識を
向ける必要があると痛感しました。
「見えない壁」が破れた瞬間、
破壊が一気に広域化する——
その現実を前提に、地域観測網と
構造モデリングの最新情報を注意深く
キャッチしていきたいと思います。
バックの中に、あるという「安心」を。
通信障害時に役立つワイドFMラジオ付き
「空間にマスクする感覚」
地方自治体避難所開設用パーテーション