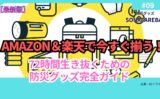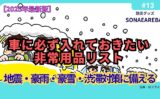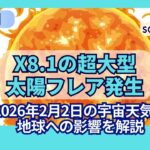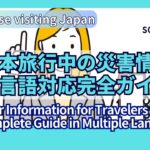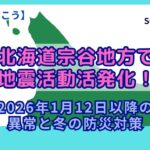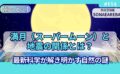本記事は広告が含まれます
こんにちは、SONAEAREBAです。
「都市型災害に備える」をテーマに、
最新動向を踏まえつつ自分自身の目線で、
帰宅困難・エレベーター停止など
大都市ならではのリスクと
対策についてお話しします。
首都圏に広がる災害リスク
大都市には人が密集し、
インフラが高度に発達していますが、
その分「帰宅困難」や
「エレベーター閉じ込め」といった
独特な災害リスクが付きまといます。
最近では南海トラフを含む遠地地震で
沿岸に津波警報が発令され
交通網が麻痺し、大規模イベント時に
地下鉄が止まるなど、首都圏の弱点が
浮き彫りとなっています。
大規模災害が起きた際、現行の国の指針は
「都市圏でマグニチュード7クラスの地震」
を想定し「発生から3日間はむやみに移動
せず、救助活動や消火活動の妨げにならな
いよう職場や安全な場所で待機」
を求めています。
帰宅困難対策の最新動向
内閣府は2025年10月、
遠隔地震や大イベントによる
交通システム停止を想定した
新たな帰宅困難者指針の見直しを
始めました。
鉄道・地下鉄がストップしても
対応できるよう、協力企業との連携や
支援ステーション整備が進んでいます。
東京都などは民間飲食チェーンと協定を
結び、「災害時帰宅支援ステーション」
で水道やトイレ、
道路情報を無償提供しています。
これらの取り組みを認知しておくことで、
避難時の不安を軽減できます。
参考リンク:
都庁総合ホームページ
「災害時における帰宅困難者支援に
関する協定」締結事業者
また、SNSや公式サイト、AI検索エンジン
を活用してリアルタイムで情報を得る力
も、現代人には不可欠と痛感します。
都市部災害では「待機」が基本となる
ため、焦りや不安を極力減らせるよう、
事前の知識・最新情報収集が重要です。
エレベーター停止と閉じ込めの課題
都会生活で忘れがちなのが、
高層マンション・オフィスの
エレベーター閉じ込めリスクです。
東京都では2025年から
「リスタート運転機能」
「自動診断・仮復旧運転機能」
の導入支援を強化しています。
これは停電や地震時に
安全装置が復帰すれば最寄り階でドアを
開放し閉じ込めを防ぎ、機器の破損診断
後、仮復旧させる最新機能です。
参考リンク:
都庁総合ホームページ
エレベーター閉じ込め防止対策等への補助
首都直下地震では最大約1万7400人が
エレベーターに閉じ込められる想定が
出ており、自己防衛策として
「耐震改修済み物件の選択」
「非常時の連絡手段確保」
「飲料水やライトの準備」
が自分にも重要だと強く認識しています。
都市災害の“死角”と新たな対策
最近注目されているのが
「メタンガスによる二次災害」
「都市インフラの老朽化」
「事業継続計画(BCP)」です。
首都圏では地下ガスの挙動や
火災リスクも課題。
加えて、道の陥没や停電による
ライフライン障害など、複合災害への
自助・共助、インフラの更新も
十分な備えが求められます。
この都市で生きる自分の行動指針
実際、災害時は
「なるべく動かない」
ことが命を守る第一歩です。
とはいえ、万が一の自宅への帰宅困難、
エレベーター閉じ込め、都市型火災などに
備え、平時から最新情報を仕入れ、
家族や職場と緊急連絡手段や行動指針を
共有しています。
必要な防災グッズ、モバイルバッテリー、
飲料水は手元に常備。勤務先や最寄り帰宅
支援ステーションもチェック済みです。
災害は予測できませんが、
知識・備え・連携が都市型リスクを
乗り越える力になると強く感じています。
皆さんも都市型災害の最新リスクと
対策を意識して、今日からアクションを
起こしましょう。
バックの中に、あるという「安心」を。
通信障害時に役立つワイドFMラジオ付き
「空間にマスクする感覚」
地方自治体避難所開設用パーテーション