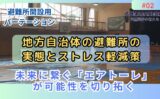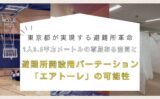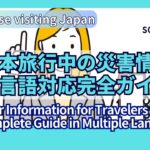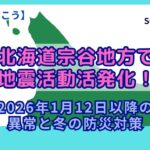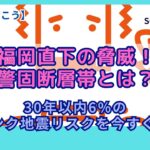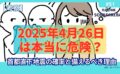本記事はAmazonアソシエイトとして、
商品を紹介して収益を得る可能性があります。
こんにちは!SONAEAREBAです。
東日本大震災から14年が経ちました。
マグニチュード9.0、最大震度7の巨大地震が
東北地方に甚大な被害をもたらした
あの日の記憶は、
今なお私たちの心に深く刻まれています。
そして今、北海道の沖合でも同じ規模の地震が
起きる可能性があることが、最新の調査結果で
明らかになりました。
北海道大学や東北大学などの研究グループが
千島海溝の根室沖で海底の地殻変動を
観測した結果、マグニチュード(M)9クラス
の地震を起こすひずみが蓄積している可能性
が高いことが判明したのです。
この記事では、
千島海溝で進行中の地殻変動とその危険性、
そして私たちがどのように備えるべきか
について詳しく解説していきます。
最新研究が明らかにした千島海溝の危険な兆候
5年間の海底観測で判明した地殻変動
北海道大学と東北大学、
海洋研究開発機構でつくる研究グループは、
2019年から千島海溝の根室沖で海底の
地殻変動を観測してきました。
彼らは釧路管内厚岸町の沖合約100キロと
約150キロの陸側プレート2カ所と
約200キロの海側プレート1カ所で、
深さ2千~5千メートルの海底に観測機器
を設置。
年に1回、海上から観測機器に音波を送り、
返信された音波と衛星利用測位システム
(GPS)などを使って位置を特定し、
機器の移動距離を測定していました。
東北大学災害科学国際研究所の富田史章助教
によると、この観測の結果、「固着域」と
呼ばれる陸側のプレートと海側のプレートが
くっついている部分が年間8センチほど
一緒に沈み込んでいることが判明しました。
これは陸のプレートの先端部分が
海のプレートと一緒になって沈み込み、
将来的に地震を起こすエネルギーを
ため込んでいることを意味しています。
プレート境界のメカニズムと地震ひずみの蓄積
千島海溝では、
海側の太平洋プレートが陸側の
北米プレートの下に沈み込んでいます。
通常、プレート同士の境界面では
滑らかに動くことができれば
大きな地震は発生しません。
しかし、
プレート同士がしっかりと固着していると、
海側プレートの沈み込みとともに
陸側プレートも引きずられ、
その境目にひずみが蓄積されていきます。
今回の観測結果は、
まさにこのひずみが千島海溝で
蓄積されていることを示しており、
政府もこの海溝沿いの巨大地震の発生が
「切迫している可能性が高い」
と評価しています。
過去の巨大地震と今後の発生確率
17世紀の超巨大地震からおよそ400年
千島海溝沿いでは
過去に300年から400年の周期で
マグニチュード9クラスの超巨大地震が
発生してきた可能性が指摘されています。
前回は17世紀に
マグニチュード8.8クラスの地震が
起きたとされており、それから約400年が
経過している現在、同様の地震発生の危険が
高まっていると考えられます。
東北大学災害科学国際研究所の
木戸元之教授は「過去の履歴を見ると
M9クラスが三百何十年に1回は起きている、
そろそろ”満期”なので、次に起こるのは
そのクラスである可能性が割とある」
と述べています。
また、産業技術総合研究所の
岡村行信名誉リサーチャーによると、
17世紀前半の津波が北海道東部の
当時の海岸から3〜4キロ内陸側まで
砂を運んだ痕跡が見つかっており、
これは千島海溝での巨大地震によるもの
であった可能性が高いとしています。
政府の地震発生確率評価
政府の地震調査委員会は、
千島海溝沿いで30年以内に
マグニチュード8.8程度以上の
「超巨大地震」が発生する確率を
7%から40%と評価しています。
また、より詳細な地域別の予測として、
根室沖では
マグニチュード7.8~8.5程度の地震が80%程度、
十勝沖では
マグニチュード8.0~8.6程度の地震が20%程度
の確率で発生する可能性があるとしています。
富田史章助教は
「17世紀の地震から約400年にわたって
現在と同じ速度でひずみが蓄積していた場合
は、将来的にマグニチュード8後半から
マグニチュード9程度の超巨大な地震を
引き起こすエネルギーがすでに蓄えられている
可能性がある」と警告しています。
想定される被害と影響
政府の被害想定シミュレーション
2021年12月に
内閣府の有識者検討会が公表した
被害想定によると、
千島海溝でマグニチュード9.3の
地震が発生した場合、
北海道厚岸町付近で震度7、
えりも町から東側の沿岸部では
震度6強の揺れが想定されています。
参考リンク:
気象庁WEBサイト
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震で
想定される震度や津波の高さ
さらに恐ろしいのは津波の高さで、
えりも町では最大27.9メートル、
根室市や釧路市にも10~20メートル以上の
津波が押し寄せると予測されています。
参考リンク:
日本経済新聞 2021年12月21日
日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震
最悪のシナリオとして、
「冬の深夜」に地震が発生した場合、
津波による死者数は千島海溝の地震で
最大約10万人に上ると推計されています。
北海道という寒冷地での災害ということ
もあり、低体温症で死亡するリスクが
高まる人も最大2万2000人に達すると
試算されています。
経済的被害と生活への影響
経済的な被害については、
千島海溝での地震の場合、
建物やインフラの被災による損害が
約16兆7000億円に上ると推計されています。
また、地震発生1日後の避難者は
約48万7000人、1週間後でも24万人以上、
1カ月後も23万人以上が避難生活を
余儀なくされると想定されています。
ライフラインにも深刻な影響が
出ると予測されており、
地震発生1週間後の時点で
上水道が利用できない人は
約19万6000人、
下水道の利用が困難となるのは
約72万9000人、
停電は約8万4000軒
に及ぶとされています。
道路や鉄道などの交通網も寸断される
恐れがあります。
千島海溝地震への備え
津波からの早期避難の重要性
政府の被害想定によれば、
津波避難ビル・タワーなどの整備が進み、
地震発生後の早期避難が実現できれば
死者は約8割減らせると見込まれています。
特に北海道の沿岸部では、
地震発生から20分前後という短い時間で
津波が到達する地域もあるため、
揺れを感じたらすぐに高台や避難施設に
移動することが命を守る鍵となります。
参考リンク:
読売新聞オンライン 2025/03/12
津波避難タワー着々整備進む…釧路地方
「多重防御」位置づけ日本・千島海溝地震備え
寒冷地特有の対策
北海道や東北地方といった
積雪寒冷地では、
通常の地震・津波対策に加えて、
低体温症対策も重要です。
避難場所での乾いた衣服、防寒着、
暖房器具等の備蓄の充実や、
屋内の避難所等への二次避難路の確保など
が求められます。
また、
個人レベルでも非常用持ち出し袋に
エマージェンシーシート、防寒具や
使い捨てカイロなどを加えておくことが
推奨されます。
自治体と地域コミュニティの取り組み
富田史章助教は、
「いつ地震が起きても対応できるように
被害の備えを充実させることが重要」
と指摘しています。
自治体レベルでは、
ハザードマップの整備や避難訓練の実施、
避難経路や避難施設の見直しなどが
進められています。
また、
地域コミュニティでの防災意識の向上や
要支援者への対応計画の策定も
重要な取り組みとなります。
後発の巨大地震への注意を促す情報発信
先発地震後の警戒の必要性
日本海溝・千島海溝沿いでは、
比較的小さな地震の後に
巨大地震が発生した事例があります。
過去には、
マグニチュード7.3の先発地震の2日後に
マグニチュード9.0の2011年東日本大震災が、
マグニチュード7.0の先発地震の18時間後に
マグニチュード8.5の1963年の択捉島南東沖
の地震が発生しています。
これらの事例を踏まえ、
内閣府は日本海溝・千島海溝沿いの
巨大地震の想定震源域及び想定震源域に
影響を与える外側のエリアで
マグニチュード7.0以上の地震が発生した際に、
後発の巨大地震に備えた注意を促す情報発信を
行う方針を示しています。
参考リンク:
気象庁WEBサイト
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」
の発表基準と情報発表の流れ
日常生活を維持しながらの備え
後発地震への警戒情報が発信された場合、
北海道から千葉県までの広範囲が
対象となりますが、防災対応としては
日常的な生活及び経済活動を継続しつつ、
過度な対応とならない範囲で一週間、
日頃からの地震への備えの
再確認を行うことが推奨されています。
具体的には、
非常用持ち出し袋の点検や家族との
連絡方法の確認、家具の固定状況のチェック
などを行うとよいでしょう。
科学的観測の継続と精度向上の取り組み
海底地殻変動観測の重要性
千島海溝周辺での地震発生メカニズムを
さらに理解するためには、
海底地殻変動観測の継続と精度向上が
不可欠です。
特に十勝・根室沖では、
マグニチュード9クラスの超巨大地震の
発生が危惧されていますが、
こうした超巨大地震の発生リスクが
明らかになってきたのが近年であるため、
十勝・根室沖の超巨大地震を起こしうる
エネルギーの蓄積の様子を海底地殻変動観測
などの直接的な手段で調査することは、
2019年以降に開始された
比較的新しい取り組みです。
今後も東北大学や北海道大学、
海洋研究開発機構などの研究機関による
継続的な観測が行われることで、
より精度の高い地震予測が可能になると
期待されています。
参考リンク:
JAMSTECウェブサイト
https://www.jamstec.go.jp/
新技術による観測手法の発展
東北大学などの研究グループは、
ウェーブグライダーと呼ばれる
無人で動く船などを使って、
海底に沈めた装置が発する音波をとらえる
新たな観測手法も導入しています。
こうした最新技術を駆使することで、
より詳細なプレート境界の状態把握が進み、
巨大地震の予測精度向上につながる
可能性があります。
まとめ:備えあれば憂いなし
千島海溝での巨大地震の発生は
避けられない自然現象です。
しかし、
その被害を最小限に抑えるための備えは
私たち一人ひとりにできることです。
最新の科学的知見によれば、
北海道沖の千島海溝では400年ぶりの
マグニチュード9クラスの超巨大地震が
発生する可能性が高まっています。
この情報を正しく理解し、
適切な対策を講じることが重要です。
「備えあれば憂いなし」
ということわざがあるように、
日頃からの防災意識と具体的な準備が、
いざというときの被害を大きく軽減する
ことにつながります。
自分自身や家族の命を守るため、
そして地域社会の一員として、
今一度防災対策を見直してみては
いかがでしょうか。
また、
この記事を読んで不安になった方も
いらっしゃるかもしれませんが、
科学的な知見に基づいた
冷静な対応が大切です。
地震そのものを防ぐことはできなくても、
その被害を最小限に抑えることは可能です。
日常生活を送りながらも、
「もしも」のときのための心構えと
準備を整えておきましょう。
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
SONAEAREBAでした。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。