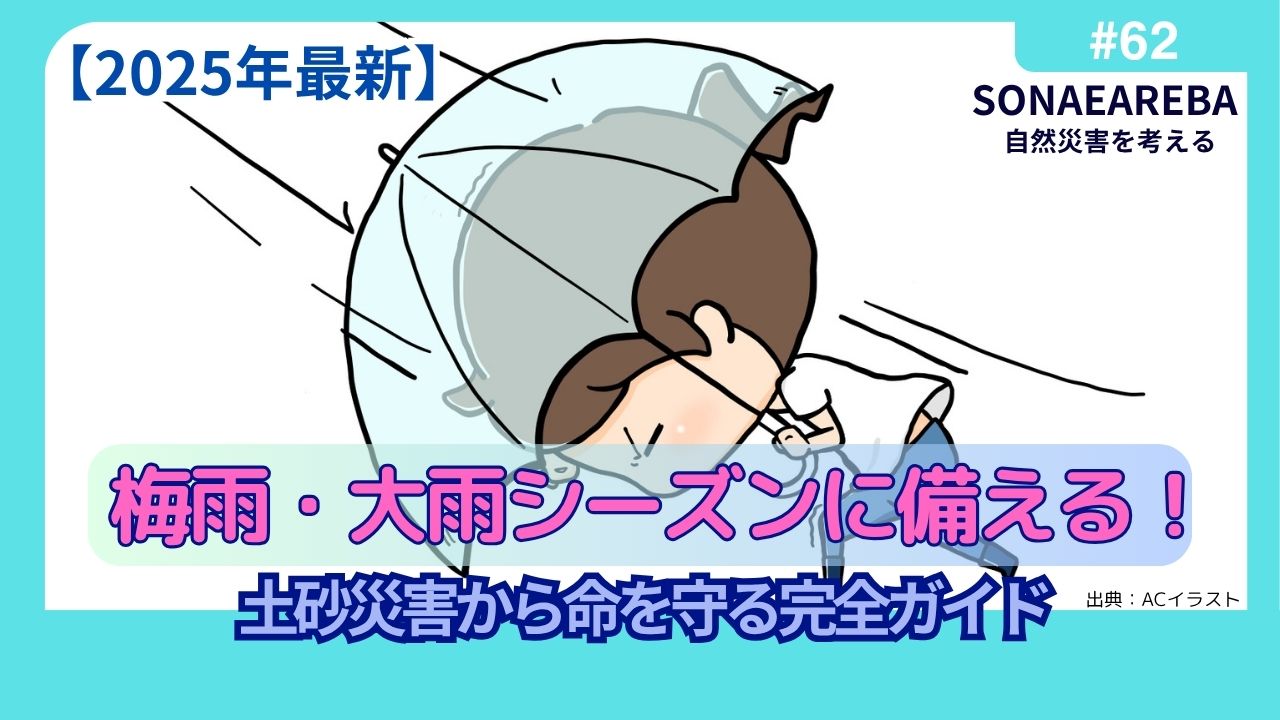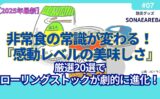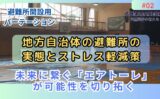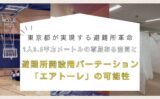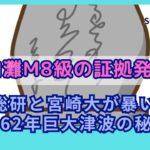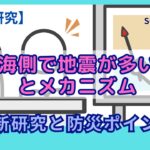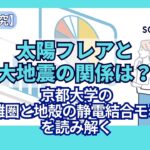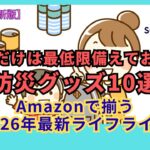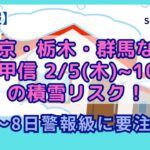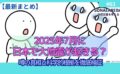この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
日本全国で年間約1,500件もの
土砂災害が発生しており、
近年は気候変動の影響で
大雨の頻度が増加傾向にあります。
梅雨入り間近の今こそ、
土砂災害への備えを見直す
絶好のタイミングです。
本記事では、
最新の気象情報や防災対策を網羅し、
あなたとご家族の命を守るための
実践的な情報をお届けします。
2025年の梅雨と大雨災害の最新動向
2025年の梅雨入り・大雨傾向【最新情報】
2025年の梅雨入りは、
沖縄・奄美が5月中旬、
九州南部は5月下旬、
九州北部から関東甲信は6月上旬、
北陸や東北は6月中旬と、
全国的に「平年並み」の時期になる
見込みです。
昨年(2024年)は記録的に遅い梅雨入り
でしたが、今年は例年通りかやや早めの
スタートとなりそうです。
特に今年は「陽性梅雨」の傾向が
強まる予想で、しとしと雨よりも、
短時間に激しく降るゲリラ豪雨や集中豪雨
が増える見込みです。
太平洋高気圧の張り出しが強く、
南からの湿った空気が流れ込みやすいため、
梅雨前線の活動が活発化し、
各地で大雨のリスクが高まります。
5月16日からは梅雨のはしりとして、
九州から関東にかけて大雨が予想されており、
17日・18日を中心に土砂災害や河川の増水に
警戒が必要です。
気候変動と大雨の関係
気象庁の調査によると、
1時間降水量80mm以上、
3時間降水量150mm以上、
日降水量300mm以上など、
強度の強い雨は1980年頃と比較して
おおむね2倍程度に頻度が増加している
ことがわかっています。
参考リンク:
気象台ホームページ
「大雨や猛暑日などのこれまでの変化」
なぜこのような変化が
起きているのでしょうか?
その理由として、気候変動による
気温上昇が挙げられます。
気温や海水温が上昇すると、
大気中に含まれる水蒸気量が増加します。
温かい海水からはより多くの水分が蒸発し、
温かい空気はより多くの水蒸気を含むこと
ができるためです。
この大気中の水蒸気は雲となり、
やがて雨となるため降水量が増加するのです。
具体的な事例として、
「平成30年7月豪雨」(西日本豪雨)
については、地球温暖化の影響によって
発生確率が約3.3倍になったことが研究により
明らかになっています。
このように、個々の大雨事象に対しても
気候変動の影響が科学的に証明されるように
なってきました。
土砂災害の基礎知識 – なぜ日本は危険なのか
日本の地形と気象条件がもたらす危険性
傾斜が急な山が多い日本は、
台風や大雨等が引き金となって、
がけ崩れや土石流、地すべりなどによる
土砂災害が発生しやすい国土環境にあります。
土砂災害は一瞬にして尊い命や家屋など
の貴重な財産を奪うなど、
甚大な被害をもたらすことがあります。
参考リンク:
政府広報オンライン
土砂災害から身を守る3つのポイントあなたも
危険な場所にお住まいかもしれません!
土砂災害の発生件数を見ると、
平成26年(2014年)から令和5年(2023年)
までの直近10年では平均して1年間におよそ
1,499件もの土砂災害が発生しています。
これは平成16年(2004年)から
平成25年(2013年)までの
10年平均のおよそ1,184件に比べ、
約1.25倍に増加しています。
さらに、
土砂災害が発生するおそれのある区域は、
日本全国で約69万区域にのぼると
推計されています。
(令和5年(2023年)末時点の推計値)
自分の住んでいる地域が安全だと
思っていても、実は危険区域に
指定されているかもしれません。
土砂災害の種類と特徴
土砂災害には主に3種類あります:
- がけ崩れ:
雨や地震の影響で、
急な斜面が突然崩れ落ちる現象。
前触れが少なく、突発的に発生するため
非常に危険です。 - 土石流:
大雨や長雨によって、
山の斜面や谷などにたまった土砂が、
水と一緒になって一気に流れ下る現象。
流れ下る速度が非常に速く、
大きな破壊力を持ちます。 - 地すべり:
斜面の一部あるいは全部が、
ゆっくりと下方に移動する現象。
徐々に進行することが多く、
亀裂や段差などの前兆現象が見られます。
これらの災害は突然発生することが多く、
短時間でまとまって降る強い雨による
水害には、数分~数十分で危険な状態になる
場合があることを理解しておく必要が
あります。
参考リンク:
土砂災害防止広報センター ホームページ
「土砂災害を防ぐ、備える、学ぶ、伝える」
土砂災害から身を守る3つのポイント
国土交通省や地方自治体では、
土砂災害による被害を防ぐため、
砂防えん堤などの施設整備や警戒避難体制の
整備などの対策を実施していますが、
これらと併せて私たち一人ひとりが土砂災害に
対して日頃から備えておくことが重要です。
ここでは、
土砂災害から身を守るために最低限
知っておくべき3つのポイントを紹介します。
1. 住んでいる場所の危険度を知る
まず最初に行うべきことは、
自分の住んでいる場所が「土砂災害警戒区域」
かどうかを確認することです。
土砂災害のおそれのある地区は
「土砂災害警戒区域」等とされています。
普段から自分の家がこれらの土砂災害の
おそれのある地区にあるかどうか、
市区町村のホームページや国土交通省の
「ハザードマップポータルサイト」などで
確認しましょう。
ハザードマップは、
大雨、台風、地震などの災害が発生した場合、
浸水や土砂災害などが発生する危険区域や
避難場所、避難経路などを
地図上にまとめたものです。
どの地域にどんな危険箇所があるのか、
付近の避難場所や避難経路を確認して
おくことで、万が一災害が発生した場合に
迅速に避難することができます。
ハザードマップの確認方法:
- 市区町村の防災担当窓口や
ホームページで確認する - 「ハザードマップポータルサイト」
(https://disaportal.gsi.go.jp/)
にアクセスする - スマートフォンでハザードマップを
確認できるアプリをインストールする
参考リンク:
東京都防災ホームページ
「東京都防災アプリ」
ただし、
土砂災害警戒区域等でない区域でも、
土砂災害が発生する場合があります。
付近に「がけ地」や「小さな沢」などが
あれば注意が必要です。
2. 気象情報と警戒レベルを理解する
雨が降り出したら「土砂災害警戒情報」
に注意することが重要です。
土砂災害警戒情報は、
大雨による土砂災害発生の危険度が
高まったときに、市町村長が避難指示を
発令する際の判断や住民の自主避難の参考
となるよう、都道府県と気象庁が共同で
発表する防災情報です。
警戒レベルを正しく理解することも大切です。
災害時の警戒レベルは
以下のようになっています:
- 警戒レベル1:災害への心構えを高める
- 警戒レベル2:避難行動の確認
- 警戒レベル3:高齢者等は避難
- 警戒レベル4:全員避難
- 警戒レベル5:命を守る最善の行動
特に重要なのが「土砂災害警戒情報」で、
これは警戒レベル4相当の情報です。
この情報が発表されたら、
避難指示が発令されていなくても、
地域内の方々に声をかけあい、早めに近くの
避難場所など、安全な場所に避難しましょう。
参考リンク:
東京消防庁「台風・大雨に備えよう」
3. 早めの避難行動を心がける
警戒レベル4が発令されたら、
全員避難が原則です。
特に、お年寄りや障害のある人など
避難に時間がかかる人は、移動時間を
考えて早めに避難させることが大事です。
避難のタイミングについて、
以下のポイントを覚えておきましょう:
- 夜中に大雨が予想される場合には、
暗くなる前に避難する - 強い雨や長雨のときは、防災行政無線や
広報車による呼びかけに注意する - スマートフォンなどの緊急速報メールや
テレビ・ラジオの緊急放送にも注意する - 事前に複数の避難経路を確認しておく
(災害時には通常の経路が使えなくなる
ことがある)
大雨による災害は土砂災害や河川の氾濫など、
避難時にも危険があるため事前に避難経路を
複数用意しておくことをお勧めします。
また、安全に避難できるか判断するために
河川の水位を確認する河川アプリの利用も
有効です。
参考リンク:
気象庁ホームページ「キキクル」
大雨による災害発生危険度を
リアルタイムで確認できます。
実際の災害事例から学ぶ – 近年の被害状況
梅雨の大雨による最近の災害
近年、日本では梅雨期間中の集中豪雨による
甚大な被害が頻発しています。
いくつかの代表的な事例を見てみましょう:
【2021年7月】静岡県熱海市の土石流災害
令和3年7月3日10時30分頃、
静岡県熱海市伊豆山の逢初川で土石流が
発生しました。
この災害では、死者・行方不明者27名、
家屋の被害128棟(135世帯)が発生し、
国道135号の通行止めや東海道新幹線・
JR東海道線の一時運休等、
大きな社会的影響が生じました。
【2020年7月】令和2年7月豪雨
令和2年7月4日から7日にかけての
集中豪雨では、九州地方で記録的な大雨
となりました。
鹿児島県鹿屋市では
1時間の降水量が109.5ミリにも達し、
気象庁は大雨特別警報を発令しました。
九州以外にも西日本や東日本で大雨が発生し、
球磨川をはじめとした多くの大河川で氾濫が
相次ぎ、土砂災害や浸水など多くの
人的・物的被害が発生しました。
これらの事例からわかるように、
近年の大雨災害は予測を超える規模で
発生しています。
気候変動の進行により、
今後もこうした極端な降水現象が増加する
可能性があります。
私たちはこれらの教訓を活かし、
事前の備えを強化する必要があります。
SONAEAREBAが教える非常持ち出し袋の正しい準備
本当に必要な防災グッズリスト
非常用持ち出し袋を準備する際には、
災害時にすぐ避難できるように、
中身は本当に必要最低限のものだけを
入れることが大切です。
以下は、推奨する基本アイテムです:
- 飲料水:
最低限1日分。
あまり重くなり過ぎないように。 - 食料・非常食:
こちらも1日分。最低限の食料は持ち出し。
アレルギーがある方は念のために多めに。 - モバイルバッテリー:
安否確認や救助要請のためにスマートフォ
ンの使用頻度が高くなります。充電のため
のモバイルバッテリーは必需品です。 - 防寒具・アルミブランケット:
夜は気温が下がるので、
防寒グッズは必須。毛布はかさばるため、
手のひらサイズに折りたためる
アルミ製のブランケットが重宝します。 - ラジオ:
必要な情報を得たいときに、
携帯ラジオが役立ちます。
ラジオを選ぶ際にはワイドFM放送が聞ける
もの、電源が切れてしまったときに備えて
手回し式の充電機能がついているものが
おすすめです。 - 救急セット:
絆創膏や消毒液に加え、止血や固定などに
使える包帯や三角巾など。また、災害時に
は砂ぼこりが舞いやすいため、マスクも実用的です。 - 自分自身の必需品:
コンタクトレンズ、メガネや補聴器、
持病の薬など日常生活で必要なもの
非常持ち出し袋の定期チェックの重要性
非常持ち出し袋を一度準備しただけでは
十分ではありません。
定期的に中身をチェックし、食料品や医薬品の
期限が切れていないか、電池類が使える状態か
などを確認することが重要です。
特に注意すべきポイント:
- 食料品と飲料水の消費期限を確認
(最低でも年に2回) - 季節に応じた衣類の入れ替え
- 電池やモバイルバッテリーの
充電状態の確認 - 家族構成や健康状態の変化に合わせた
中身の見直
土砂災害対策の最新技術と公共の取り組み
ハード対策とソフト対策
土砂災害から人々を守るため、国や地方自治体
ではさまざまな対策が実施されています。
これらは大きく「ハード対策」と
「ソフト対策」に分けられます。
ハード対策とは、
物理的な設備や構造物を建設することで
災害を防止する取り組みです。
例えば:
- 砂防えん堤:
土石流が流れてきたときに、
砂防堰堤のポケットに土砂をためこみ、
土石流を止める施設です。 - がけ崩れ防止工事:
がけをくずれにくくする工事と、
くずれてきた土砂を安全に受け止めるため
の施設を作る工事があります。 - 法枠工:
がけ崩れを防ぐための格子状の構造物を
設置する工法です。
これらの施設は、私たちの命を守る
重要な社会資本ですが、すべての危険箇所に
対策が完了しているわけではありません。
一方、ソフト対策とは、
警戒・避難体制の整備など、
情報提供や啓発活動を通じて災害に備える
取り組みです。
例えば:
- 土砂災害警戒区域等の指定と周知
- 土砂災害ハザードマップの作成・配布
- 早期避難のための情報提供システムの整備
- 防災教育や避難訓練の実施
これらのハード対策とソフト対策を
組み合わせることで、
より効果的な防災・減災が可能になります。
活用すべき情報源と警報システム
土砂災害から身を守るためには、
正確な情報をタイムリーに入手することが
重要です。以下のような情報源を
活用しましょう:
- 気象庁ホームページと気象警報:
大雨特別警報、土砂災害警戒情報などの
最新情報を確認できます。 - 自治体の防災情報:
市区町村が提供する防災メールやSNS、
防災アプリなどを活用しましょう。
例えば、東京都では「東京都防災アプリ」
を提供しています。 - ハザードマップポータルサイト:
国土交通省が運営するサイトで、全国の
災害リスク情報を一元的に確認できます。 - テレビ・ラジオの緊急放送:
災害時には停電の可能性も考慮し、
手回し充電式のラジオを用意しておくこと
をお勧めします。 - キキクル(危険度分布):
気象庁が提供する1kmから5kmのメッシュ
単位の危険度が確認できるサービスです。
これらの情報源を日頃から確認する
習慣をつけ、実際の災害時に落ち着いて
行動できるようにしましょう。
梅雨時の住まいの安全対策
事前にチェックすべき家の周辺ポイント
梅雨シーズンが本格化する前に、
自宅の周辺環境を確認し、必要な対策を
講じておくことが重要です。
以下のポイントをチェックしましょう:
- 側溝や排水口の清掃:
つまりがあると水はけが悪くなり、
浸水のリスクが高まります。 - 窓や雨戸の点検:
カギをしっかりとかけ、必要に応じて
補強します。 - 飛散物の固定:
風で飛ばされそうな物は固定するか、
家の中へ格納します。 - 屋根や壁のひび割れチェック:
雨漏りの原因となるひび割れがないか
確認しましょう。 - 樹木の状態確認:
大きな枝が折れて家を
直撃する可能性がある場合は、
事前に剪定を検討しましょう。 - 近隣の斜面や崖の状態確認:
亀裂や異常な湧水がないか注意深く
観察します。
これらの点検・対策を早めに実施することで、
災害時のリスクを大幅に減らすことが
できます。
室内での警戒・避難準備のポイント
大雨や土砂災害の危険が高まった場合、
室内でも警戒を怠らず、いつでも避難できる
準備をしておくことが大切です:
- 情報収集手段の確保:
テレビ、ラジオ、スマートフォンなどの
情報源を確保し、常に最新情報を
入手できる状態を維持します。 - 水の確保:
断水に備えて飲料水を確保するほか、
浴槽に水を張るなどして生活用水を
確保します。 - 非常用グッズの準備と確認:
避難時にすぐ持ち出せるよう、
非常用グッズをまとめ、
すぐに取り出せる場所に保管します。 - 家族との連絡方法の確認:
災害時の連絡方法や集合場所を家族で
事前に話し合い、確認しておきます。 - 避難指示が出たらすぐ避難:
「様子を見よう」と避難を遅らせることは
命取りになります。
特に夜間の避難は危険なので、明るいうち
に避難することを心がけましょう。 - 垂直避難の検討:
周囲の状況によっては、
建物の2階以上に避難(垂直避難)が
有効な場合もあります。
ただし、土砂災害の危険がある場合は
早めに安全な場所へ避難すること、
斜面から離れた逆側に避難することが基本です。
まとめ:今日からできる防災・減災アクション
明日からできる3つの備え
本記事でご紹介した内容を踏まえ、
明日から実践できる具体的なアクションを
まとめます:
- ハザードマップの確認:
自宅や職場、よく行く場所が土砂災害警戒
区域に含まれていないか確認し、
避難場所と避難経路を把握しましょう。 - 防災情報アプリのインストール:
お住まいの自治体の防災アプリや
気象情報アプリをインストールし、
設定を完了させておきましょう。 - 非常持ち出し袋の準備・点検:
本記事で紹介したリストを参考に、
必要なものを揃え、定期的に中身を
確認する習慣をつけましょう。
これらのアクションは、
いずれも時間をかけずに今すぐ始められる
ものばかりです。
「災害は明日起こるかもしれない」という
意識を持って、早速取り組んでみてください。
家族や地域で共有すべき防災知識
防災・減災の効果を高めるためには、
個人だけでなく家族や地域全体で防災知識を
共有することが重要です:
- 家族会議の開催:
避難場所、連絡方法、
家族それぞれの役割などを話し合い、
定期的に確認しましょう。 - ご近所との関係づくり:
日頃から挨拶を交わし、災害時に助け合え
る関係を構築しておきましょう。
特にお年寄りや障害のある方など、
避難に支援が必要な方の把握も大切です。 - 地域の防災訓練への参加:
自治体や町内会が実施する防災訓練に
積極的に参加し、実践的な避難行動を
体験しておきましょう。 - 学校や職場での防災計画の確認:
家族が日中別々の場所にいる場合の
対応や集合場所についても
話し合っておきましょう。
梅雨・大雨シーズンは毎年やってきます。
「備えあれば憂いなし」のことわざ通り、
事前の備えが命を守る鍵となります。
本記事でご紹介した知識や対策を参考に、
ぜひ今日からでも防災・減災のための行動を
始めてみてください。
自然災害は避けられないものですが、
その被害を最小限に抑えることは
私たち一人ひとりの心構えと行動次第です。
SONAEAREBAは今後も最新の防災情報を
お届けしていきます。
皆様の安全な毎日をお祈りしています。
💡この記事は2025年5月14日時点の
情報に基づいて作成されています。
最新の情報は各公的機関のホームページ等で
ご確認ください。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。