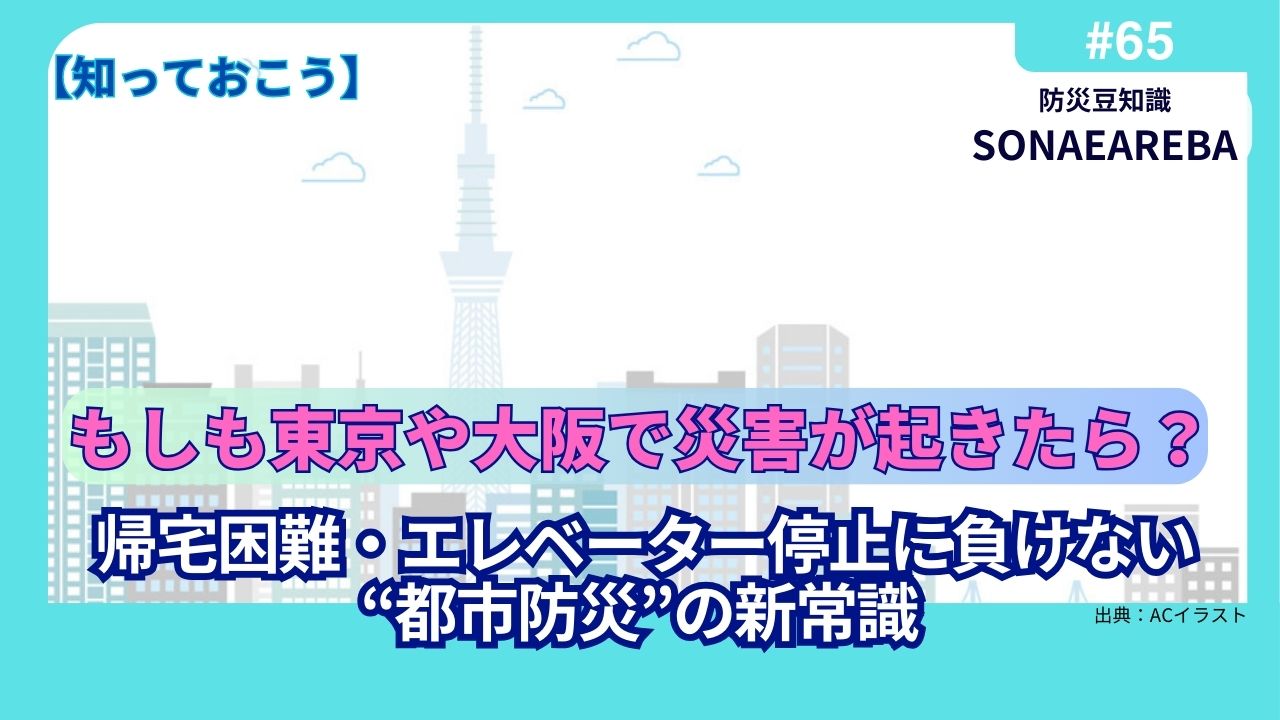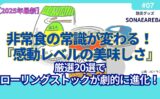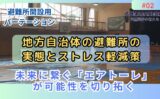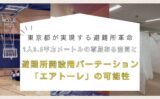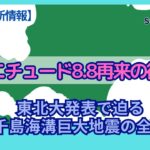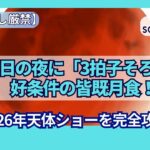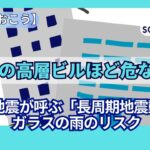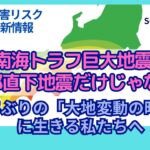この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
近年増加する都市型災害に対し、
特に大都市における固有のリスクと
効果的な対策を解説します。
災害発生時に帰宅困難者となるリスク
やエレベーター停止による
高層ビルでの孤立など、
都市特有の問題に焦点を当て、
オフィスでの備蓄方法、
徒歩帰宅ルートの事前確認、
代替交通手段の把握、
そして
災害時の効果的な情報収集方法まで、
実践的な対策をまとめました。
都市型災害の特徴と増加傾向

災害大国日本では
毎年のように自然災害が発生していますが、
特に都市部における災害は
独特のリスクと対策が必要です。
都市型災害とは何か
都市型災害とは、
森林や田畑がなくコンクリートに覆われた
都市部で発生する災害のことです。
従来の自然災害とは異なる特徴を持ち、
独自の対策が求められます。
都市型災害の代表的な例として、
2000年9月に東海地方で発生した
記録的な大雨による災害があります。
愛知県名古屋市では死者4人、
浸水家屋31,670棟という
甚大な被害が出ました。
この災害は「東海豪雨」と呼ばれ、
名古屋市内の約40%の地域が浸水する
という大規模な都市型水害となりました。
また、1982年7月23日に
長崎県で発生した集中豪雨では、
死者・行方不明者299人、
被害額3,153億円に及ぶ
大きな災害となりました。
この「7.23長崎大水害」でも
都市部の河川氾濫や道路冠水による交通障害、
ライフライン破壊などが
深刻な問題となりました。
都市型災害の増加傾向
近年、都市型災害は増加傾向にあります。
気象庁の統計によると、1時間降水量
50mm以上の「激しい雨」の発生回数は、
1976~1985年の平均が年間約226回だった
のに対し、2012~2021年の平均は
年間約327回と、約1.4倍に増加しています。
さらに、
スイスの再保険会社スイス・リーが発表した
2013年の世界616都市を対象とした
「自然災害で最も危険な都市ランキング」
「東京・横浜」が1位、「大阪・神戸」が4位、
名古屋が6位となっています。
特に「東京・横浜」では、2900万人が
巨大地震の影響を受ける可能性が高い
とされています。
自然災害で最も危険な都市ランキング
トップ10は以下の通りです。
1 東京・横浜(日本)
2 マニラ(フィリピン)
3 珠江デルタ(中国)
4 大阪・神戸(日本)
5 ジャカルタ(インドネシア)
6 名古屋(日本)
7 コルカタ(インド)
8 上海(中国)
9 ロサンゼルス(アメリカ)
10 テヘラン(イラン)
参考リンク:
ロイター WEBサイト
自然災害が危険な都市ランキング、
東京・横浜が世界1位=調査
大都市特有の6つの防災リスク
大都市には、
災害に関して次の6つの
特有リスクが存在します。
これらを理解することで、より効果的な
防災対策を立てることができます。
人口集中と施設の高密高層化
都市部では人口が集中し、限られた土地を
有効活用するために建物が高層化しています。
東日本大震災では、新宿の超高層ビルが
長周期地震動により最長13分間、
最大108センチメートルも揺れ、
「隣のビルとぶつかりそうになって怖かった」
という声もありました。
高層ビルやタワーマンションでは、
地震によるエレベーターの故障リスクも
高まります。
電気・水道・ガスなどのインフラが
ストップすれば、高層階は「空の孤島」と
化す恐れがあります。
新旧が混在した街
都市は時間をかけて発展するため、
建物の建設時期はさまざまです。
阪神淡路大震災では死者の8割が
建物の倒壊による圧死または窒息死でしたが、
倒壊した建物の約7割は
昭和56年の新耐震基準以前の建物でした。
古い木造住宅密集地では
大規模火災のリスクも高まります。
首都直下型地震のシミュレーションでは、
火災旋風の発生も予想されています。
地盤沈下や軟弱地盤
東京や大阪などの大都市には
広大な埋め立て地があります。
これらの地域は地盤が弱く、
地震時に液状化現象が発生するリスクが
高まります。
東日本大震災では東京、千葉、埼玉の
各地で液状化が発生し、家が傾いたり
半壊したりする被害がありました。
マンホールが隆起したケースもあります。
4. 複雑な地下空間
都市の地下空間は複雑に入り組んでいます。
東京の地下鉄は新しい路線ほど深く作られる
傾向があり、大江戸線の一部の駅は
地下49メートルに位置しています。
地下で最も懸念されるのは、
地震による破壊で外に出られなくなることや、
水害による冠水・浸水です。
大量消費するエネルギー
人口の多い都市では
エネルギー消費量も膨大です。
ガソリンスタンドや石油コンビナートなど、
平常時には安全に管理されているエネルギー
関連施設が、災害時には火災や爆発の原因
となる可能性があります。
移動の多さと人間関係の希薄化
都会では住居と職場が離れていることが
一般的です。災害時には多くの人々が
一斉に帰宅困難者となり、
大混乱が生じる可能性があります。
東京都の想定では、
首都直下地震発生時に最大452万人余の
帰宅困難者が発生し、そのうち9割が
区部に集中するとされています。
帰宅困難者問題の実態と対策

帰宅困難者とは
帰宅困難者とは、
災害により交通機関が停止し、
徒歩で帰宅することが困難な人々を指します。
内閣府の統計によると、
徒歩距離10km以内なら
全員「帰宅可能」ですが、
10kmを超えると「帰宅困難者」が現れ始め、
20kmを超えると全員が帰宅困難となると
されています。
東日本大震災での教訓
2011年の東日本大震災では、
首都圏で大量の帰宅困難者が発生し、
道路や駅周辺が人であふれ、
大きな混乱が生じました。
この教訓から、
「むやみに移動せず、一斉帰宅を抑制する」
という基本方針が確立されました。
帰宅困難者対策ガイドライン
内閣府は2015年に
「大規模地震の発生に伴う
帰宅困難者等対策のガイドライン」を策定し、
2024年7月に改定しました。
このガイドラインでは、
以下のような対策が示されています:
- 一斉帰宅の抑制:
災害発生時は、むやみに移動を開始せず、
職場や学校などその場にとどまることが
原則です。 - 一時滞在施設の確保:
行き場のない帰宅困難者を
受け入れるための施設を確保します。
東京都では約44万人分(67%)の
一時滞在施設を確保済みですが、まだ
約22万人分(33%)が不足しています。 - 帰宅困難者への情報提供:
正確な災害情報や交通情報を提供すること
が重要です。 - 徒歩帰宅者への支援:
水や休憩の場などを提供する
「災害時帰宅支援ステーション」
の指定と、帰宅支援対象道路の整備が
進められています。 - 時間帯別行動パターンのルール化:
災害発生から3日目までは救命救助活動、
消火活動等を中心に対応し、
4日目以降に帰宅困難者等の帰宅支援の
体制へ移行することを基本としています。
参考リンク:
内閣府 防災情報のページ
「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」
東京都総務局総合防災部防災管理課
東京都帰宅困難者ハンドブック
エレベーター停止のリスクと対応

地震時のエレベーターの挙動
地震が発生した場合、エレベーターは
どのように動作するのでしょうか?
地震時管制運転機能が付いている
エレベーターであれば、一定の揺れを感知する
と自動的に最寄階で停止し、扉が開きます。
地震時管制運転機能がない場合は、
揺れを感じたら乗客自身が近い階から
呼びボタンを全部押して、停止した階で
降りる必要があります。
地震感知器の作動基準
エレベーターの地震感知器は震度ではなく
加速度(ガル値)で設定されており、
揺れ方や建物の構造、高さ、地盤などの
影響を受けますが、概ね震度4から震度5弱
で主要動(S波)を感知して停止します。
エレベーター内に閉じ込められた場合の対処法
地震でエレベーターが停止して
閉じ込められた場合は、
まずエレベーター内に設置された
非常用インターホンや携帯電話で
外部と連絡を取りましょう。
エレベーター内には非常用飲料水や食料、
トイレキットなどが入った非常用備品ボックス
が備えられている場合があります。
無理にドアを開けたり天井からの脱出を
試みたりすることは危険ですので、
絶対にやめましょう。
エレベーター安全対策
エレベーターの安全性を高めるための
主な対策は以下の3つです:
- 地震時管制運転装置の導入:
2009年9月の建築基準法改正以降、
新設エレベーターへの設置が
義務化されました。 - 非常用備品ボックスの設置:
閉じ込められた際の乗客の安全と
快適性を確保します。 - 定期的な保守点検:
年1回の検査と定期的な保守点検が
法律で義務付けられています。
オフィスでの防災備蓄と備え

必要な備蓄品リスト
災害時、従業員を社内で保護するためには
最低でも3日分の防災備蓄品が必要です。
主な備蓄品は以下の通りです:
- 水:
ペットボトル入り飲料水
1人当たり1日3リットル、計9リットル - 主食:
1人当たり1日3食、計9食 - 毛布または保温シート: 1人1枚
- 簡易トイレ
- 衛生用品
- 懐中電灯やラジオ
適切な保管場所と保管方法
防災備蓄品の保管場所として適しているのは
以下のような場所です:
- オフィス内のキャビネット
- 従業員の個別デスク
- 倉庫や空き部屋
- 休憩室や会議室の一角
保管時の注意点は以下の6つです:
- 分散して配置する:
1か所にまとめず複数か所に分散して
保管しましょう。 - すぐに取り出せるようにする:
保管場所を従業員全員と
共有しておきましょう。 - 階段で搬出可能な場所へ:
災害時はエレベーターが使用できない
可能性があります。 - 消防法に注意する:
廊下や階段の前に物を置かない、
火災報知器やスプリンクラーに干渉しない
などの点に注意しましょう。 - 転倒防止・落下防止:
棚をロープで固定する、滑り止めシートを
敷くなどの対策を行いましょう。 - 浸水や湿気のリスクに配慮:
地面に直接段ボールを置かない、
乾燥剤を使用するなどの工夫を
しましょう。
徒歩帰宅ルートの確認方法

安全なルート選定のポイント
徒歩帰宅ルートを策定する際は、
基本的に幹線道路沿いを選択しましょう。
幹線道路は道幅が広く歩きやすいだけでなく、
以下のメリットがあります:
- 復旧が早く、火災のリスクが比較的低い
- 商業施設や公共施設が多く、災害時
帰宅支援ステーションを利用しやすい - 道路標識や周辺案内図が設置されている
ただし、
ターミナル駅、交差点、歩道橋やその周辺では
群衆雪崩(将棋倒し)の危険性も高まるため、
迂回路も設定しておくと良いでしょう。
歩ける距離の目安
徒歩の速度は通常時で時速3.5~4kmですが、
震災時はがれき類や亀裂などで時速2~3km
になると考えられています。
また、履いている靴による移動可能距離は、
一般に革靴では15km、
ヒールでは4kmが限界とされています。
ルート策定時には最大移動距離は10kmと
見積り、ルート上の一時滞在施設を
把握しておきましょう。
なお、学校などの公共施設がすべて帰宅困難者
を受け入れてくれるわけではないため、
事前に確認が必要です。
実際に歩いてみることの重要性
ルートが策定できたら
実際に歩いてみることをおすすめします。
歩いてみると、思った以上に傾斜がきつかった
り、狭い道が点在していたりと、予想外の危険
ポイントが見つかることがあります。
また、事前に下見をしておけば、
「この先の様子が全く分からない」という
不安を軽減でき、災害時に冷静な判断が
しやすくなります。
便利なツールと持ち物
徒歩帰宅に役立つツールとしては、
以下のものがあります:
- 紙の地図やオフラインマップ:
首都圏であれば昭文社の
「帰宅支援マップ」がおすすめです。
東京都の場合は都が防災マップを
整備しています。
- ラジオ:
スマホの充電は家族との連絡のために
残しておくべきです。
携帯ラジオがあれば、
情報収集や心理的な支えになります。
ワイドFMポケットラジオが入っている
SONAEAREBA防災ボトルがおすすめです。
- Yahoo!マップ:
防災モードを備えており、オフラインで
職場と自宅の周辺地図とハザードマップを
ダウンロードできます。
災害時の情報収集方法

主な情報収集手段
災害時の情報収集の主な手段は
以下のとおりです:
- ラジオ
- テレビ
- インターネット
- 地域の防災無線
- 巡回している警察や消防などから
のアナウンス - 近隣住民からの話
災害時には、正確かつ迅速な情報収集が
求められます。
まずは被害状況、交通状況・ライフライン
の情報、気象情報などを確認しましょう。
インターネット依存のリスク
大きな災害が発生すると、
多くの人がインターネットを使って情報を
収集しようとするため、回線が混雑します。
さらに、大規模災害ではインターネット設備
自体が損傷するリスクもあります。
一般的には災害発生から6時間程度は
電話ができなかったり、インターネットに
つながりにくくなったりします。
また、スマートフォンの充電切れのリスクも
あるため、インターネット以外の情報収集手段
も準備しておくことが重要です。
代替手段の準備
インターネット以外の情報収集手段として、
以下のものを準備しておきましょう:
- 公衆電話:
比較的つながりやすいと言われています。
小銭を用意し、重要な連絡先を
メモしておきましょう。
事前に避難ルートの公衆電話の場所を
調べておくことをおすすめします。
参考リンク:
NTT東日本「公衆電話設置場所検索 」 - 災害用伝言板:
https://www.web171.jp/
にアクセスすると、知っている電話番号
への伝言登録が可能です。 - ポータブルラジオ:
ラジオは地元放送局を中心に
被災地向けの情報を多く発信しています。 - 防災無線:
公的機関からの正確な情報を得られます。
信頼できる情報源
災害時には、正確な情報が期待できる
公的機関のサイトを利用しましょう。
誤った情報に基づいて行動すると、
命に関わる問題になりかねません。
まとめと今日からできる対策
個人レベルでの対策
- 徒歩帰宅ルートの確認:
実際に歩いてみるか、地図やGoogle
ストリートビューで確認しましょう。 - オフィスでの個人備蓄:
デスク周りに最低限の水や食料、
簡易トイレなどを備えておきましょう。 - 情報収集手段の複数化:
スマホだけでなく、ラジオや災害用伝言板
の使い方も知っておきましょう。 - 適切な履物の準備:
オフィスに歩きやすい靴を
常備しておきましょう。
企業レベルでの対策
- 施設内待機方針の策定と従業員への周知:
災害時の基本行動方針を策定し、
従業員に周知しましょう。 - 備蓄品の確保と適切な保管:
3日分の食料や水、必要な物資を備蓄し、
適切に保管しましょう。 - BCP(事業継続計画)の策定:
災害時の事業継続のための計画を
立てましょう。 - 定期的な避難訓練の実施:
エレベーター停止時の対応や階段での
避難などを実際に訓練しましょう。
コミュニティレベルでの対策
- 地域の防災訓練への参加:
地域で行われる防災訓練に積極的に
参加し、顔の見える関係を作りましょう。 - 近隣企業との連携:
災害時の相互支援体制を構築しましょう。 - 地域の防災マップの確認:
避難所や危険箇所を
事前に把握しておきましょう。
日常からの意識づけ
災害対策は
「いざという時のため」だけでなく、
日常生活の中での習慣づけが大切です。
例えば:
- 外出時はスマホの充電を常に確保する
- 経路検索アプリだけに頼らず、
主要な道路や目印を意識する - 天気予報を毎日チェックする習慣をつける
- オフィスの備蓄品の賞味期限を
定期的に確認する
都市型災害は年々増加傾向にあり、
特に大都市では独自のリスクと対策が
求められます。
帰宅困難者問題やエレベーター停止などの
都市特有の問題に対して、
個人、企業、地域レベルでの備えを
日頃から進めておくことが重要です。
「備えあれば憂いなし」の精神で、
普段からできる防災対策を
継続的に実践していきましょう。
この記事が皆さんの防災意識向上と
具体的な対策の参考になれば幸いです。
次回もSONAEAREBAで、
暮らしに役立つ防災情報をお届けします!
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。