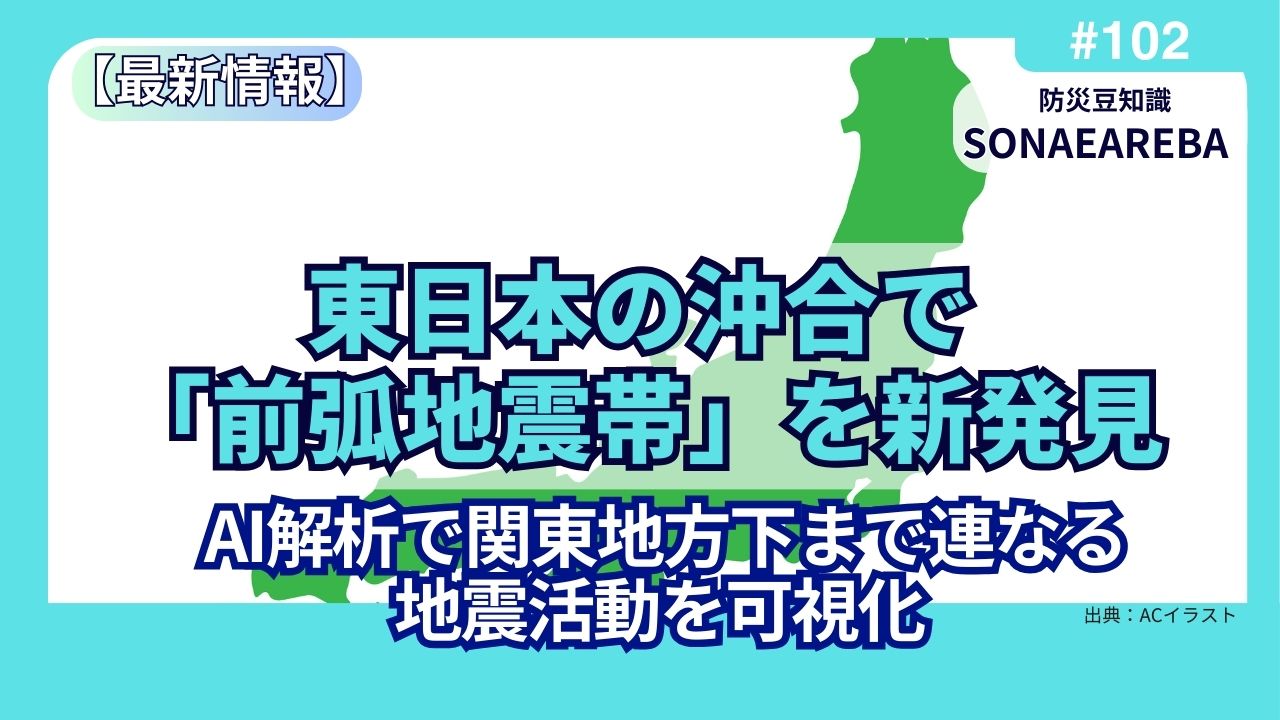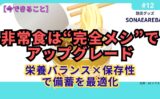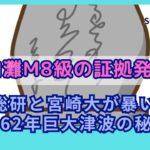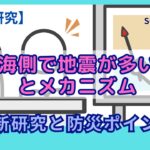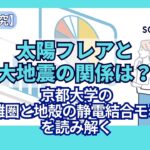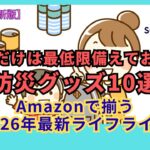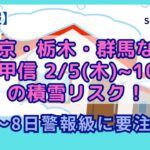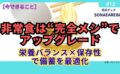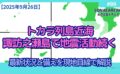この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
結論から言うと、
東北大学・東京大学などの研究チームが
S-net等の海底観測データをAIで高密度
解析し、北海道から東日本の沖合を経て
関東地方下にかけて「前弧地震帯」
と呼ばれる新たな帯状の地震活動域
を特定したことが、
2025年7月に公表されています。
参考リンク:
国立大学法人東北大学
国立大学東京大学地震研究所
プレートから上昇する水が
巨大地震の破壊拡大を止め
何が見つかったのか
今回明らかになったのは、
北海道・東北沿岸から関東地方の直下に
連続する、深さおよそ35〜75kmに
集中する帯状の地震活動域で、
海溝と火山列の間に位置する
「前弧」領域に沿って延びる
新しいタイプの地震帯です。
研究チームは「前弧地震帯」と命名し、
これが東日本太平洋側の広域にわたる
地震発生様式を整理する鍵になる
としています。
どうやって分かったのか
海底地震観測網S-netを含む
約594観測点、約4年間分(2016年夏〜
2020年夏)の波形データを深層学習で
再解析し、従来の約6倍にあたる
58万件超の震源を同定した結果、帯状の
高密度震源分布が浮かび上がりました。
この高解像度カタログ化によって、
プレート上部の浅い領域から境界、
スラブ地殻に至る「三層的」な
震源分布構造も見えてきました。
なぜ重要なのか
解析は、プレート内部の脱水で
水が上昇し摩擦が低下するプロセスが、
スロースリップの発生と
巨大地震の破壊拡大の抑制、
そして一方で直下型地震の誘発に
関与しうることを示唆します。
前弧地震帯の存在は、
プレート境界巨大地震の成長や停止、
内陸直下のリスク評価を統一的に
説明できる可能性を広げます。
関東直下・東日本の文脈
関東周辺は太平洋プレートと
フィリピン海プレートが重なって沈み込む
極めて複雑な場で、上部地殻〜
プレート境界〜スラブ内の多層的な
地震活動が以前から指摘されてきました。
今回の前弧地震帯は、
その複雑性の「帯状の核」を可視化し、
関東直下の発震様式や広域リスク評価の
更新に資する新フレームを与えます。
最新観測網とのシナジー
日本は海底観測網(S-net等)や
新たな海底モニター拡充で、
スロースリップなど従来見えなかった
前兆・緩動現象の直接観測を
強化しています。
こうした高精度観測は、
前弧地震帯における「ゆっくりすべり」と
通常地震の相互作用の解明、即時警報や
津波予警時間の延伸にもつながります。
公的評価との整合
政府の地震調査研究推進本部は
毎月の活動評価を更新しており、
2025年時点でも東日本〜関東周辺の
広域活動を継続監視しています。
今回の学術的発見は、
地域別リスク評価や長期評価の解像度向上
に資する知見として位置づけられます。
参考リンク:
地震調査研究推進本部事務局WEBサイト
生活・防災への示唆
今回の発見自体が直ちに
特定の巨大地震を予告するものでは
ありませんが、帯状の活動域が
関東直下を含む広域に連続することから、
最新のハザード情報の定期確認と、
家庭・職場の耐震・備蓄の基本対策を
平時からアップデートする意義は
一層高まっています。
高密度観測とAI解析の進展により、
前兆現象の把握や即時警報の高度化が
進む見通しで、実効的な減災につながる
期待が大きいです。
出典・参考: 東北大・東大らの研究成果発表および要約記事、
S-net高解像度解析の報道、政府月報・長期評価の公開情報を
基に構成しています。