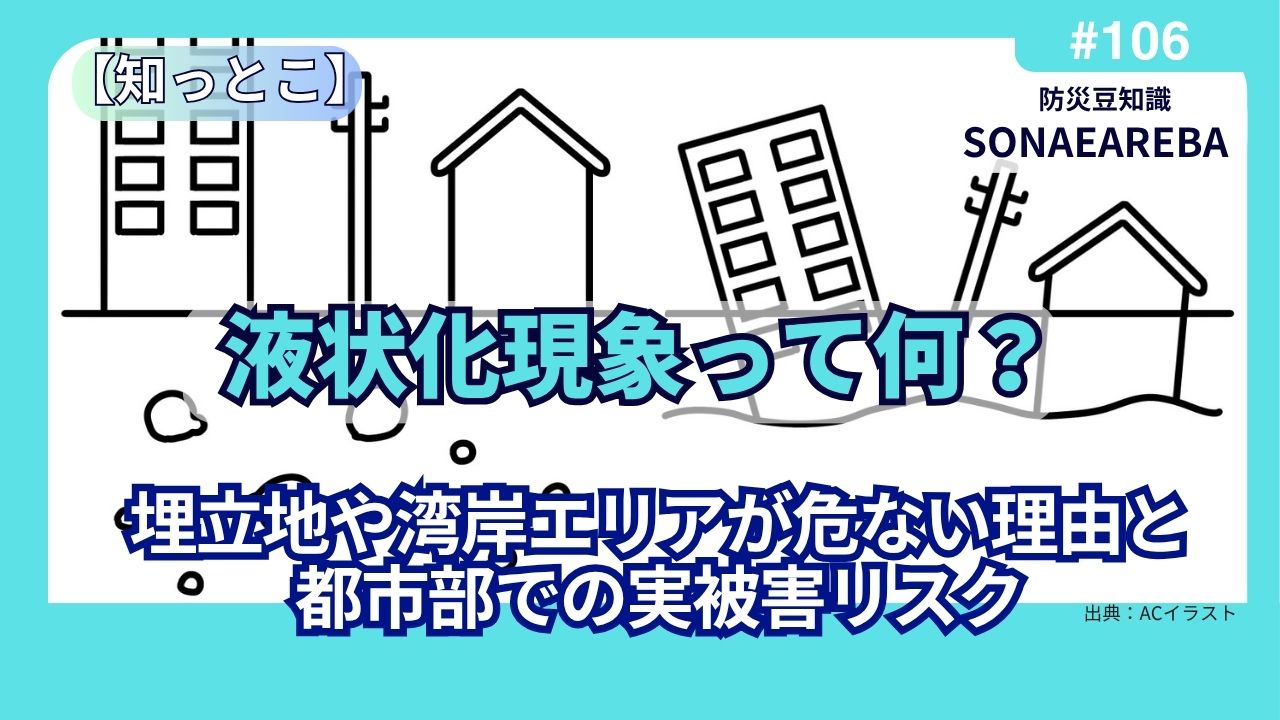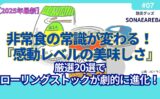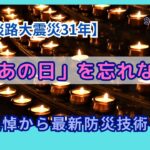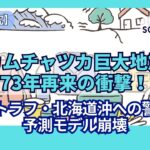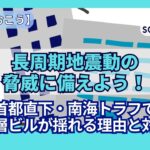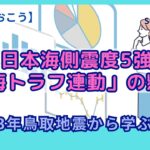この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
都市の足元は、
思っている以上に脆いかもしれません
――それが「液状化現象」です。
都市開発が進んだ東京湾岸や大阪湾岸、
名古屋港周辺の埋立地・三角州地帯では、
見た目が整然としていても、
地震時に地盤がドロドロ化して
家屋や道路が沈下・傾斜するリスクが
続いています。
参考リンク:
国土交通省ホームページ
地形区分に基づく液状化の発生傾向図等
液状化って何?
液状化は、地震の揺れで砂が緩み、
地下水の圧力が高まって土粒子が
バラバラになり、地盤が液体のように
振る舞う現象です。
木造住宅など軽量で基礎が浅い建物は
傾きやすく、道路・下水・ガスなどの
ライフラインも障害が出やすくなります。
2011年の東日本大震災では湾岸の埋立地
で住宅の沈下・傾斜、道路や配管の被害が
広範囲で確認され、復旧のハードルの
高さも社会課題になりました。
どこで起きやすい?
起きやすい条件は
「緩い砂層」「地下水位が浅い」
「粒径が均一な砂」で、
海岸・河口・扇状地・埋立地・三角州の
市街地が典型です。
東京では都が「液状化予測図」を
公開し、区ごとのリスク把握を
後押ししています(令和5年度改訂)。
参考リンク:
東京都建設局ホームページ
東京の液状化予測図 令和5年度改訂版
大阪府もPL値(液状化可能性指数)を
使った判定を示しており、
自治体のハザード情報は居住地選びや
備えの第一歩になります。
参考リンク:
大阪府ホームページ
震度分布・液状化可能性
(平成25年8月算出)
なぜ都市部で見逃されがち?
都市の再開発で道路や建物が新しくなると
「地盤まで強い」と錯覚しがちですが、
地盤条件そのものは変わらない場合が
あります。
とくに埋立地は区画が美しく整っていて
も、地震で長く揺さぶられると液状化が
顕在化し、地盤改良やライフライン復旧に
時間と費用がかかります。
過去事例でも、修理・売却・建て直しの
判断が難航し、住民負担や合意形成が
大きな壁になりました。
最新動向と技術トレンド
直近では、能登半島地震の被災地で
「地下水位低下工法」による再発防止の
実証工事が進んでいます。
千葉市でも住宅地スケールで同工法を
適用し、外周止水・集排水・揚水で
地下水位を下げ、非液状化層を厚くする
ことで被害抑制が確認されています。
研究・設計面では、浅層盤状改良など
実現性の高い宅地対策の有効性が
蓄積され、非液状化層を地表から
数メートル確保する設計思想が
整理されています。
リスク評価の実務ポイント
最初に見るべきは
自治体や国の地図で、地形区分に基づく
「液状化の発生傾向図」や
重ねるハザードマップの活用が有効です。
東京の液状化予測図や大阪府のPL値情報
など、地域の公式データで相対リスクを
確認し、必要に応じて地盤調査や
専門家評価へと進めます。
新居選びでは、自治体ハザードと
国交省の重ねるハザードマップを併用し、
揺れやすさ・地盤・浸水と合わせて
「総合リスク」で比較検討します。
参考リンク:
重ねるハザードマップ – 国土地理院
個人が取れる備え
まずは自宅周辺の液状化ハザードマップ
確認と家族での避難動線の見直し、
次に地盤判定と必要な地盤改良の検討が
基本です。
既存住宅でも表層・中層改良や、
敷地単位の地下水位管理など対策メニュー
があり、費用対効果をプロと議論しながら
段階的に進められます。
非構造物の転倒防止、断水・停電に
備えた物資やポータブル電源の準備も、
ライフライン停止時の実害を抑える
現実的な対策です。
エリア別の着眼(東京・大阪・名古屋)
- 東京湾岸(江東区・江戸川区など)は
埋立地が広く、都の予測図で相対評価
を確認し、区の詳細図や地盤情報と
突き合わせるのが有効です。
また、東日本大震災では
千葉県浦安市の舞浜周辺を含む
埋立地で広範囲に液状化が発生し、
家屋被害が甚大でした。
- 大阪ではPL値に基づく可能性判定が
公開され、湾岸低地の地盤条件と
南海トラフ地震の長周期・長時間動揺
の組合せを念頭に置きます。
- 名古屋港周辺の三角州・埋立は
全国的な傾向と同様で、
自治体ハザードと宅地レベルの
地盤調査をセットで判断するのが
合理的です。
SONAEAREBAとしての視点
都市の防災は
「買う前に調べる」「住んでから備える」
「地域で減災する」
の三段構えが現実的です。
住環境の意思決定を
地盤・水位・地形のファクトで支え、
必要時に専門家と連携して宅地改良や
地下水位管理など最適解を選ぶ――
それが長期的な資産防衛につながります。
バックの中に、あるという「安心」を。
通信障害時に役立つワイドFMラジオ付き
「空間にマスクする感覚」
地方自治体避難所開設用パーテーション