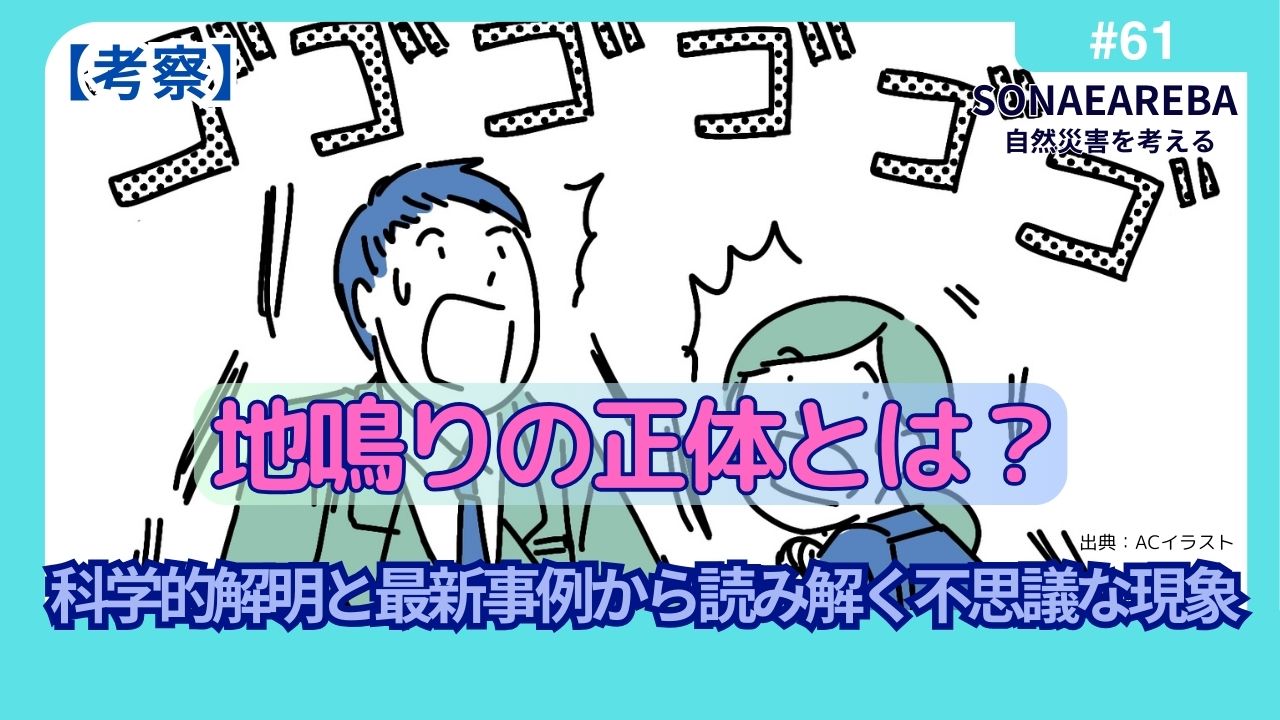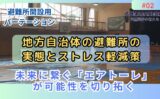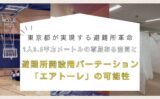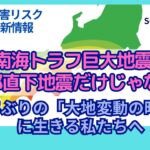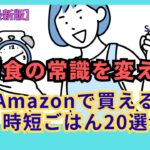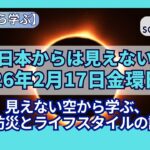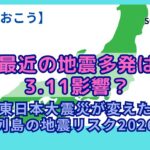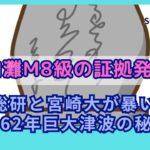この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
2025年5月に青森県津軽地方で発生した
謎の「ドーン」という音は、
多くの住民を不安にさせました。
この現象は「地鳴り」ではないかと
話題になりましたが、
その正体は何だったのでしょうか?
今回は地鳴りの科学的メカニズムから
最新事例まで、総合的に解説していきます。
地鳴りとは?基本的な定義と特徴
地鳴り(じなり)とは、
地震などによって地盤が振動して
空気中に伝わる音響現象のことです。
日本大百科全書によると、
「地震の振動が低い音として聞こえる現象」
と定義されています。
場合によっては「地響き(じひびき)」や
「鳴動(めいどう)」とも呼ばれ、
宏観異常現象の一種とされています。
私たちが住む地面の下では、
常に様々な地殻変動が起きていますが、
その多くは人間の感覚では捉えられません。
しかし、特定の条件が揃うと、
これらの振動が「ドーン」「ゴー」といった
低い音として私たちの耳に届くことが
あるのです。この現象が「地鳴り」です。
地鳴りの特徴として重要なのは、
音だけが聞こえることがあるという点です。
身体では感じないほど小さい地震でも、
音として聞こえることがあります。
この特性が、地鳴りを神秘的かつ不思議な現象
として人々に印象付けてきました。
地鳴りのメカニズム:なぜ音が発生するのか?
地鳴りが発生するメカニズムについて、
科学的な説明を見ていきましょう。
地鳴りは、地震の震源で発生した振動のうち、
数十ヘルツ以上という周波数の高いものが
地表に達して空気中を伝わってくる現象です。
人間の耳が聞ける周波数は20Hz~2万Hzと
されており、この範囲内の振動を地鳴りとして
聞くことができます。
一般的な地震の震動の周波数は数Hzと
低いため、通常は音として聞こえません。
しかし、高周波の振動が発生した場合、それが
空中音波となって私たちの耳に届きます。
研究によると、地鳴りの周波数特性は30Hzから
40Hz付近の帯域にピークがあることが明らかに
なっています。
地鳴りのメカニズムを
さらに詳しく説明すると、地震波には主に
P波(縦波)とS波(横波)があります。
P波は最初に到達する波で、
S波よりも速く伝わります。
一般的に、私たちが「地震だ!」と
認識する大きな揺れはS波によるものですが、
その前に到達するP波の振動が音として
漏れることがあり、それが地鳴りの正体だと
考えられています。
地鳴りと地震の関係:前兆なのか同時現象なのか?
地鳴りは古くから地震の前兆ではないかと
言われてきました。
しかし、科学的に見ると、
地鳴りは地震の前兆というよりも、
地震そのものに伴う現象であることが
わかっています。
日本地震予知学会会長で電気通信大学の
早川正士名誉教授によると、
「地震予知と地鳴りの関係は
いまだ科学的に解明されておらず、
地震の前兆として考えるのは現時点で早計」
だとされています。
東海大学地震予知研究センターの
長尾年恭教授も
「地鳴りの研究に取り組んでいるという
人の話は聞いたことがない。観測自体、
どこで行なえば良いのかもわからず難しい」
と指摘しています。
地鳴りが地震の前兆だと
考えられるようになった理由には、
地震波の時間差が関係しています。
前述のように、P波とS波には到達時間に
差があり、P波の段階ではまだ揺れが小さい
ため地震と認識されないことがあります。
その時にP波によって生じた音(地鳴り)を
先に聞いて、その後にS波による揺れを
感じると、地鳴りが地震の前兆のように
感じられるのです。
ただし、松代群発地震(1965年~1970年)
のような長期にわたる地震活動では、
地鳴りが地震と同時に観測されており、
地震活動と地鳴りの関連性は
確かに存在すると考えられます。
参考リンク:
長野地方気象台ホームページ
「松代群発地震」
地鳴りが聞こえやすい地域の特徴
地鳴りは場所によって聞こえ方が
大きく異なります。
どのような場所で地鳴りが
聞こえやすいのでしょうか?
地下構造や地形によって、
地鳴りの聞こえやすい所と、
まったく聞こえない所があります。
特に、堅固な地盤の場合に地鳴りが
聞こえやすい傾向があります。
例えば、茨城県の筑波山周辺は、
普通は地下に隠れている基盤岩が
地上に顔を出しているために、
よく地鳴りが聞こえることで有名です。
また、中国での研究によると、
地鳴りは「山岳や基盤岩の露頭付近、
もしくは地下水の豊富な場所、
例えば河川敷や湖沼地帯等」
に限られるという特徴があります。
さらに「浅発大地震の際に出易く、
先行時間は数分から数日の範囲にある」
ともされています。
東京などの都市部ではほとんど事例がない
という報告もあり、地域による差が
大きいことがわかります。
地質構造によって地鳴りの伝わり方が
大きく影響を受けるということでしょう。
青森県津軽地方で発生した謎の音(2025年5月)
2025年5月3日、
青森県の津軽地方で「ドーン」という
大きな謎の音が響き、多くの住民が不安を
感じました。
この音は一部地域では
約7秒間も続いたとされ、
「地鳴りのようだった」「爆発かと思った」
といった声がX(旧Twitter)などの
SNSを中心に多数投稿されました。
青森県弘前市など津軽地方の広範囲で
「すごい地鳴りがした」
「なんだ今の地鳴りは」
などの声が多数あがり、その範囲は青森市や
日本海側のつがる市まで広がっていました。
ある温泉施設では
「お客さまが『ドン!という音がして、
天井の水滴がいっぺんに落ちてきた』、
それと
『大浴場に張ってあるお湯が揺れていた』」
という証言もありました。
この現象について青森地方気象台は
「地震や火山活動に関連した情報はない」
と回答しており、岩木山の火山活動との
関連も心配されましたが、
原因は特定されていませんでした。
しかし、興味深い分析が京都大学防災研究所の
山田真澄准教授から発表されています。
山田准教授は気象庁や防災科学技術研究所、
弘前大学などの地震計データを基に、
震動の到達時間などを集計分析しました。
その結果、発生地点は仰角32度程度の、
青森県西側の空中(深浦沖約数十キロ)と
考えられるという見解を示しました。
発生源については、
高速移動する物体がさらに速度を上げた際に
起きる衝撃波ではないかと推測しています。
「もし噴火であれば震動は
火山から広がる形になる」とし、
岩木山の火山活動との因果関係はない
と説明されています。
つまり、地上からではなく空中から発生した
現象である可能性が高いのです。
参考リンク:
yahooニュース 5/7(水) 19:52配信
「地鳴り」実は空中発生?/京大准教授分析
地鳴りと混同されやすい現象
地鳴りと混同されやすい現象には
どのようなものがあるのでしょうか?
特に空中から発生する音として
考えられるものを見ていきましょう。
ソニックブーム
ソニックブームとは、
戦闘機などが音速を超える速度で飛行した際に
発生する衝撃波による音です。
青森の事例でも、
その可能性が指摘されていました。
山田准教授の分析でも、
「速度は超音速飛行機と同程度のマッハ2」
との見解が示されています。
ただし、自衛隊や米軍が飛行していないと
否定していたため、少なくとも
公式の軍事活動ではなかったようです。
隕石・火球の落下
隕石や火球が大気圏に突入する際にも、
地鳴りのような音が発生することがあります。
2020年7月には関東上空に火球が出現し、
直後に爆発音も聞こえたことがSNSで
話題になりました。
隕石の落下によって発生する衝撃波は、
火球の速度と音速によって決まる
「マッハ円錐」形状で広がります。
火球の速度が速く、円錐とはいっても
ほとんど円柱に近い形状になるそうです。
通常、隕石の落下に伴う衝撃波は、
音速で伝わるため、火球の出現から数分後に
地上に到達します。
また、衝撃波が強く聞こえる地域は、
隕石が落下した地域から何十kmも離れている
ことが多いという特徴もあります。
ただし、青森の事例では、
隕石や火球の目撃証言がなかったことから、
その可能性は低いと考えられていました。
電磁波音
もう一つ興味深い現象として、
「電磁波音」と呼ばれるものがあります。
これは火球の出現と同時にいろいろな音質の
音が聞こえる現象で、光と同じ程度の速度で
伝わることから、音として聞こえていても
本当は音ではない可能性があります。
全ての事例を人間の錯覚として
説明することは難しく、背後に出現した
流星に伴う「音」の観測報告もあるため、
特殊な現象として研究されています。
地鳴りの研究状況と学術的取り組み
地鳴りの研究はどこまで進んでいるのでしょう
か?地鳴り現象の科学的解明に向けた取り組み
を見ていきましょう。
KAKEN(科学研究費助成事業データベース)
によると、
「地震に伴う地鳴り現象の観測と分類」
というテーマで研究が行われています。
この研究の目的は
「”地震”と”地震に伴う地鳴り”との関係を
科学的に解明すること」であり、
古来より地震動に伴って地鳴りを感じたという
記録は多数あるものの、その成因は明らかでは
なく、同時記録の報告も少ないことが課題と
されています。
研究では、音波(地鳴り)と地震動とを
同時にかつ同期して記録するシステムを
構築し、観測によって得られた地鳴りを
分類して地震との対応を整理しています。
興味深いのは、従来の地震観測記録の
サンプリング周波数は100Hz前後と
可聴域音波を記録するには不十分だった
という点です。
そのため、特別な収録装置を開発し、
東京大学地震研究所筑波地震観測所に
設置して観測を進めています。
別の研究では、地鳴りの周波数特性を調査し、
30Hz~40Hz付近の帯域でスペクトルに
ピークがあることを明らかにしています。
これにより、地鳴りが地表面にP波が到達し
音波に変換して発生しているという仮説が
立てられていますが、その物理的メカニズム
の解明は今後の課題とされています。
地鳴りは観測自体が難しく、
「どこで行なえば良いのかもわからない」
という課題も指摘されており、
科学的な解明にはまだ時間がかかりそうです。
しかし、高校生でも構成できる安価なシステム
を構築して記録を収集するなど、
教育的な取り組みも進められています。
地鳴りが観測された歴史的事例
地鳴りは過去にどのような事例が
報告されているのでしょうか?
いくつかの歴史的な事例を紹介します。
松代群発地震(1965年~1970年)
昭和40(1965)年8月から約5年間にわたり、
長野県松代町(現長野市松代町)周辺では
活発な地震活動が続き、震度1以上を観測する
地震が6万回以上も発生しました。
この「松代群発地震」では、
家屋の損壊や地すべりなどの被害とともに、
地震に伴う地鳴りや発光現象なども
観測されました。
地震活動が最も活発だった
1966年4月17日には、1日の地震回数が
6704回(約13秒に1回)にものぼり、
地鳴りも頻繁に報告されました。
この群発地震の原因として、
東西方向の圧縮力を受けている不安定な状態の
ところに地下からの水・ガスが上昇したこと
が考えられています。
1944年東南海地震
1944年に発生した東南海地震では、
静岡県や三重県などで地鳴りが
記録されたという報告があります。
この地震は太平洋戦争中に発生した大地震で、
多くの被害をもたらしました。
南九州での観測事例
鹿児島県の名瀬測候所では、
大正14年から昭和19年までの間に629回の
有感地震を観測し、そのうち地鳴りを伴った
ものは197回であったという記録があります。
調査によると、
P-S時間(P波とS波の到達時間差)が5秒未満
のものに地鳴りがもっとも伴いやすく、
P-S時間が8秒を超えるものには地鳴りを
伴いにくいという結果が得られています。
これは震源が浅く、近い地震ほど地鳴りを
伴いやすいことを示しています。
また、興味深いことに地鳴りの有無は
地震の大小(振幅の大きさ)には
ほとんど無関係であることも示されており、
地震の規模よりも、地震のタイプや
地下構造などの要因がより重要であることが
示唆されています。
地鳴りが聞こえたときの対処法
地鳴りを聞いたときは、
どのように対処すればよいのでしょうか?
実際的なアドバイスをまとめました。
冷静に状況を判断する
地鳴りは必ずしも大地震の前兆ではないこと
を理解しておきましょう。
日本地震予知学会会長の早川正士名誉教授も
「地震の前兆として考えるのは現時点で早計」
と指摘しています。
パニックにならず、冷静に状況を判断すること
が大切です。
情報を収集する
テレビやラジオ、インターネットなどで
地震情報や気象情報を確認しましょう。
最近では地方気象台や自治体のSNSアカウント
でも迅速に情報が発信されています。
青森の事例でも、自治体から
「地震や火山活動に関連した情報はない」
という発表がありました。
念のため備えを確認する
地鳴りと大地震の明確な因果関係は
証明されていませんが、念のため
非常用持ち出し袋や避難経路の確認など、
防災の備えを見直す良い機会にしましょう。
地鳴りのような音が聞こえた際には、
「改めて防災に対する意識と準備を見直す
きっかけに」してみてはいかがでしょうか。
周囲の人と情報を共有する
地鳴りを聞いた場合は、
周囲の人と情報を共有することも大切です。
SNSでの情報共有も有効ですが、
デマやフェイク画像、フェイクニュースに
惑わされないよう注意が必要です。
建物や家具の安全を確認する
松代群発地震の事例では、地鳴りに伴って
「家屋の損壊、墓石・石燈の転倒、落石、
地すべり、地割れ」
などの被害が報告されています。
家の中の危険な場所や倒れやすい家具などが
ないか確認しておくと安心です。
地鳴りに関するよくある質問(FAQ)
最後に、地鳴りに関するよくある質問を
Q&A形式でまとめました。
Q1: 地鳴りはどんな音がするのですか?
A1: 地鳴りの音は「ドーン」「ゴー」など
と表現されることが多いですが、
「雷鳴」「大砲」「衣を引き裂く音」
「低い連続音」など様々な表現があります。
場所によって聞こえ方が異なりますが、
同一地域ではいつも同じような音が聞こえる
傾向があります。
Q2: 地鳴りが聞こえたら必ず地震が起きるのですか?
A2: 必ずしもそうではありません。
地鳴りと地震の関係はまだ科学的に
十分解明されておらず、地震の前兆として
考えるのは早計とされています。
地鳴りは地震に伴って発生することが
多いですが、地震の大きさや発生時期を
予測するものではありません。
Q3: 地鳴りはどんな場所で聞こえやすいのですか?
A3: 堅固な地盤の場所で地鳴りが
聞こえやすい傾向があります。
例えば筑波山周辺は基盤岩が地上に露出して
いるため、地鳴りが聞こえやすいことで
知られています。一方、東京などの都市部では
ほとんど事例がないという報告もあります。
Q4: 大地震のときには必ず地鳴りがするのですか?
A4: 大地震の際には各地で地鳴りを感じたと
いう報告が多いですが、これは建物や構造物が
きしんだり、瓦や家具が揺れたりする音である
ことが多いとされています。実際の地鳴り現象
とは区別する必要があります。
Q5: 地鳴りの研究はどこまで進んでいるのですか?
A5: 地鳴りの研究は進められていますが、
観測自体が難しく
「どこで行なえば良いのかもわからない」
という課題があります。
現在は音波と地震動を同時に記録するシステム
の開発や、地鳴りの周波数特性の分析などが
行われています。
Q6: 地鳴りと地響きは同じものですか?
A6: 地鳴りは地震などで地盤が振動して
鳴り響く音を指しますが、
地響きは「重いものが落ちたり動いたりした
時の振動や音が、地面を伝わり響くこと」
を指します。
似た現象ですが、原因が異なります。
Q7: 青森で聞こえた謎の音の正体は何だったのですか?
A7: 2025年5月に青森県津軽地方で聞こえた
謎の音については、京都大学防災研究所の
山田真澄准教授が分析した結果、発生地点は
青森県西側の空中(深浦沖約数十キロ)で、
高速移動する物体による衝撃波の可能性が
高いとされています。
ただし、正確な原因は特定されていません。
まとめ:地鳴りの謎と科学
地鳴り現象は、古くから人々の関心を
集めてきた不思議な自然現象です。
地震の振動が音として聞こえる現象ですが、
その発生メカニズムや地震との
正確な関係性については、
まだ科学的に十分解明されていません。
地鳴りは主に地震波のうち高周波成分
(数十ヘルツ以上)が空気中に伝わることで
発生し、特に堅固な地盤の地域で聞こえやすい
傾向があります。
地震の前兆というよりは、
地震そのものに伴う現象と考えられていますが、
P波とS波の到達時間差によって、
地鳴りが地震の前兆のように感じられること
もあります。
2025年5月に青森県津軽地方で発生した
謎の音については、空中から発生した衝撃波の
可能性が高いとされています。
地鳴りとして報告された現象の中には、
ソニックブームや隕石の落下、
あるいは電磁波音など、
別の原因による可能性もあります。
地鳴りの研究は観測の難しさなどから限界が
ありますが、音波と地震動を同時に記録する
システムの開発や教育用教材としての活用など
も進められています。
地鳴りが聞こえた場合は、
パニックにならず冷静に状況を判断し、
必要な情報収集と防災準備を行うことが
大切です。
地鳴りの謎は完全には解明されていませんが、
科学的アプローチによる研究が進むことで、
将来的にはより明確な理解が得られるかも
しれません。自然の不思議な現象として、
今後も注目していきたいトピックです。
最新の研究や観測事例を通じて、地鳴り現象の
理解が深まることを期待しています。
皆さんも地鳴りのような不思議な音を
聞いた際は、ぜひ記録に残して情報共有
してみてください。
科学の発展に貢献できるかもしれません。
それでは、
今回は「地鳴りの正体とは?」というテーマで
お送りしました。SONAEAREBAでした。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。