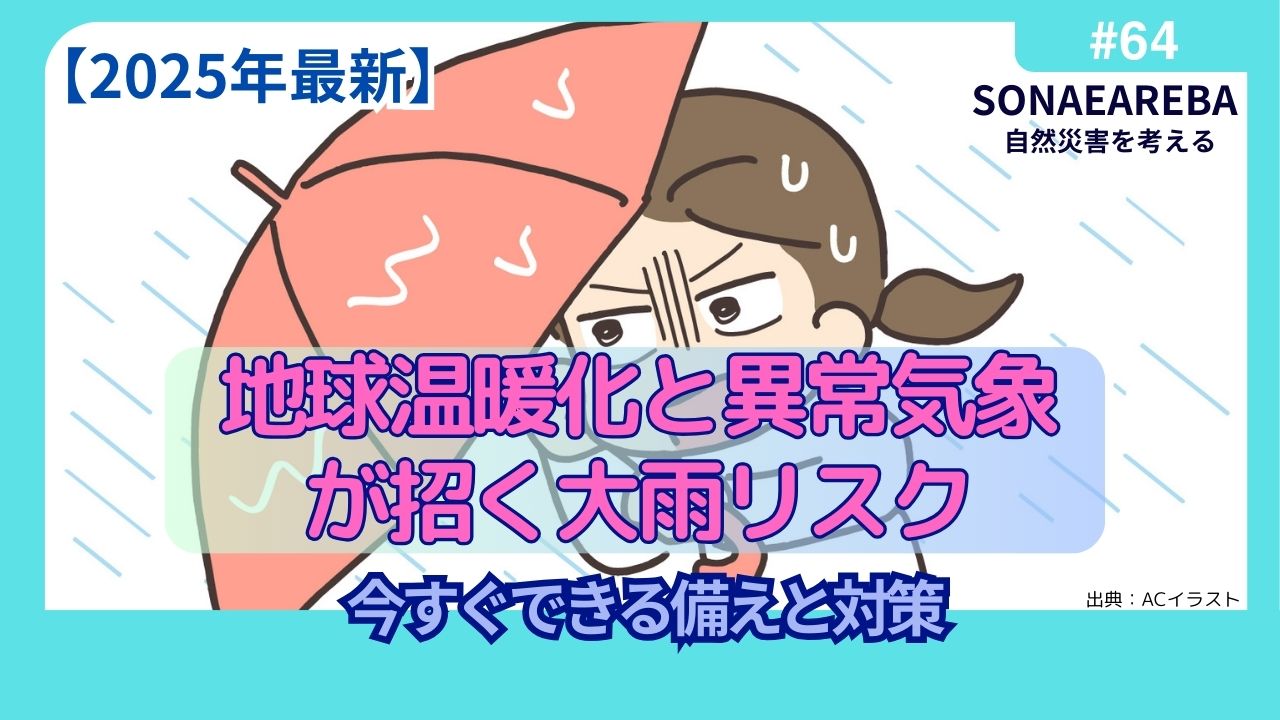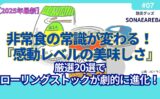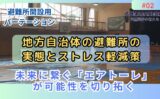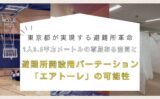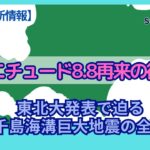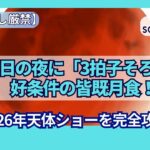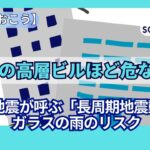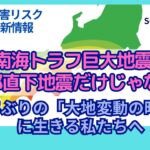この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
日本の平均気温は
過去100年間で約1.28℃上昇し、
猛暑日や豪雨の増加といった影響が
顕著になっています。
2024年には記録的な豪雨が各地で発生し、
今後もこの傾向は強まると予測されています。
本記事では地球温暖化の現状と
大雨への具体的な備え方を解説します。
ハザードマップの活用法から
家庭でできる対策まで、
命を守るための必須知識をお伝えします。
近年の異常気象と地球温暖化の関係
2025年も梅雨入りの時期が
近づいてきましたね。
最近の天気予報を見ていると
「記録的な大雨の恐れ」「線状降水帯に警戒」
といったフレーズを
頻繁に耳にするようになりました。
昨年2024年も夏は記録的な猛暑となり、
多くの地域で豪雨や土砂災害が頻発しました。
振り返ってみると、
猛暑と豪雨という一見矛盾する現象が
同時に起きているのが現代の異常気象の
特徴です。
この背景には、私たちが直面している
地球温暖化の影響があります。
2024年に起きた異常気象の実例
2024年は多くの地域で猛暑や豪雨による
災害が発生しました。
特に印象的だったのは
7月下旬に発生した石川県、山形県を
はじめとする北日本での豪雨です。
気象庁の異常気象分析検討会によると、
この豪雨の背景には強い高気圧や日本近海の
高い海面水温、エルニーニョ現象の影響が
あったことが報告されています。
参考リンク:
ウェザーニュース ホームページ
今年も猛暑や豪雨、土砂災害が頻発…
また、東海・関東地方でも
記録的なゲリラ豪雨が連日発生し、
都営地下鉄が20年ぶりに浸水するなど、
首都圏でも大きな被害が出ました。
さらに「超ノロノロ台風」と呼ばれる
台風10号の影響で、大分県由布市では
48時間で603mmという大雨を記録し、
宮川の氾濫により大きな被害となりました。
これらの異常現象は、
以前であれば非常に稀だった現象が、
気候変動によって発生頻度が高まっていること
を示しています。
ウェザーニューズの気候解析チームによると、
大分県由布市で記録された大雨は約30年前には
123年に一度程度の非常に稀な現象でしたが、
近年では63年に一度程度の頻度に変化している
と分析されています。
気象データが示す温暖化の進行
日本の気象データを見ると、
気温上昇の傾向は明らかです。
日本の平均気温は長期的には100年あたり
1.28℃のペースで上昇しており、
特に1990年代以降、高温となる年が
増加しています。
参考リンク:
国立市 ホームページ
地球温暖化の現状とその対策について
また、降水パターンにも変化が生じています。
気象庁のデータによると、
全国の1時間降水量50mm以上の大雨の
年間発生回数は増加しており、
1976~2024年の統計では10年あたり28.2回
の増加が見られ、これは統計的にも
有意な変化です。
参考リンク:
気象庁ホームページ
大雨や猛暑日などのこれまでの変化
最近の10年間(2008~2017年)は、
統計期間の最初の10年間(1976~1985年)
に比べて、50mm以上の1時間降水の
年間発生回数が約1.4倍に増加しています。
このデータからも、雨の降り方が
極端になっていることがわかります。
地球温暖化が日本にもたらす影響の現状
世界気象機関(WMO)が2025年3月に
公表した年次報告書によると、
2024年の世界平均気温は過去最高を記録し、
産業革命前と比べた上昇幅は1.55度に
達しました。この数値はパリ協定で
目標としている「1.5度に収める」という
基準に非常に近づいており、地球温暖化の
進行が危険なレベルに達していることを
示しています。
日本の気象変化と予測される未来
日本においても、
温暖化の影響は顕著に表れています。
環境省のデータによると、
日本の平均気温は1898~2008年の
観測結果によると、100年あたり1.11℃
の割合で上昇しています。
最近の統計では100年あたり
1.35℃という数値も報告されており、
上昇率が加速していることがわかります。
この温暖化傾向は今後も続くと
予測されており、対策を取らなかった場合、
21世紀末には日本の平均気温は
さらに上昇すると予測されています。
特に懸念されるのは、
真夏日(最高気温が30℃以上)の増加です。
東京の現在の真夏日は年間約46日ですが、
21世紀末には年間約103日、つまり1年の
3割近くが真夏日になると予測されています。
豪雨と浸水リスクの高まり
温暖化に伴う気温上昇は、
大気中に含むことができる水蒸気の量も
増加させます。
その結果、一度に降る雨の量が増え、
台風も強くなる可能性が高まります。
気候変動の影響として、
2100年末に日本では気温上昇や災害の増加、
生態系の変化のほか、健康被害などが
予測されています。
特に注目すべきは降水量の変化です。
大雨や短時間の強い雨の発生頻度、
雨の強さは増加する一方で、
雨の降る日数は減少すると予測されています。
つまり、降水が集中して一度に大量の雨が降る
という傾向がさらに強まるということです。
文部科学省および気象庁の
「日本の気候変動2020」によれば、
温暖化によって豪雨や雷雨は夏だけでなく、
1年を通して増えており、雨の降り方が極端に
なる傾向は今後も続くと予測されています。
これにより土砂災害や洪水浸水リスク、
特に都市洪水リスクが増大します。
参考リンク:
気象庁ホームページ
「日本の気候変動2020」
最近の豪雨災害から学ぶ教訓
近年の豪雨災害の特徴を理解することで、
より効果的な備えが可能になります。
これまでの被害事例から得られた教訓を
見ていきましょう。
変わりつつある豪雨の特性
従来、梅雨期の豪雨による大きな災害は
九州や四国、本州でも新潟・福島くらい
までが主だったという印象がありました。
しかし、昨今では石川や秋田や山形県、
あるいは北海道でも梅雨期に
豪雨が発生するようになりました。
気候変動により、豪雨の発生地域が
北上していると言えるでしょう。
また、豪雨の発生パターンにも
変化が見られます。
2024年の台風10号は「超ノロノロ台風」と
呼ばれ、非常にゆっくりとした速さで
九州地方に上陸し、長時間にわたって
大雨をもたらしました。
このような動きの遅い台風は、
特定の地域に大量の雨を降らせ、
甚大な被害をもたらす危険性があります。
京都大学の関⼭健教授によると、
世界の平均気温が産業⾰命前の19世紀と
⽐べて2度上昇すると、1時間に50mm以上の
「短時間集中豪⾬」の発⽣率が、
現状よりも1.6倍に増えるという
予測があります。
しかも、この2度の上昇は
遠い未来の話ではなく、2050年頃には
達する可能性が高いのです。
参考リンク:
日本医師会ホームページ
「地球温暖化が進んだ未来」
浸水被害のリスク地域とは
浸水リスクを考える上で重要なのは、
地形の特徴を理解することです。
国土地理院が公開している
「デジタル標高地形図」は、地形の起伏を
色別に表示しており、浸水リスクの高い
地域を直感的に理解するのに役立ちます。
参考リンク:
国土地理院ホームページ
「デジタル標高地形図」
例えば、
東京東部は内陸まで低海抜の地域が続いて
おり、特に荒川流域では沿岸部よりも少し
内陸側に海抜が低い地域が広がっています。
江戸川区のハザードマップによると、
満潮時には区の陸の約7割が水面より低い土地
になっており、想定最大規模の大雨で荒川や
江戸川が氾濫すると、江戸川区を含む江東5区
のほとんどが浸水すると予測されています。
同様に、
名古屋周辺では伊勢湾にいくつもの河川
が流れ込んでおり、全域的に海抜が低く、
大阪も複数の河川が大阪湾に流入する地域で
沿岸部から淀川流域にかけて海抜が
低い地域が広がっています。
このような地形的特徴を持つ地域では、
大雨時の浸水リスクが特に高いと
言えるでしょう。
大雨に備えるための基本対策
豪雨災害に備えるためには、
事前の準備と正しい知識が不可欠です。
以下に、誰でも実践できる
基本的な対策をご紹介します。
ハザードマップを活用した防災計画
ハザードマップとは、
大雨、台風、地震などの災害が起こったとき
に、浸水やがけ崩れなどの危険がある箇所や、
危険が迫ったときの避難経路や避難場所などを
地図上にまとめたものです。
ハザードマップは以下の方法で
入手することができます:
- お住まいの市区町村役場の窓口で
入手する - お住まいの市区町村のホームページから
ダウンロードする - 国土交通省の
「ハザードマップポータルサイト」
から入手する
ハザードマップを入手したら、
まず自宅や勤務先周辺の危険エリアを
確認しましょう。
浸水の可能性がある場所や、
土砂災害(崖崩れ・土石流・地すべりなど)
の危険性の高い場所を把握しておくことが
大切です。
次に、避難場所(指定緊急避難場所)
を確認しておきましょう。
避難場所は災害の種類によって異なります。
「浸水や土砂災害の場合の避難場所」
をしっかり確認するようにしましょう。
さらに、避難場所までの避難経路を
知っておくことも重要です。
河川が増水した場合や高潮・高波でも
安全に避難できる経路を確認してください。
気象情報の入手と活用方法
豪雨に備えるためには、
気象情報を適切に入手し、
活用することが重要です。
日本気象協会の「tenki.jp」や
気象庁のウェブサイトでは、
最新の気象情報や警報・注意報を
確認することができます。
また、スマートフォンアプリを活用すれば、
いつでもどこでも最新の気象情報を
入手することが可能です。
豪雨の兆候があった際は、
慌てずに情報収集に努めることが大切です。
事前に担当者を任命しておき、
自宅や勤務先などがある地域に豪雨が発生する
かどうかの情報収集を行いましょう。
特に注意すべきなのは、気象庁が発表する
「特別警報」や「警報」、「注意報」です。
これらの情報に加えて、
気象庁の「キキクル(危険度分布)」を
活用することで、自分がいる場所の危険度を
リアルタイムで把握することができます。
家庭でできる具体的な防災対策
豪雨に備えるための家庭でできる
具体的な対策をご紹介します。
これらの対策を事前に行うことで、
万が一の際の被害を最小限に抑えることが
できます。
浸水対策の実践法
浸水対策として、まず溝や雨どいをこまめに
掃除することが重要です。
側溝や雨どいにゴミなどが溜まっていないか
確認しましょう。
側溝が詰まっていると雨水がうまく流れず、
溢れ出す可能性も高まります。
次に、土のうや水のうなどを
用意しておくことをおすすめします。
土のうは自治体などで配布している
ところもあります。(土のうステーション等)
土のうの入手が難しい場合は、
二重にした大きめのゴミ袋に水をためて
作った水のうを代わりに使用しましょう。
豪雨の予兆があった際には、
土のうや防水シート、止水パネルなどが
正常に使えるかどうかの確認をしたあと、
浸水の危険がある場所に設置します。
玄関などの水の侵入が考えられる場所に、
土のうや水のうを設置することで、
水の侵入を防ぐことができます。
非常用グッズと避難計画の準備
万が一に備えた非常用グッズを
リュックにまとめておきましょう。
非常用グッズの使用期限や消費期限は
定期的に確認しましょう。
避難時に必要なものは、
日頃からリスト化しておくと便利です。
万が一の断水に備えて、
飲料水やトイレなどの生活用水の
確保をしておきましょう。
生活用水の確保は、
浴槽などに水を張っておくとよいでしょう。
スマートフォンや携帯電話は、
万が一の際に連絡を取ったり、
情報を入手したりする手段として、
必需品となっています。
停電に備えて、あらかじめスマートフォンや、
モバイルバッテリー充電をしておきましょう。
ノートパソコンも同様です。
また、ノートパソコンは充電器の代わり
として使用することも可能です。
ハンディファンも暑さ対策に役立ちます。
避難計画については、家族と一緒に話し合い、
避難経路や避難場所、連絡方法などを
確認しておきましょう。
特に、家族が離ればなれになった場合の
集合場所や連絡手段を決めておくことが
重要です。
デジタルツールを活用した防災情報の入手法
近年、スマートフォンやインターネットを活用
した防災情報の入手方法が充実しています。
これらのデジタルツールを活用することで、
より迅速かつ正確に防災情報を入手することが
可能になります。
防災アプリと活用シーン
現在、様々な防災アプリが提供されています。
これらのアプリを活用することで、
気象情報や避難情報、ハザードマップなどを
手軽に確認することができます。
代表的な防災アプリとしては、
「Yahoo!防災速報」「NHK ニュース・防災」
「気象庁 気象災害情報」などがあります。
これらのアプリでは、
自分がいる場所の気象情報や避難情報を
プッシュ通知で受け取ることができるため、
迅速な避難行動につなげることができます。
また、「ハザードマップポータルサイト」の
モバイル版を活用すれば、外出先でも
ハザードマップを確認することが可能です。
豪雨時に自分がいる場所の危険度を確認する
際に役立ちます。
ハザードマップポータルサイトの使い方
国土交通省が運営する
「ハザードマップポータルサイト」は、
全国のハザードマップを一元的に閲覧できる
ウェブサイトです。
このサイトでは、住所や施設名を
入力するだけで、その場所のハザードマップ
を表示することができます。
ハザードマップポータルサイトでは、
「重ねるハザードマップ」という機能を
使って、様々な災害リスクを地図上に重ねて
表示することができます。
例えば、洪水・土砂災害・津波などのリスクを
同時に確認することが可能です。
また、「わがまちハザードマップ」という
機能では、市区町村が作成したハザードマップ
を確認することができます。
自分の住んでいる地域のハザードマップを
探す際に便利です。
さらに、「災害リスク情報」では、
地点を指定するだけで、その場所の洪水や
土砂災害などのリスク情報を簡単に確認する
ことができます。
参考リンク:
「ハザードマップポータルサイト」
地球温暖化対策と大雨への備え
地球温暖化が進行する中、
大雨への備えとともに、
地球温暖化対策も重要です。
私たち一人ひとりができる温暖化対策と、
それが豪雨災害の軽減にどのように
つながるのかを考えてみましょう。
個人でできる温暖化対策
地球温暖化の主たる原因となる二酸化炭素は、
私たちの暮らしの中で発生します。
2020年度の家庭からの二酸化炭素排出量は、
約3.9トン/世帯とされています。
家庭からの二酸化炭素排出量を減らすため
には、エネルギー消費の多い照明や家電製品、
自動車、暖房、給湯などの使い方を
見直すことが効果的です。
具体的には、省エネ性能の高い照明や
家電製品への買い替え、公共交通機関の利用、
室温の適正管理などが挙げられます。
また、「うちエコ診断」を受診することで、
自分の家庭のどこでどのくらいエネルギーが
使われているのか、二酸化炭素排出量は
どれくらいなのかを知ることができます。
「うちエコ診断」は、WEB上で受診が可能。
出典・参考リンク:
環境省 うちエコ診断サイト
(https://webapp.uchieco-shindan.jp/)
地域社会での取り組み
地球温暖化対策は、
個人の取り組みだけでなく、
地域社会全体での取り組みも重要です。
例えば、
自治体や地域コミュニティでの緑化活動や
河川の清掃活動に参加することで、
豪雨時の被害を軽減することができます。
植物は二酸化炭素を吸収するだけでなく、
土壌の保水力を高める効果もあります。
また、地域の防災訓練に参加することで、
災害時の対応力を高めることができます。
特に、豪雨災害を想定した避難訓練は、
実際の災害時に冷静かつ迅速に行動するために
役立ちます。
今すぐできる備えのチェックリスト
最後に、大雨に備えるために
今すぐできる準備をチェックリスト形式
でまとめました。
以下の項目をチェックして、
自分自身や家族の安全を守るための準備を
整えましょう。
事前に確認しておくべきこと
- ハザードマップで自宅や職場周辺の
浸水リスクを確認する - 避難場所と避難経路を確認する
- 家族との連絡方法や集合場所を決めておく
- 非常用持ち出し袋の内容を確認し、
必要に応じて更新する - スマートフォンやノートパソコンの
充電器を用意しておく - 防災アプリをインストールし、
設定を完了させる
大雨が予想されるときの行動
- 気象情報や避難情報を定期的に確認する
- 側溝や雨どいの詰まりを確認し、掃除する
- 浸水の危険がある場所に土のうや水のうを
設置する - 大切な書類や写真、家財などを
高い場所に移動させる - 浴槽に水をためるなど、
生活用水を確保する - 食料や飲料水を確保する
- スマートフォンや携帯電話を充電しておく
- 危険を感じたら早めに避難する
避難指示従って行動する
まとめ:備えあれば患いなし
地球温暖化の影響で、
日本の気候は確実に変化しています。
100年あたり約1.3℃の気温上昇と共に、
豪雨の頻度や強度も増加しており、
今後もこの傾向は強まると予測されています。
特に近年は、
これまであまり豪雨被害が発生しなかった
地域でも被害が報告されるようになり、
災害のリスクは全国に拡大しています。
また、「超ノロノロ台風」のような
新たな現象も発生しており、従来の経験だけ
では対処できない状況が生まれています。
このような状況下では、
一人ひとりが正確な情報を入手し、
適切な対策を講じることが重要です。
ハザードマップで自宅や勤務先の危険度を
確認し、避難場所や避難経路を把握しておく
ことは、命を守るための基本的な準備です。
また、溝や雨どいの清掃、土のうや水のうの
準備といった具体的な浸水対策や、
非常用グッズの準備も欠かせません。
そして、スマートフォンアプリや
ハザードマップポータルサイトなどの
デジタルツールを活用して、
常に最新の防災情報を入手できるように
しておきましょう。
地球温暖化対策も重要です。
家庭でできる省エネ活動を実践し、
二酸化炭素の排出量を減らす努力も、
将来の災害リスクを減らすことに
つながります。
「備えあれば憂いなし」という言葉が
あるように、事前の準備が命を守ります。
本記事の内容を参考に、
大雨シーズンに備えて今すぐできる対策を
実践していただければ幸いです。
最後に、災害はいつ起こるかわかりません。
「自分は大丈夫」と思わずに、
常に最悪の事態を想定して備えておくことが
大切です。家族や地域の方々と協力して、
安全に過ごせるよう心がけましょう。
皆さんの防災対策が、
実際の災害時に役立つことを願っています。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。