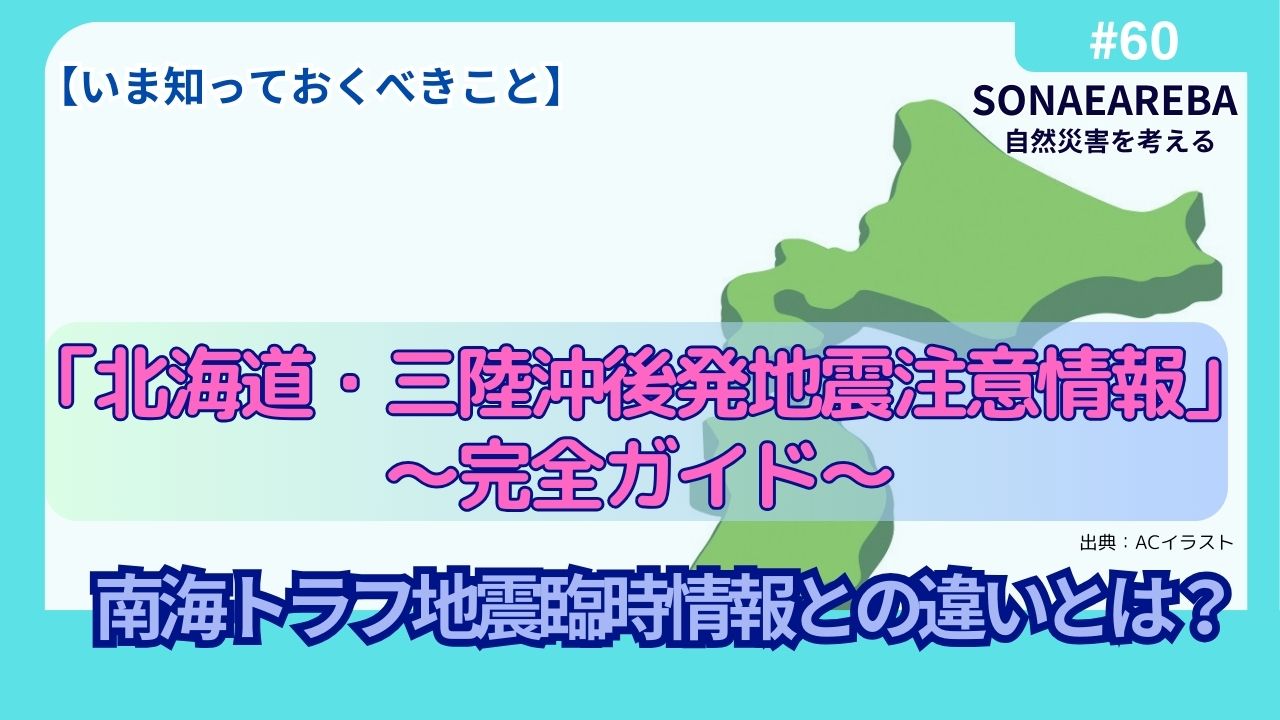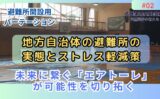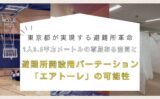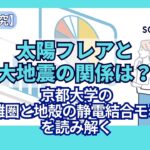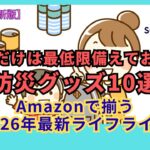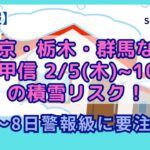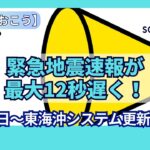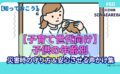この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
2024年8月8日、
日向灘を震源とする地震が発生し、
気象庁から
「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」
が発表されました。
この情報は多くのニュースで
取り上げられましたが、
実は日本には同様の目的を持つ
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」
という別の情報システムも存在しています。
今回は、この意外と知られていない
「もう一つの臨時情報」
について詳しく解説します。
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」とは何か?
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、
日本海溝・千島海溝沿いで地震が発生し、
さらに大きな地震(後発地震)が発生する
可能性が通常と比べて高まったと評価された
場合に、気象庁から発信される情報です。
最初に発生した地震を「先発地震」、
その後に引き続いて発生する可能性のある
地震を「後発地震」と呼びます。
この情報が発表されると、
特に1週間程度は後発地震に備えた
防災対策をとり、迅速に避難できるよう
準備することが求められます。
参考リンク:
気象庁ホームページ
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震について
導入の背景
なぜこのような情報システムが
導入されたのでしょうか?
日本海溝・千島海溝沿いの領域では、
過去にマグニチュード7クラスの地震が
発生した後に、東北地方太平洋沖地震
(マグニチュード9)のようなさらに大きな
地震が発生した事例が確認されています。
実際、2011年3月11日の東日本大震災の
2日前にも、マグニチュード7.3の地震が
発生していました。
このような歴史的事例を踏まえ、
先発地震の後に大規模な後発地震が発生する
可能性に注意を促すために、
2022年12月16日から
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」
の運用が開始されました。
参考リンク:
内閣府 防災情報のページ
北海道・三陸沖後発地震注意情報の解説ページ
「南海トラフ地震臨時情報」との違いは?
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」と
「南海トラフ地震臨時情報」は
似ているようで異なる点もあります。
両者を比較してみましょう。
対象地域の違い
最も大きな違いは対象地域です。
- 南海トラフ地震臨時情報:
南海トラフ沿い(主に西日本の太平洋側)
を対象 - 北海道・三陸沖後発地震注意情報:
日本海溝・千島海溝沿い(主に北海道から
東日本の太平洋側)を対象
つまり、これらの情報は日本列島を
ほぼカバーする形で、二つの大きな地震リスク
地域をそれぞれ担当しているのです。
情報の種類と基準の違い
「南海トラフ地震臨時情報」には
複数の種類があります:
- 南海トラフ地震臨時情報(調査中):
南海トラフの想定震源域またはその周辺で
M6.8以上の地震が発生した場合など - 南海トラフ地震臨時情報
(巨大地震警戒):
南海トラフの想定震源域内のプレート境界
でM8.0以上の地震が発生した場合 - 南海トラフ地震臨時情報
(巨大地震注意):
南海トラフの想定震源域内のプレート境界
でM7.0以上、M8.0未満の地震が発生した
場合など - 南海トラフ地震臨時情報(調査終了):
上記のいずれにもあてはまらない場合
一方、
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」
はこうした細かい区分はなく、
日本海溝・千島海溝沿いの領域及びその周辺で
モーメントマグニチュード7以上の地震が
発生した場合に発表されます。
参考リンク:
気象庁ホームページ
「南海トラフ地震に関連する情報」について
発表のタイミングと流れの違い
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、
地震発生から約2時間後に内閣府と気象庁
による合同記者会見で情報発信されます。
一方、「南海トラフ地震臨時情報」は
異常な現象の種類によって発表の
タイミングが異なります。
また、「南海トラフ地震臨時情報」では
「巨大地震警戒」が発表された場合、
海の近くに住んでいて津波からの避難に
間に合わない人は1週間避難することが
推奨されますが、
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」では
そのような直接的な避難の呼びかけは
行われず、備えの徹底が主に求められます。
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」はどのように発表されるのか?
情報発表の流れを具体的に見ていきましょう。
発表条件
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」
の発表条件は以下の通りです:
- 日本海溝・千島海溝沿いの領域及び
その周辺でモーメントマグニチュード7以上
の地震が発生した場合
ここで重要なのが
「モーメントマグニチュード(Mw)」
という単位です。
これは地震の大きさ
(地震が発するエネルギーの大きさ)を表す
指標で、特に巨大地震においても地震のエネル
ギーを正確に数値化することができます。
通常のマグニチュードとは異なる値になる
場合があるため注意が必要です。
情報発信の流れ
- 地震発生
- 数秒〜十数秒後:緊急地震速報
- 2〜3分後:震度速報・津波警報等
(第一報) - その後:地震情報、津波警報等(更新報)
- 約2時間後:内閣府・気象庁合同記者会見
による情報発信
先発地震による震度が大きい場合や
予想される津波が高い場合は、
先発地震についての気象庁記者会見や
官房長官会見が先に行われることもあります。
参考リンク:
気象庁ホームページ
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」
の発表基準と情報発表の流れ
防災対応を取るべきエリア
防災対応を取るべきエリアは、
北海道から千葉県までの
「震度6弱以上、津波高3m以上となる市町村」
とされています。
福島県の例では、
いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、
新地町が対象エリアとなっています。
ただし、対象エリア外が必ず安全というわけ
ではなく、エリア外に住んでいる場合でも
個々の状況を踏まえた日頃からの地震への備え
が必要です。
参考リンク:
福島県ホームページ
ふくしまぼうさいウェブ
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されたらどうすればいいのか?
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」
が発表された場合、特に1週間程度は
次のような対応が推奨されます:
- 日頃からの地震への備えの再確認:
避難場所・避難経路の確認、
非常用持ち出し袋の点検など - 迅速な避難ができる体制の確保:
特に沿岸部では、揺れを感じたら
すぐに避難できるよう準備 - 通常の生活を送りながらも
後発地震のリスクに備える
重要なのは、この情報が発表されても
「必ず地震が発生する」わけではない
ということです。
世界的事例を踏まえても、
実際に後発地震が発生する確率は
100回に1回程度とされています。
また、注意情報の発信により、
国や自治体が対象エリアの住民へ
即時避難を求めるものではなく、
対象の市町村内で避難所が必ず開設される
とも限らないことにも留意が必要です。
「南海トラフ地震臨時情報」発表の実例
2024年8月8日16時43分頃、
日向灘を震源とするマグニチュード7.1
の地震が発生しました。
この地震を受けて、
気象庁は19時15分に
「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」
を発表しました。
この地震は、西北西・東南東方向に圧力軸をも
つ逆断層型で、南海トラフ地震の想定震源域内
における陸のプレートとフィリピン海プレート
の境界の一部がずれ動いたことにより発生した
モーメントマグニチュード7.0の地震と
評価されました。
過去の世界の大規模地震統計データによると、
モーメントマグニチュード7.0以上の地震発生
後に同じ領域で、モーメントマグニチュード8
クラス以上の地震が7日以内に発生する頻度は
数百回に1回程度となります。
これが
「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」
が発表された理由であり、その後、
関西広域連合では広域防災担当委員の指示の
もと、対策準備室を設置し、被害の情報収集を
行うとともに、関西広域連合構成府県市民あて
メッセージを発出しました。
参考リンク:
関西広域連合ホームページ
南海トラフ地震臨時情報について
地震情報の発表における共通する考え方
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」と
「南海トラフ地震臨時情報」
は対象地域や細かい運用方法は異なりますが、
根底にある考え方は共通しています:
- 突発的な地震への備えが基本:
どちらの情報も、突発的に地震が発生した
場合を想定し、平時から事前の防災対策を
徹底することが大前提です - 確率は低いが無視できない
リスクへの対応:
大規模地震の後に続けて大きな地震が発生
する確率は低いものの、その可能性を無視
することはできません - 平時より高まった危険性への注意喚起:
どちらも、地震発生の可能性が平常時に
比べて相対的に高まっていることを
知らせるものです
日常生活でできる地震への備え
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」や
「南海トラフ地震臨時情報」が
発表されてから準備を始めるのでは
遅い場合もあります。
日頃から以下のような
地震への備えをしておくことが重要です:
- 家具の固定:
転倒防止器具を使用して家具を固定する - 安全な避難場所・避難経路の確認:
自宅からの避難経路を複数確保しておく - 非常用持ち出し袋の準備:
食料、飲料水、医薬品、懐中電灯、
携帯ラジオなどを備えておく - 家族との連絡方法の確認:
災害用伝言ダイヤル(171)や
災害用伝言板の使い方を確認しておく - 防災マップの確認:
居住地域のハザードマップを確認し、
危険な場所を把握しておく
参考リンク:
ハザードマップポータルサイト
特に後発地震に備えるためには、
先発地震で被災した際の対応と後発地震に
備えた対応を混同しないことが大切です。
先発地震で家屋に損傷がある場合は、
速やかに安全性を確認し、
必要に応じて避難することが重要です。
まとめ:二つの情報システムで日本列島を見守る
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」と
「南海トラフ地震臨時情報」は、
日本の二大地震リスク地域をそれぞれカバー
する情報システムとして機能しています。
これらは地震の直前予知を
目的としたものではなく、
大規模地震発生後の
「後発地震」への警戒を促すものです。
- 北海道・三陸沖後発地震注意情報:
2022年12月16日運用開始、
日本海溝・千島海溝沿いを対象 - 南海トラフ地震臨時情報:
2019年5月運用開始、
南海トラフ沿いを対象
どちらの情報も、発表されたからといって
必ず地震が発生するわけではありませんが、
地震への備えを再確認し、特に1週間程度は
警戒を強めることが推奨されます。
日本は世界有数の地震大国です。
地震はいつ発生するか予測できないものです
が、適切な備えをしておくことで被害を
最小限に抑えることが可能です。
日頃からの防災意識と
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」や
「南海トラフ地震臨時情報」への理解を深め、
いざというときに冷静に行動できるように
しておきましょう。
それでは、
皆さんの防災対策が充実したものになること
を願っています。
次回のブログでお会いしましょう!
参考:
この記事は2025年4月30日時点の
情報をもとに作成しています。
最新の情報については、
内閣府や気象庁のホームページを
ご確認ください。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。