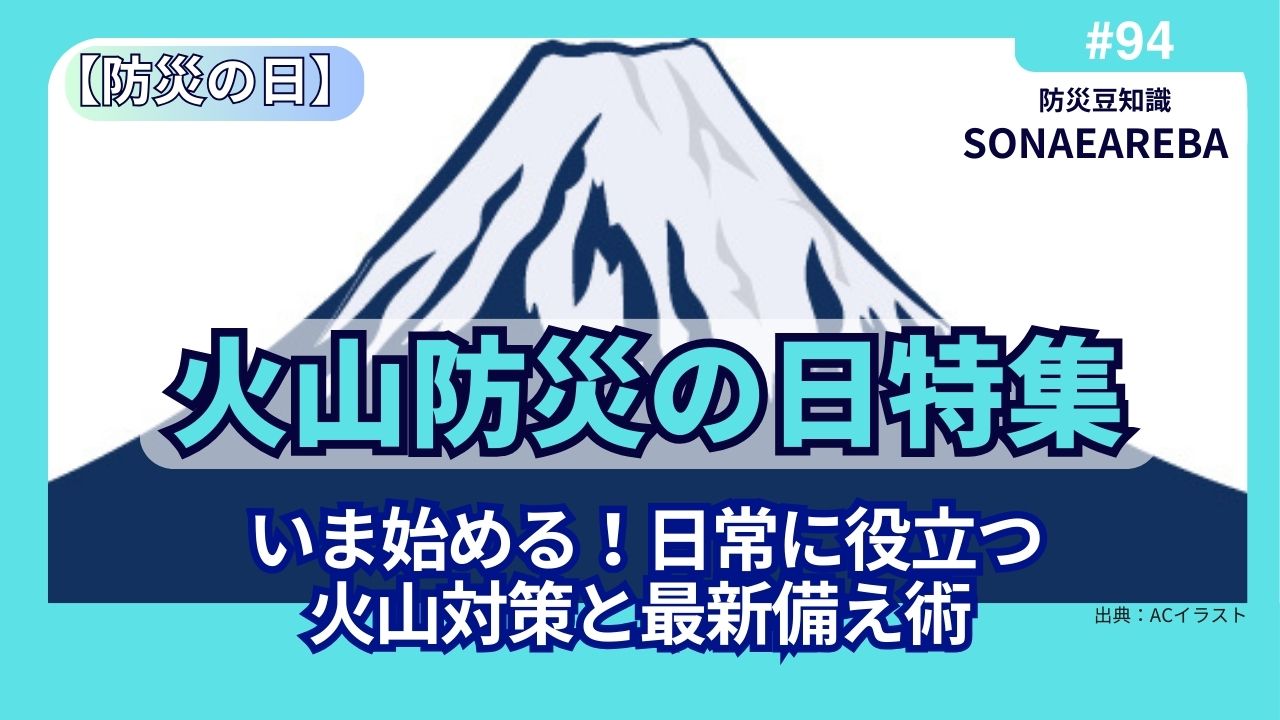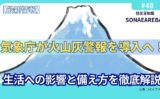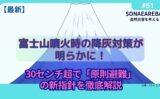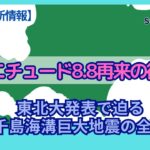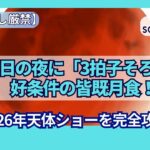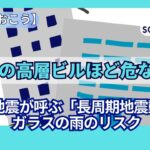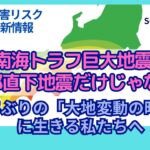この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです
「8月26日は火山防災の日」。
この夏も各地で防災イベントや
情報発信が活発化しているのを
実感しています。
火山は日本列島と深く関わる自然。
そのリスクを知り、
日常の備えを高めることが、
命を守る力に直結します。
火山防災の日とは?
2023年、活動火山対策特別措置法の
一部改正により「8月26日」が
火山防災の日に定められました。
明治44年、この日、
日本初の火山観測所が浅間山に
設置されたことが由来です。
この日は「活火山への理解」と
「防災対策を見直すきっかけ」に向けて、
全国で啓発活動が広がっています。
火山災害のリアル
火山災害は突然、
そして広範囲に影響します。
例えば富士山。
江戸時代の1707年に噴火してから、
300年以上静かな状態ですが、
過去5600年では平均30年に
一度の噴火が記録されています。
最近は防災ハザードマップや
避難計画の改定が進んでおり、
「いつ噴火してもおかしくない」
と専門家も警鐘を鳴らしています。
主な火山災害の影響
- 火山灰の広域降灰
- 溶岩流、火山弾
- 健康被害
(呼吸器・眼への影響) - ライフラインへの打撃
(交通、通信、電力、水道等) - 農作物や建物への損壊・汚染
日常でできる火山防災対策
情報収集とリスク理解
まず、自分が住んでいる地域の
火山リスクを「地図」で
確認するのが第一歩。
自治体のホームページや
ハザードマップ、気象庁の情報を
定期的にチェックしましょう。
特に「噴火警戒レベル」「噴火警報」
「避難対象区域」に関する理解は
命を守る上で重要です。
避難マップ・避難ルートを確認
火山の噴火では避難のタイミングが重要。
自宅や通勤・通学先から「どのルート・
どの時刻」で避難すべきか、
自治体の避難計画を家族やパートナーと
共有しましょう。
最新の富士山避難基本計画では、
徒歩避難が原則とされています。
- 溶岩流:基本徒歩避難(速度が遅い)
- 噴石・火山灰:避難方向・高台を意識
- 車での避難は緊急車両の妨げ、
渋滞のリスクもあるため
押さえておきましょう。
備蓄グッズの用意
火山噴火時、
最も身近な脅威となるのが「火山灰」。
降灰対策として、
最低7日分の食料・飲料水・生活必需品を
家族の人数に応じて備えましょう。
さらに次のグッズも必須です。
- マスク・ゴーグル
(呼吸器、眼の保護) - ヘルメット
- 灰が室内に侵入しないよう隙間を
塞ぐテープ - 灰を集めるためのほうき・塵取り・
スコップ・袋 - 雨具・防寒具
- ラジオ(災害情報の入手)
- モバイルバッテリー
- 常備薬
実際に備蓄しているものを写真に撮り、
家族・知人に共有するのも意識向上に
つながります。
災害時の連絡・集合方法の確認
火山噴火時は
「広域避難」や「分散避難」
の必要性が高まります。
行政からの指示を待たず、
親類宅など安全な場所に早期避難する
自主的行動も推奨されています。
災害伝言ダイヤル、SNS、家族間の
連絡手段も事前に決めておきましょう。
参考リンク:
総務省ホームページ
災害用伝言サービスについて
災害訓練・イベントへの参加
8月26日付近は全国で防災訓練や
イベントが活発に行われています。
地域のイベント情報は自治体・
内閣府の公式サイト、
防災YouTubeチャンネルなど
で発信されているので、
積極的にチェックしましょう。
参加することで自身と家族の防災力が
高まるだけでなく、コミュニティ全体の
防災意識向上にもつながります。
火山防災の最新ガイドライン
2025年3月には
「首都圏広域降灰対策ガイドライン」
が内閣府から公表されるなど、
火山防災は日々進化しています。
参考リンク:
内閣府防災情報
首都圏における広域降灰対策ガイドライン
最新の指針を、自分自身と家族が
しっかり理解し、実践できるよう
定期的にアップデートしましょう。
日常に活きる火山防災
火山防災は「備え」から始まります。
普段の暮らしの延長線上で—
例えば水や食料のローリングストック、
災害情報の確認を習慣化することで、
いざという時に慌てず行動できるように
なります。
- 「火山防災の日」はきっかけ
- 日常の防災習慣が、
命と生活を守る力になる
この一日を、家族やコミュニティで
「防災意識を高めるきっかけ」
にしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
火山は決して遠い存在ではありません。
日常生活のなかで「情報」「備蓄」
「避難経路」「連絡方法」
をいま一度点検し、誰もが自分ごととして
火山防災に取り組むことが、大切な人の
命と未来を守ることにつながります。