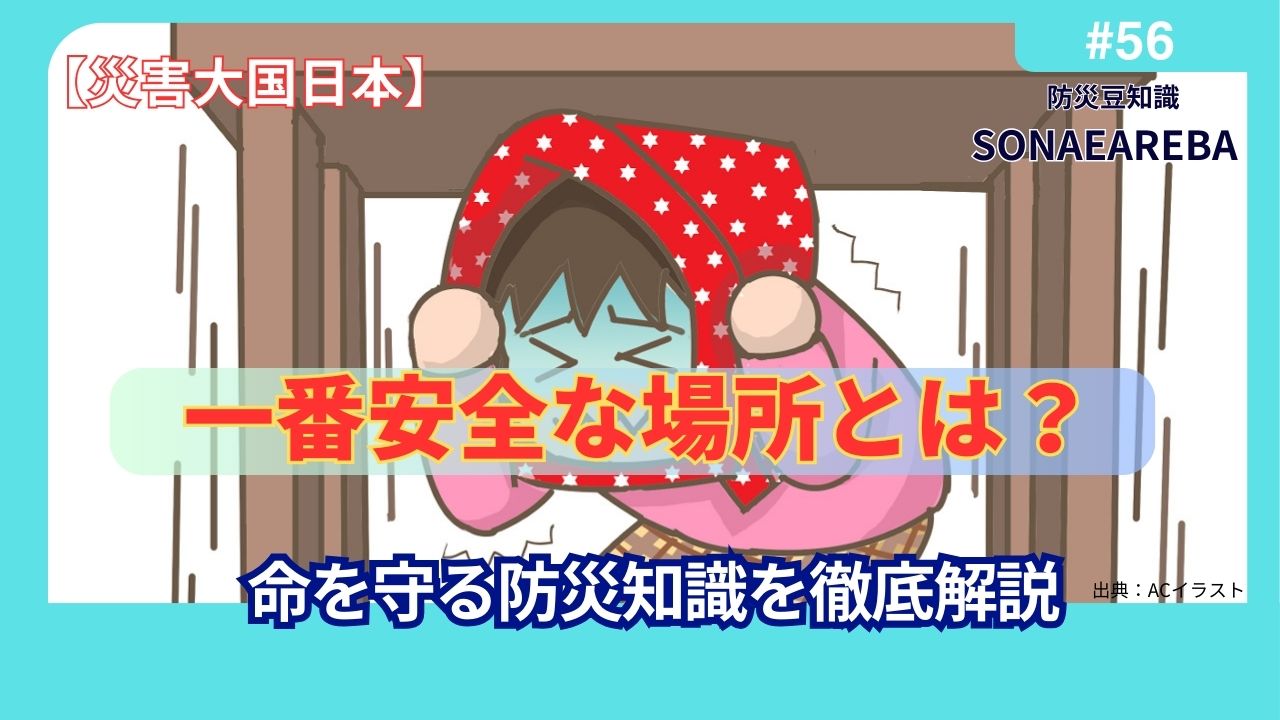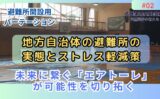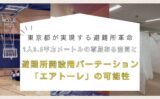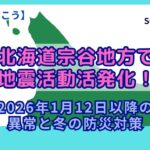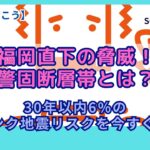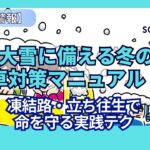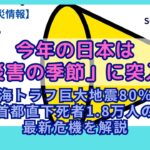この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREBAです。
今回は
「災害大国日本。一番安全な場所とは?」
というテーマの第2弾を書いていきます。
南海トラフ地震の30年間の
発生確率が80%に引き上げられ、
気候変動による水害の頻発など、
日本は今まさに災害の時代
を迎えています。
大切な命を守るためには、
どこが最も安全な場所なのか、
事前に知っておくことが重要です。
本記事では、室内・屋外それぞれの
安全な場所、ハザードマップの活用法、
避難所の重要性について
最新情報をお届けします。
日本の災害リスク最新状況
私たちが住む日本は、
残念ながら世界有数の災害大国です。
地震、台風、豪雨、火山噴火など、
さまざまな自然災害のリスクに
常にさらされています。
特に近年は気候変動の影響もあり、
予測不能な災害が増えています。
政府の地震調査委員会は
南海トラフ巨大地震が今後30年以内に
起きる確率を「80%程度」に引き上げました。
また、
首都直下型地震の発生も懸念されています。
今年の冬には東北地方で災害級の大雪が
発生するなど、全国各地で大規模な災害が
頻発しているのが現状です。
このような状況下で、
石破政権は2026年度中の防災庁設置を
目指すことを表明。
スフィア基準(避難所の満たすべき国際基準)
を踏まえた防災機能の迅速な整備を
進める方針です。
これは「本気の事前防災」として、
災害に対する国の体制を強化する
重要な一歩といえるでしょう。
では、実際に災害が起きたとき、
私たちはどこに身を寄せれば
安全なのでしょうか?
室内と屋外のそれぞれのケースについて
見ていきましょう。
室内にいるとき、最も安全な場所はどこ?
地震などの災害が発生したとき、
室内にいる場合の安全な場所は
主に4つあります。
1. 玄関(強固で逃げ道も確保できる)

玄関は壁が柱に囲まれているため
構造的に強度が高く、
さらに出入口に近いため
逃げ道も確保しやすい場所です。
一般的なリビングなどと比較して、
ガラスの配置が少ないため、
割れたガラスによるケガのリスクも
低減できます。
建物の一部が倒壊したり歪んだりしても、
脱出経路が多いという点も安心です。
2. トイレ(柱・壁に囲まれて強固)

トイレも玄関と同様に、柱や壁に囲まれた
場所なので安全性が高いとされています。
ただし、出入り口が1か所しかないため、
地震でドアが歪むと閉じ込められるリスク
があることには注意が必要です。
3. ユニットバスのお風呂(メーカーによっては耐震性が高い)

ユニットバスは、メーカーによっては
地震時の退避所として設計されています。
ユニットバスはフレームを組んで
壁を組み立てる構造で、
このフレーム自体に耐震性を持たせている
ケースが多いのです。
トイレと同様に、閉じ込められる
リスクには注意が必要です。
4. 柱や壁が多く、窓が少ない場所

総じて言えることは、
「柱・壁に囲まれて強度が高い場所」
「窓ガラスが無い・少ない場所」
が安全だということです。
家の中のどこにいても、
まずは柱や壁の多い方向に逃げ込むこと
が命を守る第一歩になります。
ただし注意すべき点として、
建物自体が倒壊してしまうような
大規模な地震の場合は、
どこに逃げても意味がありません。
そのため、
住宅の耐震化や制震装置の導入など、
建物自体の安全性を高めることが
何よりも重要です。
外出中の災害発生、安全な場所はここ
外出中に災害に遭遇した場合、
どこに身を寄せるべきでしょうか。
外出時は特に上方からの落下物に
注意する必要があります。
1. 耐震性能の高い新しいRC造のビル

外出時に最も信頼できるのは、
耐震性能が確保された
新しい鉄筋コンクリート(RC)造のビルです。
東京都では「東京都耐震マーク」を交付して、
耐震性の高いビルを周知しています。
参考リンク:
東京都耐震ポータルサイト
日頃から行動範囲内にある耐震性の高いビルを
把握しておくことで、地震発生時に素早く身を
守ることができます。
2. 公園や広場など倒壊・落下の心配がない場所

建物の倒壊や落下物の危険がない公園や
広場などのオープンスペースも安全です。
周囲を建物に囲まれている場所では、
落下物によるケガのリスクが高まります。
できるだけ開けた場所に移動しましょう。
絶対に避けるべき危険な場所
災害時に避けるべき危険な場所も
知っておくことが大切です。
室内での危険箇所
- 倒れる心配のある家具・家電の近く:
食器棚やテレビなど倒れやすい家具や
家電の近くは危険です。
地震の揺れで家具が倒れてくると
下敷きになるリスクがあり、
特に食器棚の場合は割れた食器による
ケガの危険も伴います。 - 窓ガラス・建具など割れ物の近く:
地震の揺れによって窓ガラスや鏡などが
割れ、破片でケガをする危険があります。
屋外での危険箇所
- 建物の倒壊が懸念される場所:
古い建物や耐震性の低い建物の近くは
危険です。 - 狭い路地や塀の近く:
ブロック塀や石垣の近くは避けましょう。
過去の地震でもブロック塀の倒壊による
犠牲者が出ています。 - 電柱や看板の近く:
上からの落下物の危険がある場所は
避けるべきです。
ハザードマップを活用して自宅を安全な場所に変える
災害から命を守るためには、
自分の住んでいる地域の災害リスクを
把握することが重要です。
そのための強力なツールが
「ハザードマップ」です。
ハザードマップとは
ハザードマップとは、
災害リスクのある区域や避難場所などを
地図上に示したものです。
多くの自治体では「総合防災マップ」として、
土砂災害、河川洪水、津波など
複数の災害リスクを一冊にまとめています。
たとえば松山市では
「まつやま総合防災マップ」を作成し、
全戸配布しています。
このマップには、
最新の防災情報や指定避難所一覧に加え、
複数のハザード情報が掲載されています。
参考リンク:
松山市役所「まつやま総合防災マップ」
ハザードマップの入手方法
ハザードマップは主に以下の方法で
入手できます:
- 自治体の公式ウェブサイト:
多くの自治体では、防災マップをPDFで
公開しています。 - 市役所や区役所の窓口:
松山市の例では、市役所の危機管理課、
市民課、支所・出張所などで
配布しています。 - 転入時の配布:
新しく引っ越してきた住民向けに
配布している自治体も多いです。
参考リンク:
国土交通省
ハザードマップポータルサイト
身の回りでどんな災害が起こりうるのか、
調べることができます。
ハザードマップを活用した自宅の安全対策
ハザードマップで自宅周辺の災害リスクを
確認したら、具体的な対策を取りましょう:
- 自宅の耐震診断・耐震改修:
地震のリスクが高い地域では、
家屋の倒壊等による圧死を防ぐために
耐震化が重要です。 - 家の周囲の安全チェック:
ブロック塀や屋根瓦、プロパンガスなど
の安全対策を行いましょう。 - 家の防火対策:
住宅用消火器、住宅用火災警報器、
感震ブレーカーなどの設置が効果的です。 - 避難経路の確認:
ハザードマップを見ながら、
自宅から最寄りの避難所までの
安全な経路を確認し、
家族で共有しておきましょう。 - 自宅内の危険箇所対策:
家具の固定や、ガラスの飛散防止フィルム
貼付などを行いましょう。
避難所の重要性と備えるべきこと
大規模災害時には、
自宅での生活が困難になることがあります。
そんなとき頼りになるのが避難所です。
避難所の役割と現状の課題
避難所は被災者の生活を支える
重要な場所ですが、これまでの災害では
生活環境が十分に整っていないケースが
多く見られました。
特に、長期の避難所生活において、
疾病の悪化やストレスによる
肉体・精神的疲労から「災害関連死」が
発生するという課題があります。
熊本地震では建物の崩壊などによる
直接死よりも災害関連死が4倍以上になった
という報告もあり、避難所の環境改善は
重要な課題となっています。
スフィア基準とは
石破政権が推進する「スフィア基準」は、
避難所が満たすべき国際基準です。
これは被災者の尊厳を守り、
最低限の生活環境を確保するための基準で、
十分な居住スペース、清潔な水へのアクセス、
適切な衛生設備、必要な食料の確保などが
含まれています。
日本の避難所をスフィア基準に基づいて
機能強化することで、被災者の健康を守り、
災害関連死を減らすことが期待されています。
避難所生活に備えるべきこと
避難所生活に備えて、
以下のような準備をしておくと安心です:
- 非常用持ち出し袋の準備:
最低限必要なものをすぐに持ち出せるよう
準備しておきましょう。 - 日常備蓄の実践:
災害発生後、数日間は生活必需品が
供給されない可能性があります。
日頃から備蓄を心がけましょう。 - 家族との連絡方法・集合場所の確認:
災害時に家族と連絡が取れなくなった
場合の集合場所や連絡方法を
事前に決めておきましょう。 - 避難所の場所と経路の確認:
自宅から最寄りの避難所までの
安全な経路を複数確認しておきましょう。 - 防災訓練への参加:
地域の防災訓練に参加することで、
実際の避難行動をシミュレーション
できます。
家族で取り組む防災対策
災害から家族を守るためには、
家族全員が防災について話し合い、
協力することが大切です。
家族防災会議のすすめ
家族防災会議では、
以下のような内容について
話し合いましょう:
- 家の中で安全な場所はどこか
- 応急手当の知識を身につける
- 消火器具などの安全点検
- 火気器具などの安全点検
- 避難場所、避難道路の確認
- 家族の役割分担
- 万が一の際の家族との連絡方法・集合場所
- 非常持ち出し品の点検、置き場所の確認
マイ・タイムラインの作成
マイ・タイムラインとは、
災害に備えて自分や家族がとるべき防災行動を
時系列的に整理したものです。
防災マップや各種ハザードマップで
自宅周辺の災害リスクを確認し、
いざというときのために避難先や避難行動を
あらかじめ決めておきましょう。
参考リンク:
国土交通省「マイ・タイムライン」
防災訓練への参加
いざという時に備えて、
普段から隣近所との協力体制を
作っておくことも重要です。
地域の防災市民組織への参加や防災訓練への
参加を通じて、共助の意識を高めましょう。
災害情報へのアクセスを確保する
災害時には正確な情報へのアクセスが
命を救います。
特に地方自治体の災害関連ページは
貴重な情報源ですが、アクセス集中で
サイトが閲覧できなくなることがあります。
災害情報サイトのアクセス集中対策
台風などの災害時、多くの人が情報を求めて
地方自治体のサイトにアクセスすることで、
サイトの反応が遅くなったり閲覧できなく
なったりする問題が発生しています。
こうした問題に対応するため、
サーバーやネットワークの増強や
CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の
利用が効果的ですが、地方自治体の予算では
実現が難しい場合があります。
近年では、ページをAMP化することで、
グーグルのCDNを無料で利用できる方法も
注目されています。
これにより、情報を探す人のアクセスを
グーグルのCDNで受け止めることができ、
アクセス急増に耐えやすくなります。
信頼できる災害情報源の確認
日頃から以下のような信頼できる情報源を
チェックしておきましょう:
- 地方自治体の防災ページ:
自分の住んでいる自治体の防災ページを
ブックマークしておく - 気象庁ウェブサイト:
気象警報や地震情報を確認できる - NHKなどの公共放送:
災害時には正確な情報を提供している - 防災アプリ:
地域の防災情報を通知してくれる
アプリを活用する
まとめ:今すぐできる防災対策3つ
今回は災害大国日本において、
安全な場所についてお伝えしてきました。
最後に、
今すぐ取り組める防災対策をご紹介します。
1. 自宅の安全チェックを行う
自宅内の安全な場所
(玄関、トイレ、ユニットバス、柱や壁)
と危険な場所(家具や窓ガラスの近く)
を確認し、家族と共有しましょう。
また、家具の固定や耐震対策を
検討してください。
2. ハザードマップで自宅周辺の災害リスクを確認する
お住まいの自治体のハザードマップを入手し、
自宅周辺の災害リスクを把握しましょう。
それに基づいて、安全な避難経路や避難所を
確認してください。
3. 非常用持ち出し袋を準備する
災害発生後、数日間は生きていくために
必要なものが供給されない可能性があります。
災害発生後の72時間(3日間)は、
人命救助の「デッドライン」
または「72時間の壁」と呼ばれ、
人命救助が最優先されるためです。
非常用持ち出し袋を準備し、
置き場所も家族で共有しておきましょう。
災害はいつどこで起きるかわかりません。
しかし、事前の知識と準備があれば、
被害を最小限に抑えることができます。
この記事が皆さんの防災意識を高め、
大切な人の命を守るきっかけになれば
嬉しいです。
次回の記事もお楽しみに!
SONAEAREBAでした。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。