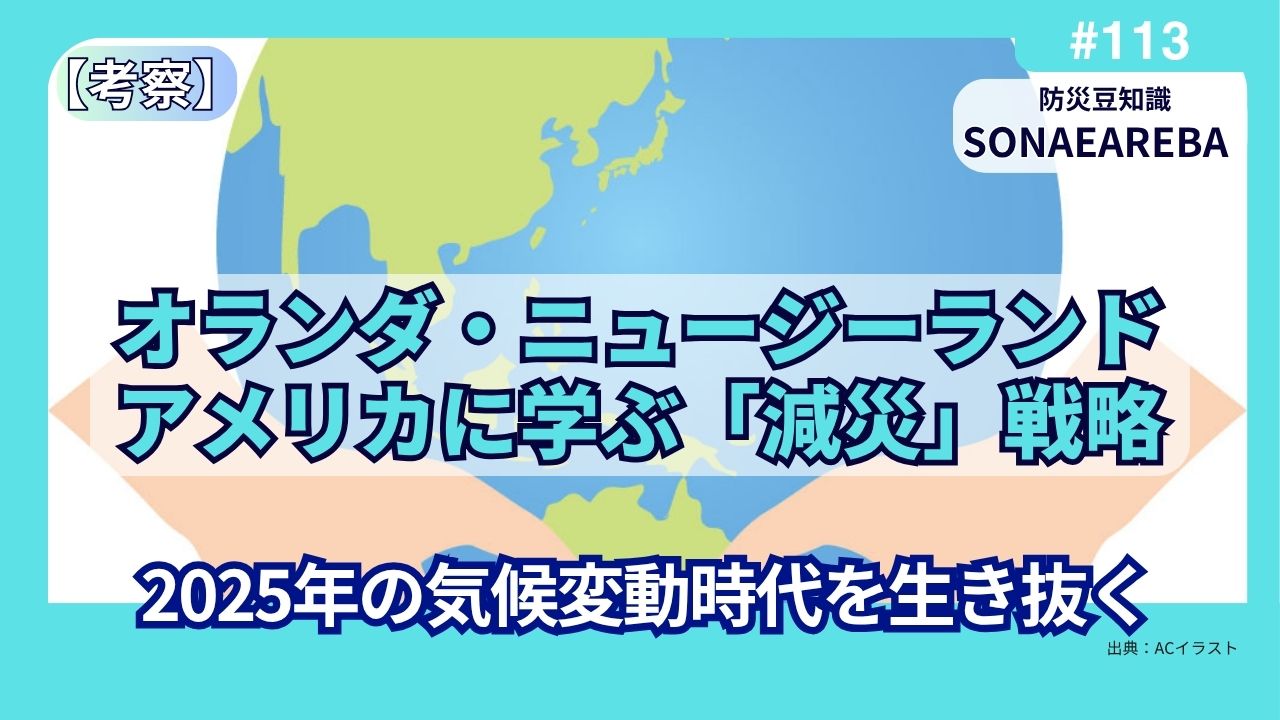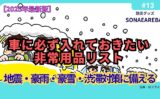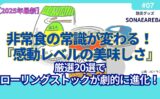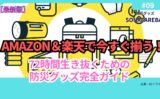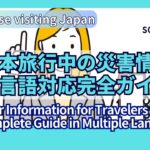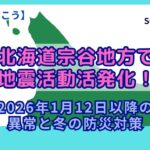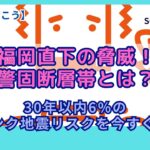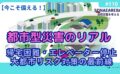この記事は広告を使用しています
こんにちは!SONAEAREAです。
私は日々、
世界中の防災政策を調査しながら、
災害に強い社会づくりについて
考えています。
今回のテーマは
世界の防災政策に学ぶ
『減災』の考え方です。
気候変動が加速する現代において、
完全に災害を防ぐことは
難しくなっています。
だからこそ、
多くの先進国が採用している「減災」と
いう考え方が重要になっているのです。
この記事では、国連が推進する
「仙台防災枠組2015-2030」を基軸に、
オランダ、ニュージーランド、アメリカ、
インドネシアなど、世界各国の先進的な
防災政策から学べることをお伝えします。
「減災」とは何か:日本の経験から世界へ
2011年の東日本大震災は、
日本の防災思想を大きく変えました。
この災害を経験した日本は、
翌2015年の第3回国連防災世界会議を
仙台で開催し、国際的な防災指針
「仙台防災枠組2015-2030」
を採択したのです。
参考リンク:
仙台市役所 ホームページ
「仙台防災枠組」推進に向けた取り組み
「減災」という考え方の核心は、
シンプルながら深い意味を持っています。
それは「災害そのものを完全には防ぐこと
はできないかもしれないが、その被害を最
小化することはできる」という認識です。
従来の防災対策は、堤防や防波堤などの
インフラ整備に重点を置いていました。
しかし、東日本大震災で想定を超える
津波が襲来したことで、この考え方に
限界があることが明らかになりました。
そこで日本が打ち出したのが
「ハード・ソフト施策の適切な組み合わ
せ」という新しいアプローチです。
具体的には、堤防などの構造物(ハード)
だけに頼るのではなく、
早期警戒システム、避難訓練、防災教育、
そして正確で迅速な情報発信(ソフト)
を組み合わせることで、人命と地域を
守ろうとするものです。
世界が注目する「仙台防災枠組2015-2030」
2030年までの国際的な防災指針として
世界が取り組む「仙台防災枠組」には、
7つの具体的なグローバルターゲット
が設定されています。
2030年までに達成すべき成果としては:
- 災害時の死亡者数を大幅に削減する
- 被災者数を大幅に削減する
- 直接経済損失をGDP比で削減する
- 重要インフラへの損害を大幅に減らす
- 国家・地方レベルの防災戦略を有する
国を増やす - 開発途上国への国際協力を強化する
- 多くの人が早期警戒システムや災害
リスク情報を利用できるようにする
これらの目標は単なる数値目標ではなく、
世界中の人々が「より安全で強靭な社会」を作るための共通言語として
機能しています。
現在、多くの国がこの枠組みに沿って
防災戦略を策定し、実行しているのです。
参考リンク:
国際連合情報センター
国連防災機関(UNDRR)神戸事務所
オランダの治水戦略:「河川に余裕を持たせる」発想
国土の約1/4が海面より低いオランダは、
水害対策の先進国として知られています。
1953年の北海大洪水で2,000人以上の
犠牲者を出した経験から、オランダは
抜本的な治水政策へと転換しました。
オランダの取り組みで特に注目すべきは
「Room for the River
(河川に余裕を持たせる)」
というプロジェクトです。
従来の治水対策では、
増水時に堤防で水をせき止めることに
重点を置いていました。
しかし、オランダが採用したのは、
河川周辺に水が流れ込むための空間を
意図的に確保するという逆転の発想です。
この施策により、
洪水が発生しても河川の水位上昇を
抑制でき、結果として堤防への
負荷を軽減させることができます。
つまり、「水と共生する」という
減災の考え方を体現した対策なのです。
さらに注目すべきは、
オランダ政府が市民向けに提供する
「浸水するの?(Overstroom ik?)」
というアプリです。
住所を入力するだけで、
想定される最悪の洪水シナリオにおいて
自宅がどの程度浸水する可能性があるか、
また浸水を経験する確率はどのくらい
あるのかを知ることができます。
これは気候変動適応の重要性を
市民レベルで共有する優れた例です。
防災は行政だけの責任ではなく、
市民が自分たちのリスクを理解し、
適応する必要があるという姿勢が
感じられます。
さらに、オランダは2050年までに
気候変動への耐性を持ち、水に関して
頑健な国へと進歩することを目指す
「デルタプログラム」も推進しており、
堤防や水門の大規模改修、
淡水供給の確保、地域の気候耐性強化に
取り組んでいます。
ニュージーランドの多層的アプローチ:建築基準から教育まで
太平洋に位置するニュージーランドは、
地震、洪水、土砂崩れ、津波、火山活動
など、多様な自然災害の脅威に
さらされている国です。
同国の防災対策は
「建築基準、緊急対応、教育の3本柱」
で構成されています。
ニュージーランドが採用している耐震基準
は、世界的に見ても最高レベルです。
1931年のホーキンガ地震による
甚大な被害をきっかけに、同国は高い
耐震基準の導入を決断しました。
その後、1965年、2004年と段階的に
基準を強化してきた結果、新築建物には
極めて高い耐震性能が求められるように
なったのです。
同国の防災教育も充実しています。
学校では地震ドリルが定期的に行われ、
市民に対しても地震対策の啓発活動が
継続的に実施されています。
さらに、ニュージーランド政府は
災害情報を得るためのウェブサイトや
ラジオ局との連携体制を整備し、
緊急時の情報発信体制を
強化しているのです。
近年、ニュージーランドでは
2016年のカイコウラ地震や
2023年のサイクロン「ガブリエル」
による洪水・土砂崩れなど、
自然災害が多発しており、
市民向けの防災備蓄リストや
ハザードマップの整備も
推進されています。
アメリカ:ハリケーン・カトリナから学んだシステム全体の再構築
2005年8月にルイジアナ州を襲った
ハリケーン・カトリナは、1,500人以上の
犠牲者を出し、米国史上最大級の自然災害
となりました。
しかし、この悲劇がもたらしたものは、
アメリカの防災システムの抜本的な改革
でもあったのです。
カトリナの直後、米国陸軍工兵隊は
タスクフォース「Guardian」を
立ち上げ、50以上の機関から150人以上の
専門家を動員して、ニューオーリンズの
洪水防御システムの問題を
科学的に分析しました。
その結果、
基礎から壊れた堤防だけでなく、
越流による浸食も洪水被害を
拡大させていることが判明したのです。
この教訓から、米国は新しい
「ハリケーン・暴風雨被害リスク削減
システム(HSDRS)」を構築しました。
重要なのは、単に堤防を嵩上げして
修復するのではなく、
152通りの異なるハリケーンシナリオを
想定し、それぞれに対応できるシステムを
設計したという点です。
さらに、排水ポンプ場の管理体制も
改革されました。
カトリナ時には、操作員の避難、
電源の喪失、冷却水の不足などにより、
ポンプ場が十分に機能しませんでした。
この教訓から、陸軍工兵隊が主要電源を
水から守り、バックアップ電源を備えて、
管理要員が安全に操作できる
環境を整備したのです。
アメリカの対応は「予測に基づいた適応」
という減災の考え方を完璧に実行した
例といえます。
インドネシア:多部門連携による総合的防災体制の構築
インドネシアは
地震、津波、火山噴火、洪水など、
アジア有数の自然災害多発国です。
同国の防災担当機関である
国家防災庁(BNPB)は、2025年度に
1兆8,870億ルピア(約170億円)の予算
を計上し、防災強化に注力しています。
特に注目すべきは、
インドネシアが「マルチセクター
(多部門)による災害対応ネットワーク」
の構築に取り組んでいる点です。
政府機関だけでなく、
民間企業や地域コミュニティ、
国際機関が連携し、災害リスクを
削減しようとしているのです。
同国では地域防災局(BPBD)が各地域に
配置され、早期警報システムの構築、
ハザードマップの作成、災害に強い村
プログラムの推進などを実施しています。
さらに、インドネシアは日本の技術協力を
受けながら、地震・津波観測及び情報発信
能力の向上に取り組んでいます。
気候変動時代の新しい防災パラダイム
2025年3月に日本の文部科学省と気象庁は
「日本の気候変動2025」
を公表しました。
この報告書によれば、
世界の極端な高温(熱波を含む)は
頻度だけでなく強度が増加しており、
大雨、台風、熱波などの
極端気象現象がさらに激化する可能性が
指摘されています。
参考リンク:
気象庁ホームページ
『日本の気候変動2025』
こうした状況下において、
従来の「標準的な災害」を想定した
防災計画では対応が難しくなっています。
そこで各国が採用しているのが
「気候変動を踏まえた適応的防災戦略」
です。
これは単に防災インフラを強化する
だけでなく、気候変動の影響を先読みし、
社会全体のシステムを柔軟に変えていく
必要があるという認識に基づいています。
環境省が作成した
「気候変動×防災実践マニュアル」
においても、気候変動リスクを踏まえた
抜本的な防災・減災対策の必要性が
強調されています。
参考リンク:
環境省ホームページ
できることから始める「気候変動×防災」
実践マニュアル -地域における気候変動
リスクを踏まえた防災・減災対策のために
私たちが実践できる「減災」
記事をお読みになって、皆さんは
「防災・減災は行政や大規模プロジェクト
の問題では?」と感じるかもしれません。
しかし、仙台防災枠組の重要な側面は、
「すべてのステークホルダーが
関わることが必要」という認識なのです。
個人レベルで
実践できる減災対策としては:
- ハザードマップの確認:
自分が暮らす地域にどのような
災害リスクがあるのかを把握する - 防災備蓄:
最低3日分の食料、水、医薬品などを
準備する
- 避難経路の確認:
いざという時の避難場所や経路を
家族で話し合う - 防災訓練への参加:
地域の防災訓練に積極的に参加し、
実際の対応を体験する - 防災情報のアクセス:
気象情報や災害情報を日頃から
チェックする習慣をつける
これらは一見、地味な取り組みに
見えるかもしれません。
しかし、各自が自分のリスクを理解し、
準備することが、結果として地域全体の
強靭性(レジリエンス)を高めるのです。
世界から学び、地域で実践する
世界の防災政策から学べることは、
「災害と完全に戦う」のではなく、
「災害と共生し、被害を最小化する」
ことの大切さです。
オランダの「河川に余裕を持たせる」
という発想、
ニュージーランドの「多層的防御」、
アメリカの「シナリオベースの計画」、
インドネシアの「多部門連携」
これらはすべて、
「想定を超える
災害にも対応できるシステム」
を目指しています。
現在、世界は仙台防災枠組の折り返し
地点を越えようとしています。
2025年は、
各国がこれまでの取り組みを評価し、
新たな戦略を策定する年になります。
皆さんが暮らす地域でも、
こうした国際的な防災哲学が
少しずつ浸透し始めています。
自分たちの地域にどのような防災政策が
あるのか、どのような取り組みが
行われているのかに関心を持つことから、
「減災社会」への歩みが始まるのです。
私たちSONAEAREAは、
今後も世界の先進的な防災事例を
お伝えし、皆さんが一歩先を行く
防災対策を実践できるよう
お手伝いしたいと考えています。
次回のテーマもお楽しみに。
皆さんの「もしもに備える」
を応援しています。
バックの中に、あるという「安心」を。
通信障害時に役立つワイドFMラジオ付き
「空間にマスクする感覚」
地方自治体避難所開設用パーテーション