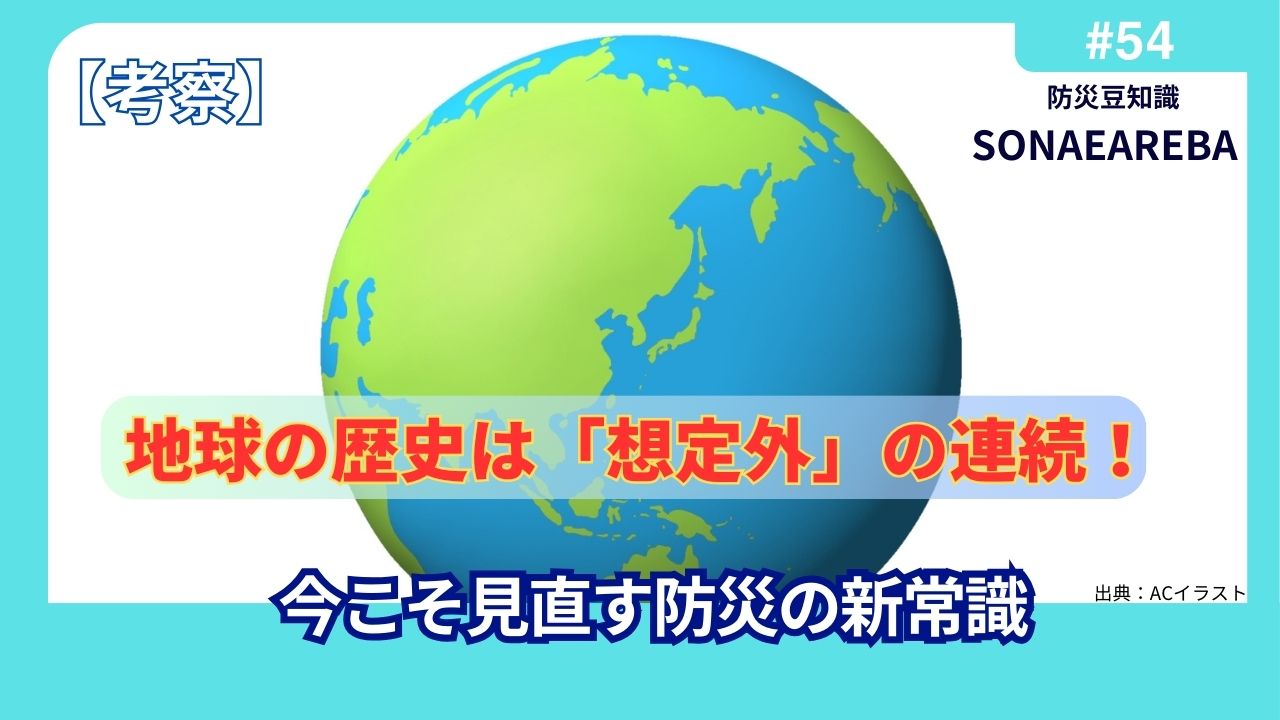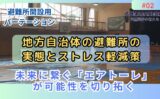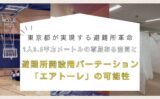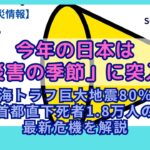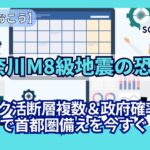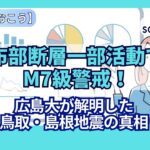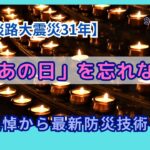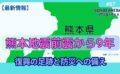この記事は広告を使用しています
防災視点から考える。地球の歴史は「想定外」の繰り返し
こんにちは!SONAEAREBAです。
私たちは「想定外」という言葉を、
特に大きな災害が発生した後に
よく耳にします。
2011年の東日本大震災では、
それまでの防災対策の想定を超える規模の
津波が発生し、多くの人命が失われました。
しかし、地球の歴史を紐解くと、
実はこの「想定外」という現象は
繰り返し起きており、
私たちの想定の範囲を超える自然現象が
常に存在していることがわかります。
今回は防災の視点から「想定外」に
ついて考え、私たちにできる準備に
ついて探っていきたいと思います。
「想定外」とは何か?その本質と問題点
「想定外」という言葉は、
単に「予想していなかった」
という意味ではありません。
防災の文脈では、
「科学的に予測可能であったにもかかわらず、
対策上考慮されていなかった事象」
を指すことが多いのです。
日本学術会議が2007年に発表した答申では、
当時の防災体制に懸念を示し、
短期的経済重視の姿勢から長期的安全確保を
最優先とする方向への「パラダイム変換」の
必要性を訴えていました。
この懸念は2011年の東日本大震災で
現実となり、そして2019年からのコロナ禍
でも同様の問題に直面することになりました。
予測と想定の違い
防災において「予測」と「想定」は
区別すべき重要な概念です。
「予測」の説明責任は科学にあり、
「想定」の判断責任は行政にあるとも
言われます。
東日本大震災を例に考えてみると、
日本海溝ではM9の地震が起きにくいとする
「比較沈み帯モデル」が重視されていました。
しかし、2002年に地震本部は、
福島県沖でもM8が起こらないと考える
理由はないとして調査を進め、
2011年2月には大津波500年周期説を
まとめていました。
つまり、
科学的な「予測」はあったものの、
防災対策上の「想定」には
組み込まれていなかったのです。
「想定外」が生じる主な要因
- 経験の浅さ:
私たち人間の経験はたかだか
二、三世代の間の経験でしかありません。
一方、ある特定の山腹や渓流において
大規模崩壊や土石流が発生するのは数百年
あるいは数千年に一度という程度です。
この時間スケールのギャップが
「想定外」を生み出します。 - 気候変動:
地球温暖化などによる気候変動によって
想定外の気象現象が発生する可能性が
あります。 - 社会の変化:
開発あるいは土地放棄による土地利用の
変化など、私たちの社会の変化も
「想定外」の災害を引き起こす要因と
なります。 - 半世紀の経験に依存:
近年の防災対策は、半世紀の経験しかない
科学技術の知見のみに頼ってきました。
一方で私たちと自然との付き合いは
農耕社会になってからでも2000年を
超えており、地域の経験こそ50年間の
科学技術より確実な部分もあるのです。
歴史に学ぶ「想定外」の災害事例
歴史を振り返ると、
「想定外」と言われた大規模災害は
数多く存在します。
これらの事例から学ぶことで、
今後の防災対策に活かすことが
できるでしょう。
東日本大震災と津波の教訓
東日本大震災を引き起こした地震と津波は、
発生直後には「予測不能」として
扱われましたが、
実際には対策上の「想定外」でした。
これにより回復不能な原発事故や、
多くの人命を失う結果を招いたというのが
東日本大震災の本質です。
歴史記録や観測記録などの直接証拠がない
地震・津波は防災対策に活かされにくい傾向
があります。
自然地理学が提示する古地震や活断層は
間接証拠として扱われます。
間接証拠をどこまで重視するかは法的にも
明確ではありません。
過去の土砂災害から見る「想定外」
普段から防災を意識していない
多くの人々にとって土砂災害は
ほとんど想定外の災害になってしまいます。
これは激甚土砂災害の重要な特徴の一つ
として理解しておく必要があります。
このような状況から、
砂防の世界では以前からソフト対策、
とりわけ警戒・避難の重要性を
強調してきたのです。
土砂災害、洪水氾濫、津波などのほか、
山林火災、豪雪、高潮、竜巻なども
含めて、予知・予測技術のさらなる向上
とともに、想定外を十分意識した
「防災施設の設置と警戒・避難対策」
の充実が今後の基本方針となるでしょう。
防災視点で考える「想定外」への備え方
「想定外」の災害に備えるためには、
科学的知見と地域の経験知を組み合わせた
総合的なアプローチが必要です。
科学的予測の限界を認識する
防災において重要なのは、
科学的予測には限界があることを認識し、
間接証拠も含めた多角的な視点で
災害リスクを評価することです。
日本海溝沿いに多くの海底活断層が
分布することが明らかになっていますが、
これらは過去の地震の痕跡であることは
間違いありません。
こうした情報を地震ハザード評価に
どれだけ活かせるかは地理学者の
専門的知見が必要になります。
「既往最大」の考え方を見直す
「想定」の基本は「既往最大」です。
地震直後には「理論上最大」まで考慮すべき
という議論がありましたが、
その必要性と妥当性には疑問があります。
今一度基本は「既往最大」として、
それをどう決めるかを整理すべきでしょう。
従来通り、直接証拠があり否定しがたいもの
だけを「既往最大」とするのではなく、
間接証拠から可能性が高いと判断される事象
までを既往最大とすべきではないでしょうか。
経済との相克のなかで、
明確な答えを出すハードルは高いかも
しれませんが、検討に値する視点です。
防災の正攻法を機能させる
近年、行政における防災の道筋はある程度
明確になってきました。
①ハザードマップを作り、
②自らの危険性を知り、
③対応を考え、
④適切な行動をする、
というのは防災の正攻法です。
しかし、重要なことはそれぞれの段階が
しっかり機能しているかを点検することです。
形だけの対策ではなく、実効性のある防災体制
を構築する必要があります。
家庭でできる防災対策:「想定外」に備える
家庭レベルでも「想定外」の事態に
備えることができます。
以下に具体的な方法をご紹介します。
子供と一緒に行う防災準備
子供への防災教育は、
次世代の防災意識を高める上で
非常に重要です。
家庭で実践できる具体的な取り組みには
以下のようなものがあります:
- 避難経路と集合場所の確認:
家族全員で避難経路や集合場所を
確認しましょう。
地震や火災など、災害ごとに異なる行動が
必要になるため、それぞれの場合を想定
して話し合うことが大切です。 - 非常持ち出し袋を一緒に準備する:
子供と一緒に非常持ち出し袋を準備する
ことで、防災意識が高まります。
「なぜこのアイテムが必要なのか」
を話し合いながら準備すると、
子供も理解しやすくなります。 - ゲームや遊びを活用する:
防災ゲームやクイズ形式の学習は、
子供が楽しみながら学べる方法です。
例えば、「ぼうさいすごろく」や
「防災かるた」などがおすすめです。 - 災害時の行動をシミュレーション:
地震が発生した際にどう行動すべきか、
具体的なシミュレーションを
行いましょう。
「まず低く」「頭を守り」「動かない」
といった基本動作を実践することで、
緊急時にも冷静に対応できるように
なります。
日常生活に防災を取り入れる
普段から防災について話し合う機会を
作りましょう。
例えば、ニュースで地震が報じられた際に
「私たちならどうする?」
と問いかけてみると良いでしょう。
また、室内キャンプや停電時を想定した
一晩電気を使わずに食事から就寝までの
生活体験など、「もしも」を想定した遊びを
通じて学ぶ方法も効果的です。
これにより、子供たちはより実感を持って
防災について考えるようになります。
インバウンド時代の防災対策
近年、訪日観光客が増加していることから、
災害時の外国人対応も重要な課題と
なっています。
観光庁のデータによると、
2024年にはコロナ禍からの回復もあり、
多くの外国人が日本を訪れています。
日本は地震や台風などの自然災害が
多い国であり、観光客が増えるということは、
災害が起きたときにその人たちを
どう支援するかも考えなければなりません。
地域住民として、また家族として、
災害時に外国人をどのように支援できるか
考えておくことも、現代の防災対策として
重要な視点です。
多言語での避難情報の提供や、
外国人にもわかりやすい避難誘導サインの
整備などが求められています。
最新の防災技術と研究
防災の分野では、日々新しい技術や
研究が進んでいます。
これらの最新情報を知ることで、
より効果的な防災対策を講じることが
できるでしょう。
デジタル技術の活用
急速に進化するデジタル技術は、
都市の計画や管理に革命をもたらしています。
国土交通省では都市の3Dデータを活用し、
都市の持続可能な発展と市民の生活の質を
向上させるための「Project PLATEAU」を
推進しています。
参考リンク:
国土交通省
都市空間情報デジタル基盤構築支援事業
「Project PLATEAU」
このプロジェクトでは、
都市の3Dデータを活用して、
水害シミュレーションや避難計画の策定など、
防災に関する様々な取り組みが
行われています。
防災士の活躍
自然災害のリスクが高まる昨今、
地域の防災力向上の一環として
注目されているのが「防災士」の存在です。
防災士は、地域の防災活動をリードする
専門資格であり、その取得を支援する
助成制度が各地で導入されています。
防災士の資格を取得することで、
地域の防災リーダーとして活躍することが
期待されています。
自治体によっては防災士資格取得の助成制度
も設けられているので、興味のある方は
調べてみるとよいでしょう。
参考リンク:
日本防災士機構
自治体による資格取得への助成
防災キャンプの取り組み
「楽しく備える」「楽しみながら備える」
をテーマに、
災害時でも「生き抜く力」「生きる力」
を養うための防災キャンププログラムが
注目されています。
例えば、災害時にも役立つロープワークの
活用法をキャンプで楽しく実践しながら
習得する方法などが紹介されています。
楽しみながら実用的なスキルを
身につけることで、防災への意識を
自然と高めることができるのです。
参考リンク:
一般社団法人日本防災キャンプアウトドア協会
災害時のアウトドアスキル防災キャンプ体験
防災における「想定外」を減らすための提言
「想定外」の災害を完全になくすことは
難しいかもしれませんが、
その影響を最小限に抑えるための
取り組みはできます。
以下に、防災の視点から「想定外」を
減らすための提言をまとめます。
科学と社会の相克を解消する
いま求められることは、俯瞰的な点検です。
短期的経済中心の価値観からの
パラダイムシフトを遂げることも重要であり、
それに貢献できる防災教育に対して
地理学は責任を持っています。
科学的な予測と社会的な想定のギャップを
埋めるためには、科学者と政策決定者、
そして市民との対話が不可欠です。
科学的知見を適切に政策に反映させる
仕組みづくりが求められています。
防災教育の充実
防災教育は、
「想定外」の災害に対応するための
重要な取り組みです。
家庭での防災教育に加え、
学校や地域コミュニティでの防災教育も
充実させる必要があります。
特に、過去の災害事例から学ぶことで、
将来起こりうる災害への備えを
強化することができます。
歴史的な災害の記録を保存し、
次世代に伝えていくことも
重要な防災教育の一環と言えるでしょう。
地域の知恵を活かす
近年の激甚災害の多発を思うと、
防災対策を半世紀の経験しかない科学技術の
知見のみに頼ってきたのが誤りだったのかも
しれません。
一方で私たちと自然との付き合いは
農耕社会になってからでも2000年を超えます。
その間の知見を積み重ねた地域の経験こそ
50年間の科学技術より確実な部分も
あるでしょう。
地域に伝わる災害の記憶や対処法を
掘り起こし、現代の防災対策に活かす
取り組みを進めることが大切です。
まとめ:「想定外」に備えるための心構え
地球の歴史は「想定外」の繰り返しであり、
私たちの想定を超える自然現象は
今後も発生する可能性があります。
しかし、
過去の災害から学び、科学的知見と
地域の経験知を組み合わせることで、
「想定外」の影響を最小限に
抑えることができるのです。
防災対策の基本は、
①ハザードマップを作り、
②自らの危険性を知り、
③対応を考え、
④適切な行動をすることです。
この流れが確実に機能するよう、
日頃から点検と改善を行うことが大切です。
家庭では、
子供と一緒に避難経路の確認や
非常持ち出し袋の準備を行い、
日常生活の中に防災の視点を
取り入れることで、
「想定外」の事態にも対応できる力
を養うことができます。
最後に、防災は特別なことではなく、
日常生活の延長線上にあるものです。
「考える」「話し合う」「行動する」
というプロセスを繰り返すことで、
防災意識が自然と身につきます。
この記事が皆さんの防災意識を高め、
「想定外」の災害に備える
きっかけとなれば幸いです。
「想定外」は必ずしも「予測不能」ではなく、
適切な「想定」と「準備」によって、
その影響を最小限に抑えることができる
のです。
日々の備えが、いざというときの
大きな力になることを忘れないでください。
今日から始められる防災対策で、
大切な人の命と暮らしを守りましょう。
地方自治体避難所開設用パーテーション
ダンボールやテントではない「新しい空間」
「エアトーレ」は日本の避難所を変えます。
バックの中に、あるという「安心」を。