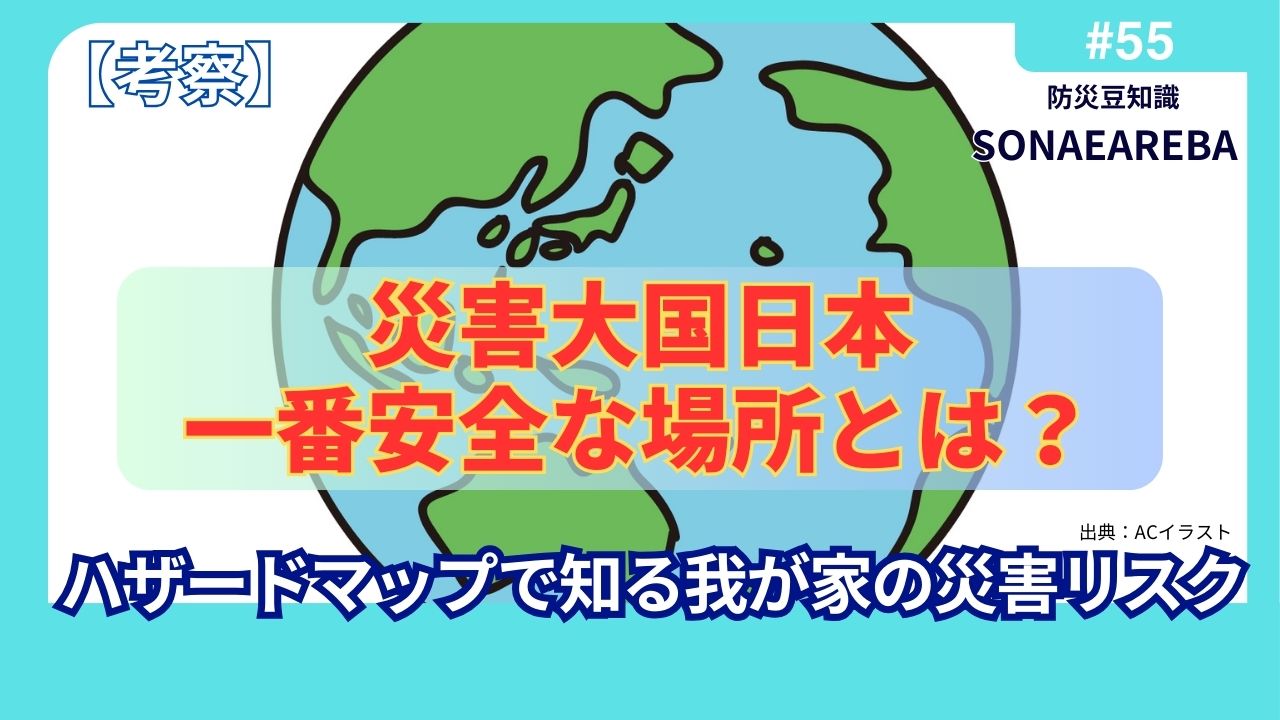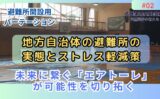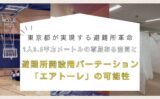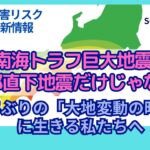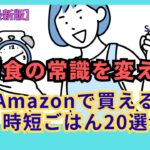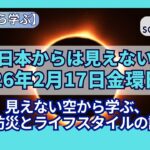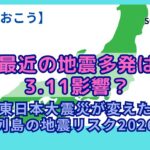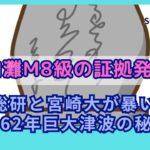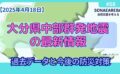本記事はAmazonアソシエイトとして、
商品を紹介して収益を得る可能性があります。
こんにちは!SONAEAREBAです。
今回は
「災害大国日本。一番安全な場所とは?」
というテーマで記事にしていきます。
地震、台風、洪水、土砂災害…
次々と日本を襲う自然災害。
「本当に安全な場所はどこにあるのだろう?」
と考えたことはありませんか?
私自身、
防災について調べれば調べるほど、
もし、引っ越せるならば日本のどこに
住むべきか悩むようになりました。
でも、
結論からいうと「絶対に安全な場所」
は実は存在しないんです。
それでも、
比較的災害リスクの低い地域や、
自分の住む場所をより安全にする
方法はあります。
今回はそんな「災害に強い場所」の特徴と、
どこに住んでいても役立つ防災情報を
2回にわたってお届けします。
日本が抱える災害リスクの現状
日本は四方を海に囲まれた島国であり、
環太平洋火山帯に位置しているため、
地震や火山活動が活発です。
また、台風の通り道にもあたり、
近年は気候変動の影響で豪雨災害も
増加傾向にあります。
特に2024年能登半島地震では、
住宅・建築物・漁港や土木インフラに
甚大な被害をもたらしました。
一方で、これまで進めてきた
耐震対策などが一定の効果を発揮した
という側面もあります。
1995年の阪神・淡路大震災以降に強化された
耐震基準で新設・補強された木造住宅や
道路橋梁などには、ほぼ被害がなかったこと
が報告されています。
日本政府も国土強靱化基本法の改正など、
災害対策を強化していますが、
完全に安全な場所というのは難しい問題です。
なぜなら、災害の種類や発生リスクは
地域によって異なるため、
絶対的に安全な場所は存在しません。
では、相対的に見て災害リスクの
低い地域はどこなのでしょうか?
災害種類別・最もリスクの低い地域ランキング
自然災害と一言で言っても、
地震、台風、豪雨など様々な種類があります。
まずは災害種類別に、
リスクの低い地域を見ていきましょう。
参考リンク:
Jackery Japan
日本で一番災害が少ない県ランキング
地震の発生が少ない都道府県ランキング
地震の発生回数が少ない都道府県を
ランキング形式で見ていきます。
| 都道府県 | 発生回数 |
|---|---|
| 1位:佐賀県 | 5回 |
| 2位:鳥取県 | 9回 |
| 3位:福岡県 | 10回 |
| 4位:滋賀県、奈良県 | 11回 |
| 5位:富山県、京都府 | 15回 |
| 6位:三重県、山口県 | 16回 |
| 7位:大阪府 | 17回 |
※2023年のデータです
参考リンク:
気象庁 観測地点別震度観測回数表
興味深いのは、
上位がほとんど西日本であることです。
これは地理的な要因によるものです。
日本の地下では、プレートと呼ばれる
4枚の岩盤が押し合っており、
プレートの活動によって地震が発生します。
4枚のプレートのうち、
北米・太平洋・フィリピン海の
3枚のプレートが日本の東側に
集中しているため、地震の頻度が
偏っているのです。
台風の接近が少ない地方ランキング
続いて、台風の接近数が
少ない地方を見てみましょう。
| 地方 | 1年の平均接近回数 |
|---|---|
| 1位:北海道 | 1.63回 |
| 2位:北陸地方 | 2.56回 |
| 3位:東北地方 | 2.58回 |
| 4位:中国地方(山口県以外) | 2.93回 |
| 5位:関東・甲信地方 | 3.18回 |
| 6位:近畿地方 | 3.19回 |
| 7位:四国地方 | 3.31回 |
台風の被害を避けるなら、
太平洋側から離れた東北側や北海道が
他の地域より安全と言えそうです。
沖縄から関東にかけて
台風が接近しやすいのは、日本の東に発生する
太平洋高気圧と西から東に吹く偏西風という
2つの現象によるものです。
台風は太平洋高気圧を回り込むようにして
移動し、さらに偏西風によって東側に
流されていきます。
ゲリラ豪雨の発生が少ない都道府県ランキング
近年増加している局地的な大雨(ゲリラ豪雨)
について見てみましょう。
| 都道府県 | 2023年から過去5年の平均回数 |
|---|---|
| 1位:香川県 | 340回 |
| 2位:神奈川県、大阪府 | 370回 |
| 3位:佐賀県 | 390回 |
| 4位:埼玉県 | 550回 |
| 5位:鳥取県 | 600回 |
| 6位:徳島県 | 610回 |
| 7位:山梨県 | 620回 |
ゲリラ豪雨は全国的に比較的高頻度で
発生しているため、どの都道府県でも
完全には避けられません。
さらに、今後は地球温暖化の影響で
ゲリラ豪雨が頻発すると予測されています。
参考リンク:
ウェザーニューズ
ゲリラ雷雨の発生回数と特徴
総合的に災害リスクが低い都道府県トップ3
災害の種類別に見てきましたが、
総合的に見て自然災害が少なく、
移住を検討する際におすすめの
都道府県はどこなのでしょうか?
※2021年を対象とした比較
参考リンク:
総務省 統計局 第29章 災害・事故
1位:山梨県
2021年に山梨県で発生した
自然災害の被害は、
負傷者数が3人、床上浸水が1件と
非常に少なくなっています。
山梨県で自然災害の被害が少ない理由は、
県主導で災害対策に
積極的に取り組んできたからです。
2019年、山梨県は東日本台風によって
道路が一週間寸断され、
経済・観光に大きなダメージを受けました。
この過去の被害を教訓にして、
山梨県は以下のような災害対策を
実践しています:
- 治水・砂防事業による水害対策
- 太陽光発電システムの導入支援
- 倒木被害を抑えるための樹木事前伐採
- 電柱倒壊による停電を防ぐための
電線類地中化事業
参考リンク:
山梨県公式サイト
山梨県の取り組み 強靱化計画について
大きな被害を受けたからこそ
山梨県は対策を徹底し、
自然災害の被害が少ない都道府県として
評価されています。
しかしながら、富士山噴火という
大きな災害リスクを抱えているのも事実です。
2位:群馬県
2021年に群馬県で発生した
自然災害の被害は、
負傷者数が4人、床下浸水が4件、
河川の被害が1件となっています。
2019年の台風19号上陸時、
群馬県は土砂崩れによって
死者4人の被害が出ました。
住宅の全壊やライフラインの寸断も
起きています。
自然災害による被害を抑えるため、
群馬県は「ぐんま5つのゼロ宣言」を発表し、
防災マップの周知や、停電をなくすための
再生可能エネルギープロジェクトにより、
災害対策を充実させています。
参考リンク:
群馬県公式サイト
『ぐんま5つのゼロ宣言』
3位:奈良県
2021年に奈良県で発生した
自然災害の被害は、
床下浸水が10件、河川の被害が1件でした。
奈良県は日本一災害に強い県を目標に掲げ、
防災情報の提供や避難経路の整備などに
力を入れています。
また、地震の回数が少ないことも特徴で、
地震発生回数ランキングでも4位に
入っています。
参考リンク:
奈良県公式サイト
県民情報 防災・危機管理ページ
災害に強い都市は?「生き残る街」ランキング
都道府県単位だけでなく、
市町村レベルではどうでしょうか?
2012年に発表された
『大地震が来ても「最後まで生き残る街」
ランキング』では、首位は福岡市でした。
このランキングでは、
都道府県単位で大地震のリスク分析
をして相対的に安全性の高い上位15の
都道府県を抽出し、市単位で生活利便
性や建物安全性を分析しています。
木造率や建物の老朽化率から倒壊や
火災延焼の危険性が低い自治体を
選び出した結果、福岡市が首位と
なりました。同ランキングでは福岡市について、
「過去に福岡市を中心とする大地震
はなく、大きな被害報告もない。
非木造率が高く、老朽化した建物が
少ないことからも、建物倒壊、
火災延焼などのリスクが低い。
また人口当たりの店舗数、
商品販売数、医師の数も多い」
としています。福岡市に続く第2位は福岡県久留米市、
引用:フクリパ 福岡の今と未来をつむぐ
第3位は山口市と熊本市でした。
ただし、2016年4月の熊本地震
(M7.3)の発生後、熊本県は
企業誘致用Webサイトに掲載していた
「過去120年間マグニチュード7以上
の地震は発生していない」との文章を
削除しています。
これは、過去のデータだけでは
将来の災害を完全に予測できないことを
示す例と言えるでしょう。
富山県も注目の災害リスク低地域
もう一つ注目したい県が富山県です。
富山県は地震と台風被害が少なく、
他県と同様自然災害リスクが低い県として
有名です。
県のデータによると、
1991年から2020年までの30年間で
震災回数が全国最小であり、
2009年~2018年までの10年間、
台風などによる水害被害累積額が
もっとも低い都道府県の1つとなっています。
県庁所在地である富山市は
豪雪地帯の1つとされますが、
主に積雪量が多いのは山間部であり、
平野部は比較的降雪量が少なく、
他の災害も極端に少ないことから
安全に暮らしやすい県といえそうです。
参考リンク:
移住STYLE 災害が少ない県はどこ?
大都市特有の災害リスク
一方で、大都市には
特有の災害リスクがあることも
忘れてはなりません。
以下に、防災面から見た大都市の
6つのリスクを紹介します:
リスク1:人口集中と施設の高密高層化
人が増えると居住スペースが必要になり、
空間を求めて高層化する傾向があります。
施設も集中するため高密高層化になり、
災害時に以下のようなリスクが生じます:
- 東日本大震災時には高層ビルが
大きく揺れ、最長13分間、最大108cmの
揺れが観測された(長周期地震動) - エレベーターの故障が多く報告された
- 電気・水道・ガスなどのインフラが
ストップすれば、高層階では孤立する
リスクがある
リスク2:新旧が混在した街
都市は一気に作られたものではなく、
次第に大きくなっていくため、
住居や施設の建設時期はバラバラです。
古い建物は新しい耐震基準に対応しておらず、
災害時に大きなリスクとなります:
- 阪神淡路大震災では死者の8割が
建物の倒壊による窒息死もしくは圧死 - 昭和56年の新耐震基準以前の建物の
全壊・半壊率は約7割だった - 古い木造住宅の倒壊により火災が発生し、
木造住宅密集地では大規模火災へと
発展するリスクがある
リスク3:地盤沈下や軟弱地盤
東京や大阪には広大な埋め立て地があり、
地盤の弱い土地の上に
多くの建物が建っています:
- 東日本大震災では東京、
千葉、埼玉の各地で液状化が発生 - 家が傾いたり、マンホールが
隆起したりする被害があった - 基礎が浅い一軒家では液状化による
被害が見られる一方、基礎を地下深くまで
打ち込むマンションでは傾きなどは
見られていない
リスク4:複雑な地下空間
大都市の地下は複雑に地下鉄が走り、
地下の商業施設も発展しています:
- 地震による破壊で外に出られなくなる
リスク - 冠水、浸水などで地下鉄が
閉鎖されるリスク - 閉じ込められる脅威がある
リスク5:大量消費するエネルギー
人が多いとそれだけエネルギーを消費します:
- ガソリンスタンドが各所にあり、
港湾内には石油コンビナートがある - 平常時には安全に管理されている
エネルギーが災害時には火災や爆発の
原因となるリスク
リスク6:移動の多さと人間関係の希薄化
都会では住居と職場が
離れていることが珍しくありません:
- 災害時に家族と離れている可能性が高い
- 地域コミュニティのつながりが
希薄なため、災害時の助け合いが
難しい場合がある
近い将来懸念される南海トラフ巨大地震
これまで比較的災害の少ない地域を
見てきましたが、
現在日本で最も警戒されている
大規模災害が「南海トラフ巨大地震」です。
政府の地震調査委員会が今後30年以内に
発生する確率を「80%程度」としており、
最新の被害想定が2025年3月に
発表されました。
最大でマグニチュード9クラスとされ、
激しい揺れと大津波が超広域に及ぶと
予測されています:
- 震度6弱以上が神奈川県から鹿児島県に
かけての24府県600市町村 - 震度7が静岡県から宮崎県にかけての
10県149市町村 - 津波3メートル以上が福島県~沖縄県に
かけての25都府県 - 津波10メートル以上が関東~九州に
かけての13都県 - 高知県と静岡県では局地的に30メートルを
超える津波のおそれ
被害想定では、死者は最悪で29万8000人に
のぼり、前回の32万3000人から8%ほどの
減少にとどまっています。
また、避難生活の中で体調を悪化させて
亡くなる「災害関連死」も今回初めて試算
され、最大で5万2000人と予測されています。
この数字は東日本大震災のおよそ13倍に
のぼり、避難者の生活環境の改善などが
急務となっています。
自分の住む地域の災害リスクを知る方法
「災害が少ない県」があることは
分かりましたが、誰もがすぐに引っ越せる
わけではありません。
そこで大切なのは、
自分が住んでいる地域の災害リスクを
正確に把握することです。
ハザードマップの活用方法
ハザードマップとは
「災害予測」と「被害の範囲」を
地図化したもので、『防災マップ』とも
呼ばれます。
マップには、被害想定区域、避難経路、
避難場所、防災関係施設の位置など
地域ごとの危険予測や避難に関する
情報が示されています。
特に、一戸建ての住まいの購入を
検討している人にとっては、
自宅の被災を防ぐ、
または自宅が被災した場合の被害を
最小限に抑えるために、
必ず確認しておくべきツールといえます。
ハザードマップの入手方法
- 各自治体のホームページ
- 国土交通省
ハザードマップポータルサイト:
https://disaportal.gsi.go.jp/3 - 地震本部ホームページ
(政府 地震調査研究推進本部):
https://www.jishin.go.jp/3
重ねるハザードマップなど、
パソコンやスマートフォンがあれば
簡単にハザードマップの情報を
利用できるツールもあります。
自宅の安全性を確認する
自分の住む地域の災害リスクを把握したら、
次は住宅そのものの安全性を確認しましょう。
建物の耐震基準をチェック
建築基準法は時代と共に変化してきました。
特に重要なのは1981年に改正された
「新耐震基準」です。
これは「極めて稀に起こる大地震でも
倒壊しないこと」を前提にしています。
まずは、自分の住んでいるマンションや家が、
どの耐震基準を満たしているのかを
知っておくことが重要です。
ただし、熊本地震の調査では
1981年から2000年5月までに建てられた
住宅のうち、9.1%が倒壊・崩壊した
という報告もあります。
さらに2000年基準は、
1995年の阪神・淡路大震災を踏まえ、
木造住宅の耐震性を強化した耐震基準です。
2000年6月1日以降に建築確認申請が
行われた建物が対象で、
現行の耐震基準とも呼ばれています。
建築年数だけで安全性を判断するのではなく、
必要に応じて耐震診断を受けることを
おすすめします。
参考リンク・出典:
国土技術政策総合研究所ホームページ
避難所の重要性と課題
どんなに災害対策をしていても、
いざという時に避難が
必要になる場合があります。
そんな時に重要となるのが「避難所」です。
避難所生活の現実
避難所は、被災者の命を
一定期間守り続ける拠点です。
東日本大震災や阪神・淡路大震災、
中越地震の統計によると、
避難所生活は最低でも1カ月は続く可能性が
あります。
また、発災直後は多くの被災者が避難所に
殺到するため混乱が予想されます。
救助活動の現場では「災害後の72時間」が
勝負だと言われており、この時間帯は
特に混乱します。
避難所で直面する6つの課題
災害発生直後から数日間は、
避難所を運営する職員にとって最も忙しく、
ストレスが溜まりやすい期間です。
避難所ではどのような課題が
発生するのでしょうか?
- 断水:
水道の給水が途絶え、飲料水の不足だけ
でなく、トイレが使えない、入浴できないといった問題が発生 - 停電:
電力供給が途絶え、特に夜間は不安や
心配が大きくなる - 食料・救援物資等の不足:
必要な物資が届かないことで不安が高まる - 場所取り等の避難者同士のトラブル:
限られたスペースでの生活によるストレス - 避難所運営職員の業務負担増大:
対応する職員の疲労 - 感染症のリスク:
密集した環境でのクラスター発生の可能性
このような環境を改善すべく、
政府の防災対策をはじめ、
各地方自治体の防災対策室・危機管理室が
環境改善策を講じています。
また、災害時は自治体の職員も被災者です。
地域住民で共助することが不可欠です。
災害に備える具体的な対策
どこに住んでいても災害リスクは
ゼロにはなりません。
では、私たちはどのように
備えればよいのでしょうか?
自宅の防災対策
- 耐震補強:
必要に応じて耐震診断を受け、
弱点があれば補強工事を検討しましょう。 - 家具の固定:
震度4〜5強の地震でも家具が転倒する
危険があります。転倒防止器具、L字金具
などで固定することが重要です。 - 非常用備蓄:
最低3日分、できれば1週間分の水と食料を
備蓄しておきましょう。 - 防災グッズの準備:
懐中電灯、携帯ラジオ、モバイルバッテリ
ー、救急セットなどを用意しておきます。
避難計画の作成
- 避難経路の確認:
ハザードマップを活用して、
自宅から避難所までの安全なルートを
事前に確認しておきましょう。 - 集合場所の決定:
家族が離れ離れになった場合の
集合場所を決めておきます。 - 避難のタイミング:
「逃げ遅れゼロ」を目指し、
危険を感じたら迷わず避難する心構えを
持ちましょう。
停電対策として注目の太陽光発電+蓄電池
近年、災害時の停電対策として
「太陽光発電と蓄電池の組み合わせ」
が注目されています。
災害時にライフラインが途絶えても、
太陽光で発電した電気を蓄電池に貯めて
おけば、最低限の電力を確保できます。
特に長期的な停電が予想される
大規模災害時には心強い味方となるでしょう。
費用対効果を考慮しながら、
導入を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ:どこに住んでも「備え」が最大の防御
今回、
「災害大国日本。一番安全な場所とは?」
というテーマで様々な角度から
検討してきました。
結論としては、残念ながら
「まったく災害のない県」は
存在しないというのが現実です。
例えば、地震が少ない滋賀県でも
琵琶湖での津波リスクがあり、
台風被害の少ない香川県でも南海トラフ地震
の災害リスクが存在しています。
災害のリスクが低い地域を選ぶことは
一つの選択肢ですが、どこに住んでいても
「災害はいつか起こるもの」と想定して
適切な対策を講じることが何よりも重要です。
私たち一人ひとりができることは、
以下の3つに集約されます:
- 知る:
自分の住む地域の災害リスクを
ハザードマップで確認する - 備える:
家の耐震性を高め、防災グッズを準備する - 行動する:
いざという時に迷わず避難できるよう、
避難計画を立てておく
「備えあれば憂いなし」という
言葉がありますが、防災においては
まさにその通りです。
この記事が皆さんの防災意識を高め、
具体的な行動につながれば幸いです。
最後に、
災害時に本当に大切なのは「命」です。
物的被害は後から回復できますが、
命は取り返せません。
危険を感じたら迷わず避難する勇気を
持ちましょう。
次回もSONAEAREBAでは、
皆さんの「備え」に役立つ情報を
お届けします。
それでは、
また次回の記事でお会いしましょう!